2011年02月28日
仰清正公 №18 しんがり
-仰清正公- №18 しんがり
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第18話「しんがり」
あとになって この長久手の戦は羽柴軍の敗戦とされるが、かろうじてそれを避けた堀秀政の軍はよく戦った。そこへ加藤虎之助の軍が救援に駆けつける。
だが長久手城、岩崎城を落とした池田軍はそこへとどまりすぎ、徳川軍の逆襲に敗れる。
羽柴軍の動きに対して徳川軍はすばやく勢力を移動し、その感激を埋めるために加藤らは駆けずり回らねばならなかった。大勢力で動きの鈍い羽柴勢に対して、野戦上手な徳川軍は隙を突こうとする。
図体の大きい羽柴の主力が本営に引き上げるのに、秀吉が加藤虎之助と堀尾茂助(堀尾吉晴)に命じたのは「しんがり・殿」役であった。しんがりとは、軍列の最後尾をいう。主力を守りながら追撃してくる敵を迎え撃つ。この迎撃に力を入れすぎれば本体に遅れ、その間隙を敵の遊軍に狙われ、本体そのものに損害が及ぶ。つまり、しんがり軍は、本体との距離を詰めず開けず、敵と戦いながら後退、実は本体と同じ速度で前進しなければならないのである。
このような野戦、それもてったい劇でのしんがり軍は非常に難しいものだったが、加藤・堀尾の軍は、タイマツを赤々と点し、鉄砲隊、弓隊、槍隊の三重の装備で、浅く攻めては堅く守るという戦術で、しんがり軍の役目を果たした。
このしんがり軍のことを、当時の言葉なのか方言なのか「しっぱらり」というらしいですよ。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第18話「しんがり」
あとになって この長久手の戦は羽柴軍の敗戦とされるが、かろうじてそれを避けた堀秀政の軍はよく戦った。そこへ加藤虎之助の軍が救援に駆けつける。
だが長久手城、岩崎城を落とした池田軍はそこへとどまりすぎ、徳川軍の逆襲に敗れる。
羽柴軍の動きに対して徳川軍はすばやく勢力を移動し、その感激を埋めるために加藤らは駆けずり回らねばならなかった。大勢力で動きの鈍い羽柴勢に対して、野戦上手な徳川軍は隙を突こうとする。
図体の大きい羽柴の主力が本営に引き上げるのに、秀吉が加藤虎之助と堀尾茂助(堀尾吉晴)に命じたのは「しんがり・殿」役であった。しんがりとは、軍列の最後尾をいう。主力を守りながら追撃してくる敵を迎え撃つ。この迎撃に力を入れすぎれば本体に遅れ、その間隙を敵の遊軍に狙われ、本体そのものに損害が及ぶ。つまり、しんがり軍は、本体との距離を詰めず開けず、敵と戦いながら後退、実は本体と同じ速度で前進しなければならないのである。
このような野戦、それもてったい劇でのしんがり軍は非常に難しいものだったが、加藤・堀尾の軍は、タイマツを赤々と点し、鉄砲隊、弓隊、槍隊の三重の装備で、浅く攻めては堅く守るという戦術で、しんがり軍の役目を果たした。
このしんがり軍のことを、当時の言葉なのか方言なのか「しっぱらり」というらしいですよ。(JS)
Posted by たわらや at
22:37
│Comments(0)
2011年02月28日
駅弁ばんざい №12 根室本線 厚岸駅 かきめし
-駅弁ばんざい- №12
根室本線 厚岸駅 かきめし
◆ 駅弁ばんざい 厚岸駅
かきめし
(氏家待合所 950円)

初めて北海道に旅をしたのは、高校3年生になる前の春休みのことでした。昭和62(1987)年03月20日に旅立ち、山陽・東海道・東北新幹線を乗り継いで、青森からは青函連絡船・十和田丸で函館へ。見る景色全てが感動でした。
03月24日、札幌22:25発(急行まりも号)第411列車に乗り込みました。翌朝06:10に釧路着。この日、最東端の納沙布岬を目指しました。
途中の厚岸駅で買った「かきめし」が美味しかったこと。私にとりまして、印象に残る駅弁の一つです。
厚岸というとなんと言っても、厚岸湾で採れる牡蠣。
長方形の弁当折。紐を解き、緑色の弁当包みを取り、上蓋をめくる。
磯の香りと、牡蠣の炊込み御飯があらわれます。
この時に同伴した仲のよい二人の友人も、
「わ~っ」と思わず声を上げました。
厚岸名産の牡蠣を使い、牡蠣の煮汁を入れて炊きこんだ御飯。トッピングに、ひじき、あさり、つぶ貝の海の幸を載せ、ちょっと塩辛い蕗。ぎっしりとごはんが詰まっていました。
「旨い~」
車窓に広がる湿原や海の景色を眺めながら、ご当地の幸を頂いたこと。旅の醍醐味そのものです。
当時は高校生でしたので、カップ酒で一杯という訳には行きませんでしたが、今ならば、きっとカップ酒をちびちびやりながら「かきめし」を食べると思います。
あっ、もう一度、根室本線の厚岸駅に行ってみたいなぁ~。
根室本線 厚岸駅 かきめし
◆ 駅弁ばんざい 厚岸駅
かきめし
(氏家待合所 950円)

初めて北海道に旅をしたのは、高校3年生になる前の春休みのことでした。昭和62(1987)年03月20日に旅立ち、山陽・東海道・東北新幹線を乗り継いで、青森からは青函連絡船・十和田丸で函館へ。見る景色全てが感動でした。
03月24日、札幌22:25発(急行まりも号)第411列車に乗り込みました。翌朝06:10に釧路着。この日、最東端の納沙布岬を目指しました。
途中の厚岸駅で買った「かきめし」が美味しかったこと。私にとりまして、印象に残る駅弁の一つです。
厚岸というとなんと言っても、厚岸湾で採れる牡蠣。
長方形の弁当折。紐を解き、緑色の弁当包みを取り、上蓋をめくる。
磯の香りと、牡蠣の炊込み御飯があらわれます。
この時に同伴した仲のよい二人の友人も、
「わ~っ」と思わず声を上げました。
厚岸名産の牡蠣を使い、牡蠣の煮汁を入れて炊きこんだ御飯。トッピングに、ひじき、あさり、つぶ貝の海の幸を載せ、ちょっと塩辛い蕗。ぎっしりとごはんが詰まっていました。
「旨い~」
車窓に広がる湿原や海の景色を眺めながら、ご当地の幸を頂いたこと。旅の醍醐味そのものです。
当時は高校生でしたので、カップ酒で一杯という訳には行きませんでしたが、今ならば、きっとカップ酒をちびちびやりながら「かきめし」を食べると思います。
あっ、もう一度、根室本線の厚岸駅に行ってみたいなぁ~。
Posted by たわらや at
22:15
│Comments(0)
2011年02月27日
仰清正公 №17 小牧長久手の戦い
-仰清正公- №17 小牧・長久手の戦い
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第17話「小牧・長久手の戦い」
天正12年。伊勢長島にいた織田信勝は天下が自分から遠ざかっていくのにいらだっていた。弟の信孝はすでに混乱の中自害している。信勝は羽柴秀吉を信じる老臣を抹殺して将来を浜松にいる徳川家康に頼った。
秀吉が大阪城を築いた同時期、美濃(岐阜)、尾張、伊勢の諸国は混乱が続いていた。流れは秀吉か家康になるのだろうが、どの国の誰がどちら側につくか、見通せなかった。
その中で織田信勝は家康を頼った。家康は小牧山に出張ってきた。
いちおう天下を治めた形の羽柴秀吉は混乱の美濃、尾張、伊勢地方を平定しなければならない。浜松にいた徳川家康が織田信勝に頼られたとはいえ、この地に出張ってくるとなればこれに応じなければならない。そこで十二万五千の陣容で出動する。これが歴史にいわれる小牧、長久手の戦いである。
徳川勢は羽柴軍の三分の一、五万の軍勢だがこちらは野戦に強い。一方、羽柴軍は城攻めが得意である。結果は大きい合戦にはならなかったが、局地戦で徳川軍は勝利を挙げた。
羽柴軍は小牧のの戦いに敗れたが、羽柴、徳川軍はそれぞれ戦略を繰り返すのみで大きい合戦はなく、それぞれ大阪城、清洲城に戻る。そもそもこの戦いは、織田信勝が羽柴秀吉を離れ、徳川家康を頼ったことに原因があった。その信勝自身が伊勢長島に戻り、このままではどうにもならないと見て、秀吉に詫を入れる形になった。
こうして、秀吉、家康の間には決戦はおこなわれなかった。そして秀吉、徳川家康、織田信勝と和睦をすることになります。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第17話「小牧・長久手の戦い」
天正12年。伊勢長島にいた織田信勝は天下が自分から遠ざかっていくのにいらだっていた。弟の信孝はすでに混乱の中自害している。信勝は羽柴秀吉を信じる老臣を抹殺して将来を浜松にいる徳川家康に頼った。
秀吉が大阪城を築いた同時期、美濃(岐阜)、尾張、伊勢の諸国は混乱が続いていた。流れは秀吉か家康になるのだろうが、どの国の誰がどちら側につくか、見通せなかった。
その中で織田信勝は家康を頼った。家康は小牧山に出張ってきた。
いちおう天下を治めた形の羽柴秀吉は混乱の美濃、尾張、伊勢地方を平定しなければならない。浜松にいた徳川家康が織田信勝に頼られたとはいえ、この地に出張ってくるとなればこれに応じなければならない。そこで十二万五千の陣容で出動する。これが歴史にいわれる小牧、長久手の戦いである。
徳川勢は羽柴軍の三分の一、五万の軍勢だがこちらは野戦に強い。一方、羽柴軍は城攻めが得意である。結果は大きい合戦にはならなかったが、局地戦で徳川軍は勝利を挙げた。
羽柴軍は小牧のの戦いに敗れたが、羽柴、徳川軍はそれぞれ戦略を繰り返すのみで大きい合戦はなく、それぞれ大阪城、清洲城に戻る。そもそもこの戦いは、織田信勝が羽柴秀吉を離れ、徳川家康を頼ったことに原因があった。その信勝自身が伊勢長島に戻り、このままではどうにもならないと見て、秀吉に詫を入れる形になった。
こうして、秀吉、家康の間には決戦はおこなわれなかった。そして秀吉、徳川家康、織田信勝と和睦をすることになります。(JS)
Posted by たわらや at
23:00
│Comments(0)
2011年02月27日
知っているようで知らない酒の話№131いつ生まれた吟醸の言葉
-知っているようで知らない酒の話- №131
いつ生まれた「吟醸」という言葉 後編
■ 吟醸酒の戦後は

写真は、「昭和天皇の御大典の儀の地方選酒になり、加藤吉平商店の蔵の前で、当時の蔵役との記念写真。」。この写真が何を物語っているか、たいへんに興味深いことがあります。写真は昭和初期のこと。この前掛けに「吟醸」という文字があります。日本で初めて吟醸という言葉が登場した時の写真である(と思う)。
現在では誰もが吟醸酒という言葉に馴染みがあるが、高度に精米して醸した日本酒=吟醸酒が誕生したのがこの時代である。それまで、お米を磨く手段としては水車精米か、人力による足踏み精米でありました。
水車精米にしろ、足踏み精米にしろ精米歩合90%程度しか磨くことができなかった。現在の基準では精米歩合60%以下が吟醸酒で、50%以下が大吟醸酒であるが、この精米が可能にしたのが、広島の佐竹利市氏が発明した「佐竹式竪型精米機」の誕生だ。動力に電気を使い、現在の精米機の原点といえる機械を完成させた。高度精白した原料米を低温でじっくりと醗酵させると、この世のものとは思えぬ芳しい香気が漂う美酒が生まれました。これを吟醸酒と評しました。その当時吟醸酒を加藤吉平商店は発売していたことを物語っています。
残念なことに、高度に精米する吟醸酒は、暗い時代を迎えてしまいます。米が国の統制下におかれ、贅沢に米を使う吟醸酒は醸造が認められなくなりました。
もともと吟醸酒は明治40年から隔年に開催された全国新酒品評会の出品酒として各地の銘醸蔵が腕を競うため醸しました。昭和13年を最後に戦後まで開催が中止されました。
戦後、日本酒を醸造することはできるようになったが、吟醸酒の復活はそれよりもっともっと後のことになります。昭和44年に「梵」(加藤吉平商店)で戦後初の吟醸酒発売になるが、みんなが吟醸酒を認知するのは昭和50年代、60年代。ようやく吟醸酒の戦後がやってきたのでした。吟醸酒にとっては長い長い戦争だったように思います。
■ 梵 純米大吟醸 無濾過生原酒
1800ml:3780円(税込)
原料米:兵庫県産 山田錦
精米歩合:52%
日本酒度:+5.0
酸度:1.3
アミノ酸度:?
アルコール度数:17.5%
使用酵母:KATO(自社酵母)9号酵母
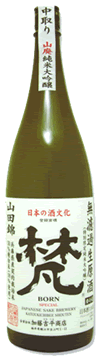
◆ 梵・唯一の生酒
梵・山廃純米大吟醸無濾過生原酒
【こんな人に飲んで欲しい】
「山廃」という言葉が日本酒のラベルに登場します。これは昔ならがの伝統的な技法で仕込む一種の酒づくりの工法(流儀)です。山廃は味わい深いタイプの酒が多いのですが、このお酒は山廃の中では最も綺麗な味わいに仕上がっています。「山廃」の入門酒としてお薦めします。
【お手ごろな価格の大吟醸】
やや力強い原酒の骨太い味わい。吟醸香りも高く濃醇旨口タイプ。香味ともにパワフルながらバランスがよく生酒ながらキレがいいので、滑らかなので飲み易さを感じます。濃いけどスムーズ。
原料米は兵庫山田錦。山廃純米大吟醸ですので、本当に美味しいです。
原酒でアルコール度数が高いので、ロックにしても楽しめます。上手に凍らせて、氷酒などにしても面白いと思います。
大吟醸はたいへん高価な酒です。このお酒も安くはありませんが、リズナブルな価格です。価格以上に酒が素晴らしい酒です。
いつ生まれた「吟醸」という言葉 後編
■ 吟醸酒の戦後は

写真は、「昭和天皇の御大典の儀の地方選酒になり、加藤吉平商店の蔵の前で、当時の蔵役との記念写真。」。この写真が何を物語っているか、たいへんに興味深いことがあります。写真は昭和初期のこと。この前掛けに「吟醸」という文字があります。日本で初めて吟醸という言葉が登場した時の写真である(と思う)。
現在では誰もが吟醸酒という言葉に馴染みがあるが、高度に精米して醸した日本酒=吟醸酒が誕生したのがこの時代である。それまで、お米を磨く手段としては水車精米か、人力による足踏み精米でありました。
水車精米にしろ、足踏み精米にしろ精米歩合90%程度しか磨くことができなかった。現在の基準では精米歩合60%以下が吟醸酒で、50%以下が大吟醸酒であるが、この精米が可能にしたのが、広島の佐竹利市氏が発明した「佐竹式竪型精米機」の誕生だ。動力に電気を使い、現在の精米機の原点といえる機械を完成させた。高度精白した原料米を低温でじっくりと醗酵させると、この世のものとは思えぬ芳しい香気が漂う美酒が生まれました。これを吟醸酒と評しました。その当時吟醸酒を加藤吉平商店は発売していたことを物語っています。
残念なことに、高度に精米する吟醸酒は、暗い時代を迎えてしまいます。米が国の統制下におかれ、贅沢に米を使う吟醸酒は醸造が認められなくなりました。
もともと吟醸酒は明治40年から隔年に開催された全国新酒品評会の出品酒として各地の銘醸蔵が腕を競うため醸しました。昭和13年を最後に戦後まで開催が中止されました。
戦後、日本酒を醸造することはできるようになったが、吟醸酒の復活はそれよりもっともっと後のことになります。昭和44年に「梵」(加藤吉平商店)で戦後初の吟醸酒発売になるが、みんなが吟醸酒を認知するのは昭和50年代、60年代。ようやく吟醸酒の戦後がやってきたのでした。吟醸酒にとっては長い長い戦争だったように思います。
■ 梵 純米大吟醸 無濾過生原酒
1800ml:3780円(税込)
原料米:兵庫県産 山田錦
精米歩合:52%
日本酒度:+5.0
酸度:1.3
アミノ酸度:?
アルコール度数:17.5%
使用酵母:KATO(自社酵母)9号酵母
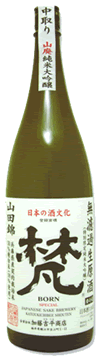
◆ 梵・唯一の生酒
梵・山廃純米大吟醸無濾過生原酒
【こんな人に飲んで欲しい】
「山廃」という言葉が日本酒のラベルに登場します。これは昔ならがの伝統的な技法で仕込む一種の酒づくりの工法(流儀)です。山廃は味わい深いタイプの酒が多いのですが、このお酒は山廃の中では最も綺麗な味わいに仕上がっています。「山廃」の入門酒としてお薦めします。
【お手ごろな価格の大吟醸】
やや力強い原酒の骨太い味わい。吟醸香りも高く濃醇旨口タイプ。香味ともにパワフルながらバランスがよく生酒ながらキレがいいので、滑らかなので飲み易さを感じます。濃いけどスムーズ。
原料米は兵庫山田錦。山廃純米大吟醸ですので、本当に美味しいです。
原酒でアルコール度数が高いので、ロックにしても楽しめます。上手に凍らせて、氷酒などにしても面白いと思います。
大吟醸はたいへん高価な酒です。このお酒も安くはありませんが、リズナブルな価格です。価格以上に酒が素晴らしい酒です。
Posted by たわらや at
12:00
│Comments(0)
2011年02月26日
仰清正公 №16 大石運び
-仰清正公- №16 大石運び
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第16話「大石運び」
北の庄を落城させ、長浜に戻った加藤虎之助清正は、かつての幼馴染、今は武将として活躍している森本利吉、飯田才八の二人に新しい名前を授けた。
森本利吉は森本義太夫、飯田才八は飯田角兵衛となる。天承11年、三人とも22歳であった。
北の庄に柴田勝家を滅ぼした羽柴秀吉は、全国に号令をかけるための城は大阪に築こうと思っていた。織田信長も同じような構想をもっていたらしいが、明智光秀の反逆にあって実現できなかった。
場所は信長が長く争ったのち和睦した石山本願寺である。ここは河内平野の米の収穫が期待され、城の脇には淀川がある。これを導けば堀が築けるし、淀川を通じて海にも開けている。
八町四方の石山寺を中心に、二の丸三の丸を築くという大構想であった。この石山に武将を招いた秀吉は、北の庄一番槍は加藤虎之助とし、四百七十石の知行に三千石が加増された。ともに福島市松、片桐助作、平野権兵衛、脇坂陣内、粕谷助右衛門なども加増された。
大阪城の普請奉行は浅野長政、益田長盛に決まった。天承11年7月、秀吉が大阪城築城にかかったとき、全国から一万人の人即が集められた。
秀吉は石山の敷地に宿泊用の小屋を建てた。それから、八層の天主の建築にかかる。この重曹の天主を支える石は相当大きいものではなければならない。蜂須賀正勝はその大石が小豆島にあることを告げ、運搬を加藤虎之助に明治、その辺の地理に明るい男として正林隼人・しょうばやしはやと・を紹介してよこした。その男は「摂津の国高槻の在、正林の生まれで土地の名を名乗り正林隼人」と名乗った。経歴を聞くと「荒木摂津の守に仕え一千石の知行をいただいていた」という。浪人の後小豆島に暮らしたのでどこにどんな石があるかわかるという。蜂須賀正勝には人足として仕え、見出されたとのこと。
小豆島の西南に問前島というところがあり、ここを虎之助は本陣として石を切り出した。五十畳敷きの大石を大船に乗せ、周囲に小舟を浮き代わり
にして淀川から陸揚げし、大阪城壁の京橋口に据えられた。これを台石として石垣が築かれた。
正林隼人は、小豆島での働きで虎之助の家来に取り立てられた。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第16話「大石運び」
北の庄を落城させ、長浜に戻った加藤虎之助清正は、かつての幼馴染、今は武将として活躍している森本利吉、飯田才八の二人に新しい名前を授けた。
森本利吉は森本義太夫、飯田才八は飯田角兵衛となる。天承11年、三人とも22歳であった。
北の庄に柴田勝家を滅ぼした羽柴秀吉は、全国に号令をかけるための城は大阪に築こうと思っていた。織田信長も同じような構想をもっていたらしいが、明智光秀の反逆にあって実現できなかった。
場所は信長が長く争ったのち和睦した石山本願寺である。ここは河内平野の米の収穫が期待され、城の脇には淀川がある。これを導けば堀が築けるし、淀川を通じて海にも開けている。
八町四方の石山寺を中心に、二の丸三の丸を築くという大構想であった。この石山に武将を招いた秀吉は、北の庄一番槍は加藤虎之助とし、四百七十石の知行に三千石が加増された。ともに福島市松、片桐助作、平野権兵衛、脇坂陣内、粕谷助右衛門なども加増された。
大阪城の普請奉行は浅野長政、益田長盛に決まった。天承11年7月、秀吉が大阪城築城にかかったとき、全国から一万人の人即が集められた。
秀吉は石山の敷地に宿泊用の小屋を建てた。それから、八層の天主の建築にかかる。この重曹の天主を支える石は相当大きいものではなければならない。蜂須賀正勝はその大石が小豆島にあることを告げ、運搬を加藤虎之助に明治、その辺の地理に明るい男として正林隼人・しょうばやしはやと・を紹介してよこした。その男は「摂津の国高槻の在、正林の生まれで土地の名を名乗り正林隼人」と名乗った。経歴を聞くと「荒木摂津の守に仕え一千石の知行をいただいていた」という。浪人の後小豆島に暮らしたのでどこにどんな石があるかわかるという。蜂須賀正勝には人足として仕え、見出されたとのこと。
小豆島の西南に問前島というところがあり、ここを虎之助は本陣として石を切り出した。五十畳敷きの大石を大船に乗せ、周囲に小舟を浮き代わり
にして淀川から陸揚げし、大阪城壁の京橋口に据えられた。これを台石として石垣が築かれた。
正林隼人は、小豆島での働きで虎之助の家来に取り立てられた。(JS)
Posted by たわらや at
23:00
│Comments(0)
2011年02月26日
コラム・呑んどっと №20 寿司の古今を考える
-コラム・呑んどっと-№20
寿司の古今を考える
■ 富山駅 駅弁 『特選ますのすし』

(㈱源 1700円)
最近は百貨店の催事で、全国有名駅弁大会がよく行われています。全国各地の旧国鉄を完乗を8年かがりで行った私にとって、とくに印象に残る駅弁が富山駅の『ますのすし』です。駅弁大会でも高い人気の駅弁当です。今年も、私の地元の百貨店で駅弁当大会がありました。もちろん『ますのすし』を買い、お燗酒を飲みながら、ますのすしを食べました。旨かったです。
富山駅『ますのすし』の歴史はたいへんに古い。1912年(明治45年)に発売が開始されています。富山駅の開業は1899年(明治32年)。北陸本線は字のごとく、近畿地方から北陸を結ぶ大動脈。物資輸送もさることながら、駅弁が発売されるようになったのは旅客輸送が増えたからでしょう。
丸い輪っぱに、富山県産のコシヒカリを酢飯にして、朱鷺色の鱒を敷き詰め、笹でくるんだ押し寿司が『ますのすし』です。笹の葉の緑と鱒の朱鷺色が色鮮やかで、まさに駅弁のの芸術品と言っていいような駅弁です。
北陸本線を走る特急の車内テーブルにちょうど載せれる程の大きなになっています。『ますのすし』の箱の中に付属のプラステック製のナイフがついています。それを使って、8等分に割って食べます。押し寿司なので、おなかいっぱいになります。
私も北陸本線を旅する時には、必ず、この『ますのすし』を2つ購入します。1つは、すぐに車内で食べます。もう1つは、お土産にします。賞味期限が切れるのですが、『ますのすし』も押し寿司でありますので、少し時間を経過して美味しくなります。お酢と鱒とシャリが馴染むのでしょうか。どのくらい熟成させるかというと約1~2日。車内で食べるできたての『ますのすし』よりも格段に旨くなります。熟成させたものを売っていればいいのですが、製造する駅弁の会社としては、賞味期限がくれば、販売することはできないため、この熟成『ますのすし』づくりは、購入した人の楽しみな作業になります。
この『ますのすし』は、江戸時代に八代将軍・徳川吉宗が、富山藩主より献上され、たいへん気に入ったということです。きっとその時に吉宗が食した『ますのすし』も熟成した『ますのすし』であったと思います。ちなみに笹の葉は殺菌作用もあるということでくるんであるようです。先人達の美意識と知恵に感服します。
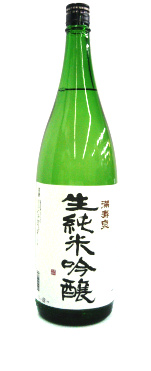
富山のますのすし には 富山の銘酒「満寿泉」がぴったり。
原料米 兵庫産
麹米:山田錦
掛米:山田錦
精米歩合:麹米50%
:掛米40%
日本酒度:非公開
酸 度:非公開
アミノ酸度:非公開
アルコール度数:16~17%
酵 母:
価 格:1800ml 3150円(税込)
■ 寿司の古今を考える
『ますのすし』を食べながら、子どもからこんな質問がきた。
「生の魚を切り身にしてシャリに載せたものが寿司だが、『ますのすし』や『松前寿司』はシャリを押しつぶした押寿司。具を散らしたチラシ寿司など寿司といいながらいろいろあるけど、どう違うのか?」
というものであった。なるほど、寿司(鮨)という名称は同じでも、少しづつ製法の違いを指摘したものであろう。
私なりに調べてみました。
■ 寿司の起源は馴れ寿司
馴れ寿司をご存知でしょうか?。有名なのは、琵琶湖(滋賀県)周辺で食べらている鮒の馴れ寿司が有名です。
太古の昔、冷蔵庫が無かった時代、川や湖・海で獲れた魚を長期保存するために生まれた保存食が馴れ寿司です。魚の持つ、有用な動物性たんぱく質を長期保存する知恵は、我々祖先が編み出した食文化の歴史そのものです。
獲れた魚に塩と飯を混ぜ合わせ、樽などのような容器に入れます。丈上部に蓋をして、蓋の上に重石を置いて圧力をかけます。この状態で、短くて数カ月、もしくは何年もの間この状態を保ちます。
炊いた米が時間と伴に乳酸発酵をし始めます。飯から乳酸が生まれます。乳酸発酵がどんどん進み、その結果、飯状の粒粒は原型をとどめない形になりますが、樽の中は乳酸によりPHが低下します。つまり酸性状態となり、雑菌の繁殖が抑制されるか死滅されます。
これによって、長期保存が可能となるということになります。また、魚のタンパク質は、アミノ酸に分解されます。アミノ酸は旨味の成分ですので、馴れる程に旨味を増すということになります。
臭いは、ちょうど、八丈島などで造られるクサヤの干物に似ています。一種独特の臭いがありますので好き嫌いがはっきり分かれます。
一般的にタンパク質分解酵素を含んだ微生物にはこの系統の臭いがあります。腐敗しているか、発酵しているか、紙一重のような微妙は臭いです。
寒冷な地方では、蒸した飯に加えて、麹米を用いる馴れ寿司もあります。麹の持つ糖化酵素に作用により、発酵を促し、甘みを増す保存食を作り出します。石川県のカブラ寿司、秋田県のハタハタ寿司が麹米を入れた馴れ寿司です。
■ 押し寿司から江戸前へ
馴れ寿司が出来上がるまで、何カ月、何年という時間がかかります。米酢が作られるようになった室町時代後期に、蒸飯に酢を混ぜ、箱に入れてネタを上に置き、重石を置いて食べる押し寿司ができました。
私たちが一般的に想像する寿司は江戸前。シャリの上に新鮮な肴が乗ったものが登場するのは今から200年前の江戸・両国。諸説あるが、文化12(1829)年には文献に登場しています。長期保存食から、気の短い江戸っ子が育んだ直ぐに食べられる寿司まで、時代とともに変化しています。いずれの寿司も晴れの日のご馳走であったことは変わりがないようです。
さて、21世紀は回転寿司からどんな寿司が産まれるのでしょうか?。食の進化を見るもの楽しみの一つです。
寿司の古今を考える
■ 富山駅 駅弁 『特選ますのすし』

(㈱源 1700円)
最近は百貨店の催事で、全国有名駅弁大会がよく行われています。全国各地の旧国鉄を完乗を8年かがりで行った私にとって、とくに印象に残る駅弁が富山駅の『ますのすし』です。駅弁大会でも高い人気の駅弁当です。今年も、私の地元の百貨店で駅弁当大会がありました。もちろん『ますのすし』を買い、お燗酒を飲みながら、ますのすしを食べました。旨かったです。
富山駅『ますのすし』の歴史はたいへんに古い。1912年(明治45年)に発売が開始されています。富山駅の開業は1899年(明治32年)。北陸本線は字のごとく、近畿地方から北陸を結ぶ大動脈。物資輸送もさることながら、駅弁が発売されるようになったのは旅客輸送が増えたからでしょう。
丸い輪っぱに、富山県産のコシヒカリを酢飯にして、朱鷺色の鱒を敷き詰め、笹でくるんだ押し寿司が『ますのすし』です。笹の葉の緑と鱒の朱鷺色が色鮮やかで、まさに駅弁のの芸術品と言っていいような駅弁です。
北陸本線を走る特急の車内テーブルにちょうど載せれる程の大きなになっています。『ますのすし』の箱の中に付属のプラステック製のナイフがついています。それを使って、8等分に割って食べます。押し寿司なので、おなかいっぱいになります。
私も北陸本線を旅する時には、必ず、この『ますのすし』を2つ購入します。1つは、すぐに車内で食べます。もう1つは、お土産にします。賞味期限が切れるのですが、『ますのすし』も押し寿司でありますので、少し時間を経過して美味しくなります。お酢と鱒とシャリが馴染むのでしょうか。どのくらい熟成させるかというと約1~2日。車内で食べるできたての『ますのすし』よりも格段に旨くなります。熟成させたものを売っていればいいのですが、製造する駅弁の会社としては、賞味期限がくれば、販売することはできないため、この熟成『ますのすし』づくりは、購入した人の楽しみな作業になります。
この『ますのすし』は、江戸時代に八代将軍・徳川吉宗が、富山藩主より献上され、たいへん気に入ったということです。きっとその時に吉宗が食した『ますのすし』も熟成した『ますのすし』であったと思います。ちなみに笹の葉は殺菌作用もあるということでくるんであるようです。先人達の美意識と知恵に感服します。
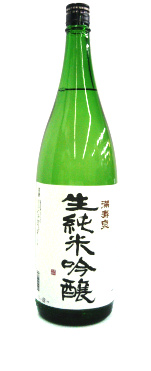
富山のますのすし には 富山の銘酒「満寿泉」がぴったり。
原料米 兵庫産
麹米:山田錦
掛米:山田錦
精米歩合:麹米50%
:掛米40%
日本酒度:非公開
酸 度:非公開
アミノ酸度:非公開
アルコール度数:16~17%
酵 母:
価 格:1800ml 3150円(税込)
■ 寿司の古今を考える
『ますのすし』を食べながら、子どもからこんな質問がきた。
「生の魚を切り身にしてシャリに載せたものが寿司だが、『ますのすし』や『松前寿司』はシャリを押しつぶした押寿司。具を散らしたチラシ寿司など寿司といいながらいろいろあるけど、どう違うのか?」
というものであった。なるほど、寿司(鮨)という名称は同じでも、少しづつ製法の違いを指摘したものであろう。
私なりに調べてみました。
■ 寿司の起源は馴れ寿司
馴れ寿司をご存知でしょうか?。有名なのは、琵琶湖(滋賀県)周辺で食べらている鮒の馴れ寿司が有名です。
太古の昔、冷蔵庫が無かった時代、川や湖・海で獲れた魚を長期保存するために生まれた保存食が馴れ寿司です。魚の持つ、有用な動物性たんぱく質を長期保存する知恵は、我々祖先が編み出した食文化の歴史そのものです。
獲れた魚に塩と飯を混ぜ合わせ、樽などのような容器に入れます。丈上部に蓋をして、蓋の上に重石を置いて圧力をかけます。この状態で、短くて数カ月、もしくは何年もの間この状態を保ちます。
炊いた米が時間と伴に乳酸発酵をし始めます。飯から乳酸が生まれます。乳酸発酵がどんどん進み、その結果、飯状の粒粒は原型をとどめない形になりますが、樽の中は乳酸によりPHが低下します。つまり酸性状態となり、雑菌の繁殖が抑制されるか死滅されます。
これによって、長期保存が可能となるということになります。また、魚のタンパク質は、アミノ酸に分解されます。アミノ酸は旨味の成分ですので、馴れる程に旨味を増すということになります。
臭いは、ちょうど、八丈島などで造られるクサヤの干物に似ています。一種独特の臭いがありますので好き嫌いがはっきり分かれます。
一般的にタンパク質分解酵素を含んだ微生物にはこの系統の臭いがあります。腐敗しているか、発酵しているか、紙一重のような微妙は臭いです。
寒冷な地方では、蒸した飯に加えて、麹米を用いる馴れ寿司もあります。麹の持つ糖化酵素に作用により、発酵を促し、甘みを増す保存食を作り出します。石川県のカブラ寿司、秋田県のハタハタ寿司が麹米を入れた馴れ寿司です。
■ 押し寿司から江戸前へ
馴れ寿司が出来上がるまで、何カ月、何年という時間がかかります。米酢が作られるようになった室町時代後期に、蒸飯に酢を混ぜ、箱に入れてネタを上に置き、重石を置いて食べる押し寿司ができました。
私たちが一般的に想像する寿司は江戸前。シャリの上に新鮮な肴が乗ったものが登場するのは今から200年前の江戸・両国。諸説あるが、文化12(1829)年には文献に登場しています。長期保存食から、気の短い江戸っ子が育んだ直ぐに食べられる寿司まで、時代とともに変化しています。いずれの寿司も晴れの日のご馳走であったことは変わりがないようです。
さて、21世紀は回転寿司からどんな寿司が産まれるのでしょうか?。食の進化を見るもの楽しみの一つです。
Posted by たわらや at
20:25
│Comments(0)
2011年02月25日
仰清正公 №15 覇者決まる
-仰清正公- №14 覇者
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第15話「覇者決まる」
柴田勝家が北の庄へ戻る途中、越前の府中(武生)の城主、前田家に立ち寄る。本来、前田家は柴田勢に組するはずだったが、羽柴勢と一戦交えただけで府中の城に戻ったのは、羽柴にもつきあいがあったからでもある。だが、柴田は前だが友好的に迎えてくれていることは理解できた。二人は自らの武勇を恥合った。前田利家は48歳、柴田勝家は62歳であった。その夜柴田勝家は北の庄の城に戻った。残っていた重臣と防備の相談をする。だが、佐久間モリマサは、羽柴勢の追尾を受けながら戦っている。同じ夜秀吉は北の庄から9里ほど離れた今荘に、ついた。福島市松、加藤虎之助、片桐助作などを率いてである。
前田は羽柴軍に幸福したが、柴田は勝てぬことを知りながら羽柴軍と戦う決心をする。手勢は少ない。城下の住民と場内の女子供は避難させ、本丸に篭城する。
勝つ家とその武将たちは、九重の本丸とともに絶えたが、織田信長の妹おいちの方の娘、茶々ら三人は羽柴勢に助けられた。
加藤虎之助清正は、柴田の滅亡で、自分の主君 羽柴藤吉郎秀吉の天下が来たことを実感した。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第15話「覇者決まる」
柴田勝家が北の庄へ戻る途中、越前の府中(武生)の城主、前田家に立ち寄る。本来、前田家は柴田勢に組するはずだったが、羽柴勢と一戦交えただけで府中の城に戻ったのは、羽柴にもつきあいがあったからでもある。だが、柴田は前だが友好的に迎えてくれていることは理解できた。二人は自らの武勇を恥合った。前田利家は48歳、柴田勝家は62歳であった。その夜柴田勝家は北の庄の城に戻った。残っていた重臣と防備の相談をする。だが、佐久間モリマサは、羽柴勢の追尾を受けながら戦っている。同じ夜秀吉は北の庄から9里ほど離れた今荘に、ついた。福島市松、加藤虎之助、片桐助作などを率いてである。
前田は羽柴軍に幸福したが、柴田は勝てぬことを知りながら羽柴軍と戦う決心をする。手勢は少ない。城下の住民と場内の女子供は避難させ、本丸に篭城する。
勝つ家とその武将たちは、九重の本丸とともに絶えたが、織田信長の妹おいちの方の娘、茶々ら三人は羽柴勢に助けられた。
加藤虎之助清正は、柴田の滅亡で、自分の主君 羽柴藤吉郎秀吉の天下が来たことを実感した。(JS)
Posted by たわらや at
23:00
│Comments(0)
2011年02月25日
コラム・呑んどっと №20 江戸時代のデフォルトと商人 後編
-コラム・呑んどっと-№20
江戸時代のデフォルトと商人 後編
■ 固定した知行高
日本じゅうの禄高を、一つの基準に基づいて把握したのは豊臣秀吉の太閤検知であります。この検知により、日本じゅう各地の知行を知ることができました。
江戸に入り、戦国の世から平和な時代へ。寛永2(1625)年、三代将軍・家光は旗本屋敷地を知行高に応じて定めました。これにより、毎年の禄高が固定することになります。5000石の旗本は、子も孫も5000石の旗本なのです。1石は1両という相場は固定していました。
ところが、世が移り、受け取る石高は変わらないのです。生活には欠かせない薪や油、屋敷を修繕にやってくる修繕屋の手間賃、屋台の蕎麦の料金、舗で販売しているだんごや饅頭や寿司など、ありとあらゆるもの物価が徐々に高騰していくのです。収入が固定となっている武士は物価高騰分、生活は苦しくなります。また、知行の大小によって、それ相当の下男・下女を雇わなければならないという時代です。その費用も騰がるばかりでした。
武士は喰わねど高楊枝…という武士の面子が詠われたのはこのようなことからでしょう。不足を補うために札差から、来年受取る予定のお米を担保に金子(きんす)を用立てしたのです。その金利が年利18%。立ち行かなくのは目に見えていますね。
寛政元(1789)年、寛政の改革の一環として、老中・松平定信は棄捐令を出しました。5年前の1784年以前の旗本・御家人の借金をすべて棒引きにする法。これが施行されると札差は以後、申し合わせたように一切お金を用立てしなくなります。
これまで、大いに消費をしていた札差(商人)は一切の贅沢をやめたといいます。吉原に人がいなくなったといいます。
旗本・御家人は益々苦しくなりました。
幕末の天保14(1843)年にも同じように棄捐令が出されました。
少し話が飛躍するかもしれませんが、各藩でも同じような措置がなされ、商人は御上に金を貸しても返ってこないというのが定説になったと思います。
江戸時代、各街道の各宿で、酒造業を営んだ近江出身の商人たちもそうでした。時代が大きく変わり、明治になります。これらの商人は明治新政府にも冷たく、岩崎弥太郎のような新生の実業家が銀行を興し、殖産興業化政策の一翼を担うことになります。それなりの財を有していた酒造業の旦那衆は、銀行を経営するぐらいできたのでしょうが、そういったことはしていません。棄捐令がトラウマとなったことは事実のようです。
江戸時代のデフォルトと商人 後編
■ 固定した知行高
日本じゅうの禄高を、一つの基準に基づいて把握したのは豊臣秀吉の太閤検知であります。この検知により、日本じゅう各地の知行を知ることができました。
江戸に入り、戦国の世から平和な時代へ。寛永2(1625)年、三代将軍・家光は旗本屋敷地を知行高に応じて定めました。これにより、毎年の禄高が固定することになります。5000石の旗本は、子も孫も5000石の旗本なのです。1石は1両という相場は固定していました。
ところが、世が移り、受け取る石高は変わらないのです。生活には欠かせない薪や油、屋敷を修繕にやってくる修繕屋の手間賃、屋台の蕎麦の料金、舗で販売しているだんごや饅頭や寿司など、ありとあらゆるもの物価が徐々に高騰していくのです。収入が固定となっている武士は物価高騰分、生活は苦しくなります。また、知行の大小によって、それ相当の下男・下女を雇わなければならないという時代です。その費用も騰がるばかりでした。
武士は喰わねど高楊枝…という武士の面子が詠われたのはこのようなことからでしょう。不足を補うために札差から、来年受取る予定のお米を担保に金子(きんす)を用立てしたのです。その金利が年利18%。立ち行かなくのは目に見えていますね。
寛政元(1789)年、寛政の改革の一環として、老中・松平定信は棄捐令を出しました。5年前の1784年以前の旗本・御家人の借金をすべて棒引きにする法。これが施行されると札差は以後、申し合わせたように一切お金を用立てしなくなります。
これまで、大いに消費をしていた札差(商人)は一切の贅沢をやめたといいます。吉原に人がいなくなったといいます。
旗本・御家人は益々苦しくなりました。
幕末の天保14(1843)年にも同じように棄捐令が出されました。
少し話が飛躍するかもしれませんが、各藩でも同じような措置がなされ、商人は御上に金を貸しても返ってこないというのが定説になったと思います。
江戸時代、各街道の各宿で、酒造業を営んだ近江出身の商人たちもそうでした。時代が大きく変わり、明治になります。これらの商人は明治新政府にも冷たく、岩崎弥太郎のような新生の実業家が銀行を興し、殖産興業化政策の一翼を担うことになります。それなりの財を有していた酒造業の旦那衆は、銀行を経営するぐらいできたのでしょうが、そういったことはしていません。棄捐令がトラウマとなったことは事実のようです。
Posted by たわらや at
06:00
│Comments(0)
2011年02月24日
仰清正公 №14 覇者
-仰清正公- №14 覇者
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第14話「覇者」
織田家の跡目については、関係者の誰もが不満を持っていた。信長が生きていて、後の世を「こうする」と漠然とでもいいから方向を示しておけば、それにはだれも文句はいえなかっただろうが。だが、突然の死に見舞われたのだから、「この跡目はオレが」と思う者が多くいてもいたしかたがない。中でも、柴田勝家は実力では一番だと思っていた。信長の妹、お市の方を妻にしていることもある。
だが、本能寺の変が起きたとき、北陸で上杉勢と対峙していた。明智光秀を討つこともできず羽柴秀吉に先行されてしまった。
清洲城の談合も、秀吉にサラリと処理されてしまい、それでも織田家の所領の配分で、秀吉の城、長浜を手に入れた。京へ上る足がかりとしてもあったが、秀吉へのいやがらせもあったに違いない。
これまでの織田家に対する貢献と実績、それに現状からみても 柴田勝家と羽柴秀吉はぶつからざるを得ない状況だった。
柴田勝家は、上杉勢との争いを中止して、北の庄(福井)から南下しようとしたが、天正10(1582)年の冬は雪が深く、柴田勝家は動き出せない。秀吉は京都を出発し、長浜の城を取り返した。城にいた勝家の養子・勝豊は、自ら秀吉の軍に入り、味方になった。
秀吉は勝家の南下に備え、北国街道を押さえる拠点として天神山に砦を築かせていた。
天神山の砦は、加藤虎之助が築いたものである。丸太を大地に打ち込み、柵を回し、雪がなくなっても砦として十分に役立つものだった。食料も十分に備えてある。虎之助はこの砦を十日で作ったが、秀吉の命を受けて視察に来た同僚福島市松正則は砦の頑丈さに驚いた。雪が解ければこの辺が柴田、羽柴両軍の衝突点になるだろうとは武将たちはみな思っていた。
虎之助と福島市松(後の正則)は同年で22歳である。虎之助は13歳のとき、母の縁で長浜城主の木下藤吉郎に仕えた。福島市松はそれより早く藤吉郎の小姓として使えているのでともに一軍を預かっているが知行・市松は五百石、虎之助は四百五十石である。
軍楽は杉野弥次右衛門、武術は塚原卜伝の縁者塚原斉次郎に学んだ。
まだ雪の深い中、柴田勝家は猛将といわれる佐久間玄馬モリマサに手勢を預け、ひそかに南下を図らせた。
佐久間盛政は三千の兵を率いて南下してくるが虎之助が固める春日山の砦は迂回した。そして陣を構える。柴田勝家は三万の兵を率いて南下を始める。これに対して羽柴秀吉の勢力の守備は完全とはいえない。その上、秀吉本人は美濃の国にいた。秀吉は勝家が動いたと聞くと、夜を徹して長浜にもどってくる。しかしそのときは羽柴軍の守備網のいくつかは柴田勢に破られていた。
急遽、帰った秀吉の指揮のもと、羽柴軍は戦列を固める。春日山の砦にいた虎之助も急遽秀吉の下に参じる。
この羽柴勢と柴田勢の対峙に、柴田に組することになっていた前田勝家親子が動かなかったため、柴田勢は撤退することになる。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第14話「覇者」
織田家の跡目については、関係者の誰もが不満を持っていた。信長が生きていて、後の世を「こうする」と漠然とでもいいから方向を示しておけば、それにはだれも文句はいえなかっただろうが。だが、突然の死に見舞われたのだから、「この跡目はオレが」と思う者が多くいてもいたしかたがない。中でも、柴田勝家は実力では一番だと思っていた。信長の妹、お市の方を妻にしていることもある。
だが、本能寺の変が起きたとき、北陸で上杉勢と対峙していた。明智光秀を討つこともできず羽柴秀吉に先行されてしまった。
清洲城の談合も、秀吉にサラリと処理されてしまい、それでも織田家の所領の配分で、秀吉の城、長浜を手に入れた。京へ上る足がかりとしてもあったが、秀吉へのいやがらせもあったに違いない。
これまでの織田家に対する貢献と実績、それに現状からみても 柴田勝家と羽柴秀吉はぶつからざるを得ない状況だった。
柴田勝家は、上杉勢との争いを中止して、北の庄(福井)から南下しようとしたが、天正10(1582)年の冬は雪が深く、柴田勝家は動き出せない。秀吉は京都を出発し、長浜の城を取り返した。城にいた勝家の養子・勝豊は、自ら秀吉の軍に入り、味方になった。
秀吉は勝家の南下に備え、北国街道を押さえる拠点として天神山に砦を築かせていた。
天神山の砦は、加藤虎之助が築いたものである。丸太を大地に打ち込み、柵を回し、雪がなくなっても砦として十分に役立つものだった。食料も十分に備えてある。虎之助はこの砦を十日で作ったが、秀吉の命を受けて視察に来た同僚福島市松正則は砦の頑丈さに驚いた。雪が解ければこの辺が柴田、羽柴両軍の衝突点になるだろうとは武将たちはみな思っていた。
虎之助と福島市松(後の正則)は同年で22歳である。虎之助は13歳のとき、母の縁で長浜城主の木下藤吉郎に仕えた。福島市松はそれより早く藤吉郎の小姓として使えているのでともに一軍を預かっているが知行・市松は五百石、虎之助は四百五十石である。
軍楽は杉野弥次右衛門、武術は塚原卜伝の縁者塚原斉次郎に学んだ。
まだ雪の深い中、柴田勝家は猛将といわれる佐久間玄馬モリマサに手勢を預け、ひそかに南下を図らせた。
佐久間盛政は三千の兵を率いて南下してくるが虎之助が固める春日山の砦は迂回した。そして陣を構える。柴田勝家は三万の兵を率いて南下を始める。これに対して羽柴秀吉の勢力の守備は完全とはいえない。その上、秀吉本人は美濃の国にいた。秀吉は勝家が動いたと聞くと、夜を徹して長浜にもどってくる。しかしそのときは羽柴軍の守備網のいくつかは柴田勢に破られていた。
急遽、帰った秀吉の指揮のもと、羽柴軍は戦列を固める。春日山の砦にいた虎之助も急遽秀吉の下に参じる。
この羽柴勢と柴田勢の対峙に、柴田に組することになっていた前田勝家親子が動かなかったため、柴田勢は撤退することになる。(JS)
Posted by たわらや at
18:00
│Comments(0)
2011年02月24日
コラム・呑んどっと №19 江戸時代のデフォルトと商人 前編
-コラム・呑んどっと-№19
江戸時代のデフォルトと商人 前編
■ デフォルト
私は政治家でも、経済学者でもない。酒屋のいち主であります。政治にも、経済にも明るい方ではありません。酒屋のオヤジの視点で考察します。
今から2年前、2009(平成21)年に自民党から民主党へ政権が交代しました。そして、現在の国会で審議されている平成23年度予算案は、民主党の責任で立案されたものと理解しています。税収が伸び悩み、不足した財源は国債で補うというもの。これにより国債の発行高は1000兆円に迫ることになります。1000兆円、途方もない金額です。日本の人口1億2千万人で割り算すると、833万円になります。「おぎゃ~」と産まれて、833万円の借金があるということになります。
また、100万円の札束の厚さはおよそ1㎝。1000兆の札束の長さは、なんと10000㎞。シベリア鉄道が9300㎞ですので、それよりも遥かに長いのです。びっくりしますね。
国債の引き受け手の95%は国民ということで、問題はないというのですが、果たしてそうなのでしょうか。
このままでは、償還できなくなる事態になるのも時間の問題のように思います。最近、新聞やテレビでの経済学の論客が口にするのが「デフォルト」という単語です。
■ 江戸時代のデフォルト
デフォルト、いわゆる徳政令であります。借金・利息の棒引きです。
江戸時代にもこのような事態が起こりました。江戸幕府ができて間もない徳川家光の時代にはすでに旗本・御家人の貧乏が問題視されるようになったといいます。倹約に励むにも限度があります。不足したお金を札差から借りることになります。札差は年利18%の利息をとり、財を蓄えることになります。
10代将軍・徳川家治の側近・田沼意次の商重主義を是正するべく、11代将軍・徳川家斉の筆頭老中として白羽の矢がたったのが白河藩主・松平定信公。8代吉宗の孫にあたる定信公は、天明3(1783)年の天明の大飢饉の時に、素早く他藩から米を買い集め藩内の餓死者を出すことがなかったといいます。東北地方の諸藩にはかなりの餓死者が出たことと比較するとまさに救世主。その手腕が買われての抜擢となりました。
世にいう、寛政の改革に着手するのです。その一つが棄捐令(きえんれい)です。旗本・御家人の過去5年以上前の借金を棒引きにするという法律。大江戸の札差88軒の棒引きの総額はなんと119万両に上ったと言われています。
棄捐令が出た直後は「さすがは名君吉宗公の孫」として囃されたのですが、その後、思わぬ問題が生じてくるのでした。(続く)
江戸時代のデフォルトと商人 前編
■ デフォルト
私は政治家でも、経済学者でもない。酒屋のいち主であります。政治にも、経済にも明るい方ではありません。酒屋のオヤジの視点で考察します。
今から2年前、2009(平成21)年に自民党から民主党へ政権が交代しました。そして、現在の国会で審議されている平成23年度予算案は、民主党の責任で立案されたものと理解しています。税収が伸び悩み、不足した財源は国債で補うというもの。これにより国債の発行高は1000兆円に迫ることになります。1000兆円、途方もない金額です。日本の人口1億2千万人で割り算すると、833万円になります。「おぎゃ~」と産まれて、833万円の借金があるということになります。
また、100万円の札束の厚さはおよそ1㎝。1000兆の札束の長さは、なんと10000㎞。シベリア鉄道が9300㎞ですので、それよりも遥かに長いのです。びっくりしますね。
国債の引き受け手の95%は国民ということで、問題はないというのですが、果たしてそうなのでしょうか。
このままでは、償還できなくなる事態になるのも時間の問題のように思います。最近、新聞やテレビでの経済学の論客が口にするのが「デフォルト」という単語です。
■ 江戸時代のデフォルト
デフォルト、いわゆる徳政令であります。借金・利息の棒引きです。
江戸時代にもこのような事態が起こりました。江戸幕府ができて間もない徳川家光の時代にはすでに旗本・御家人の貧乏が問題視されるようになったといいます。倹約に励むにも限度があります。不足したお金を札差から借りることになります。札差は年利18%の利息をとり、財を蓄えることになります。
10代将軍・徳川家治の側近・田沼意次の商重主義を是正するべく、11代将軍・徳川家斉の筆頭老中として白羽の矢がたったのが白河藩主・松平定信公。8代吉宗の孫にあたる定信公は、天明3(1783)年の天明の大飢饉の時に、素早く他藩から米を買い集め藩内の餓死者を出すことがなかったといいます。東北地方の諸藩にはかなりの餓死者が出たことと比較するとまさに救世主。その手腕が買われての抜擢となりました。
世にいう、寛政の改革に着手するのです。その一つが棄捐令(きえんれい)です。旗本・御家人の過去5年以上前の借金を棒引きにするという法律。大江戸の札差88軒の棒引きの総額はなんと119万両に上ったと言われています。
棄捐令が出た直後は「さすがは名君吉宗公の孫」として囃されたのですが、その後、思わぬ問題が生じてくるのでした。(続く)
Posted by たわらや at
07:00
│Comments(0)
2011年02月23日
仰清正公 №12 跡目争い
-仰清正公- №13 跡目争い
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第13話「跡目争い」
織田信長が死んだ跡の跡目は、信長の次男信勝と三男信孝のいずれかになりそうだが、この二人は仲が悪かった。本能寺の変の後、信勝は安土城に入ったが、火を出して城を消失する。信孝は羽柴秀吉について山崎合戦に加わったので後を継ぐ有利さがあった。
跡目を決めるその評定は、天承十年六月二十七日、清洲城で開かれた。
信長の武将で上席は柴田勝家、羽柴秀吉、丹羽長秀、池田恒興らである。信勝、信孝も清洲には来ていたが評定には出なかった。
堀秀政も出席していたが、徳川家康は浜松で成り行きを見守っていた。加藤虎之助も秀吉に従って清洲城に入った。会議には出られず、福島市松とともに控え室にいた。
評定は秀吉が仕切っていた。秀吉が押したのは二条御所で明智勢に攻められ自殺した信忠(のぶただ)の三歳になる三法師であった。その後見に信勝と信孝を立て、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、それに自身秀吉と織田家の重臣が守るというものだった。
三法師には近江の国坂田郡二万五千石を台所費用とし、堀秀政代官となる。
信勝には北伊勢に尾張の国を、信孝には美濃の国を与えた。
織田兄弟、重臣らにとって収まる話ではないが受けざるを得なかった。
新発田か費えは越前の国に加え、近江の長浜を求めた。京に近いからである。羽柴秀吉は播磨の国に山城と河内に明智の旧領、丹波を得た。
この話がまとまり、虎之助は秀吉に京都に潜入する命を受ける。秀吉に先んじて、京の人心をつかめという命令だ。詳しくは蜂須賀正勝に聞けという。正勝は戦いぶりもさることながら、人心を把握する特技があった。
虎之助は、話し合いの進め方を学び、さらにこれから進んでいく地域の人心がどうなのかを調べる実務を任されたのです。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第13話「跡目争い」
織田信長が死んだ跡の跡目は、信長の次男信勝と三男信孝のいずれかになりそうだが、この二人は仲が悪かった。本能寺の変の後、信勝は安土城に入ったが、火を出して城を消失する。信孝は羽柴秀吉について山崎合戦に加わったので後を継ぐ有利さがあった。
跡目を決めるその評定は、天承十年六月二十七日、清洲城で開かれた。
信長の武将で上席は柴田勝家、羽柴秀吉、丹羽長秀、池田恒興らである。信勝、信孝も清洲には来ていたが評定には出なかった。
堀秀政も出席していたが、徳川家康は浜松で成り行きを見守っていた。加藤虎之助も秀吉に従って清洲城に入った。会議には出られず、福島市松とともに控え室にいた。
評定は秀吉が仕切っていた。秀吉が押したのは二条御所で明智勢に攻められ自殺した信忠(のぶただ)の三歳になる三法師であった。その後見に信勝と信孝を立て、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、それに自身秀吉と織田家の重臣が守るというものだった。
三法師には近江の国坂田郡二万五千石を台所費用とし、堀秀政代官となる。
信勝には北伊勢に尾張の国を、信孝には美濃の国を与えた。
織田兄弟、重臣らにとって収まる話ではないが受けざるを得なかった。
新発田か費えは越前の国に加え、近江の長浜を求めた。京に近いからである。羽柴秀吉は播磨の国に山城と河内に明智の旧領、丹波を得た。
この話がまとまり、虎之助は秀吉に京都に潜入する命を受ける。秀吉に先んじて、京の人心をつかめという命令だ。詳しくは蜂須賀正勝に聞けという。正勝は戦いぶりもさることながら、人心を把握する特技があった。
虎之助は、話し合いの進め方を学び、さらにこれから進んでいく地域の人心がどうなのかを調べる実務を任されたのです。(JS)
Posted by たわらや at
18:00
│Comments(0)
2011年02月23日
知っているようで知らない酒の話№130いつ生まれた吟醸の言葉
知っているようで知らない酒の話 №130
いつ生まれた「吟醸」という言葉
■ いつ生まれた「吟醸」という言葉
吟醸酒が市民権を得て久しい。製造の面において、「吟醸」とは精米歩合60%以下まで磨き、アルコール添加量については本醸造に準じた酒です。では、吟醸とはいつごろ、誰が使い始めたのでしょうか。
品評会に醸された門外不出の存在であった吟醸酒を世に広めたのは私の恩師である篠田次郎先生です。
前醸造試験所所長・秋山裕一先生の著書「吟醸酒のはなし」の冒頭の文章にはこう書いてあります。
今日、吟醸酒が静かな人気をよび、多くの酒通の方々から注目されていることは、まことに喜びにたえない。これだけ注目されていながら、成書としてまとまったものでは篠田次郎氏の『吟醸酒』があるだけで、技術的な、製造法や成分についての本が見当たらない。その理由として、筆者は、吟醸酒づくりは今日でもまだ試行錯誤の段階なのかと考えたり、一方では、「日本酒は芸術作品である」といわれるから、普通の酒づくりの醸造論はありえても吟醸論は奥が深く、名人のみが到達しうる聖域であってとても筆者の立ち入る筋のものではないということか、と思ったりするのである。
と書いてあります。なるほど。
篠田次郎先生によると、明治時代の酒のレッテルに「謹製」内容の言葉として「吟醸」使われたといいます。
大正6年、広島の酒史を書いた桐原花村著『天下の芳醇』の中に「上酒吟醸の秘訣は…」とあり、「吟味して醸す」といった言葉のようです。

(写真は福井県・加藤吉平商店より 昭和初期の蔵人の前掛けに「吟醸」と書いてある 詳細は下記に)
全国清酒品評会が明治40年より2年に一度、開催されるようになりました。当時、品評会入選の優良酒は「醇良酒」といっていたようで、業界雑誌「日本醸造協会誌」上んでの「吟醸」については、大正12年、江田鎌次郎先生の品評会出品酒を評した論説「吟醸に対する希望」の中で出てくるが、品評会では「香気芳列、旨味タップリ、且つハネのある濃醇酒を選ぶべし」とし、いらずらに米を高度に精米し、低温発酵の吟醸を行い、アルコール分が低い、エキス分の多い口当たりのよい酒を造ろうとしているが、これは推賞できないと論じており、「吟醸酒」との表現は使っていません。ただ、現実にはこういう飲みやすい型の酒が次第に迎えられるようになっていくのであります。(つづく)
追伸:さて、江田鎌次郎先生と真っ向から美酒論を展開する鹿又先生が「吟醸と経済」(昭和2年)の論文の中で、吟醸酒についての定義を定めるという話は、次回に…江田VS鹿又論争は戦前の日本酒史のひのき舞台ですね。
余談だが・・・(長文です)
写真の説明:
写真:「昭和天皇の御大典の儀の地方選酒になり、加藤吉平商店の蔵の前で、当時の蔵役との記念写真。」。この写真が何を物語っているか、たいへんに興味深いことがある。この写真は昭和初期のこと。この前掛けに「吟醸」という文字がある。日本で初めて吟醸という言葉が登場した時の写真である(と思う)。
現在では誰もが吟醸酒という言葉に馴染みがあるが、高度に精米して醸した日本酒=吟醸酒が誕生したのがこの時代である。それまで、お米を磨く手段としては水車精米か、人力による足踏み精米であった。
水車精米にしろ、足踏み精米にしろ精米歩合90%程度しか磨くことができなかった。現在の基準では精米歩合60%以下が吟醸酒で、50%以下が大吟醸酒であるが、この精米が可能にしたのが、広島の佐竹利市氏が発明した「佐竹式竪型精米機」の誕生だ。動力に電気を使い、現在の精米機の原点といえる機械を完成させた。高度精白した原料米で低温でじっくりと醗酵させるとこの世のものとは思えぬ芳しい香気が漂う美酒が生まれた。これを吟醸酒と評したのである。その当時吟醸酒を加藤吉平商店は発売していたことを物語っている。
残念なことに、高度に精米する吟醸酒は、暗い時代を迎えてしまう。米が国の統制下におかれ、贅沢に米を使う吟醸酒は醸造が認められなくなった。
もともと吟醸酒は明治40年から隔年に開催された全国新酒品評会の出品酒として各地の銘醸蔵が腕を競うため醸した。昭和13年を最後に戦後まで開催が中止された。
戦後、日本酒を醸造することはできるようになったが、吟醸酒の復活はそれよりもっともっと後のことになる。昭和44年に「梵」(加藤吉平商店)で戦後初の吟醸酒発売になるが、みんなが吟醸酒を認知するのは昭和50年代、60年代。ようやく吟醸酒の戦後がやってきたのだ。吟醸酒にとっては長い長い戦争だったように思う。
いつ生まれた「吟醸」という言葉
■ いつ生まれた「吟醸」という言葉
吟醸酒が市民権を得て久しい。製造の面において、「吟醸」とは精米歩合60%以下まで磨き、アルコール添加量については本醸造に準じた酒です。では、吟醸とはいつごろ、誰が使い始めたのでしょうか。
品評会に醸された門外不出の存在であった吟醸酒を世に広めたのは私の恩師である篠田次郎先生です。
前醸造試験所所長・秋山裕一先生の著書「吟醸酒のはなし」の冒頭の文章にはこう書いてあります。
今日、吟醸酒が静かな人気をよび、多くの酒通の方々から注目されていることは、まことに喜びにたえない。これだけ注目されていながら、成書としてまとまったものでは篠田次郎氏の『吟醸酒』があるだけで、技術的な、製造法や成分についての本が見当たらない。その理由として、筆者は、吟醸酒づくりは今日でもまだ試行錯誤の段階なのかと考えたり、一方では、「日本酒は芸術作品である」といわれるから、普通の酒づくりの醸造論はありえても吟醸論は奥が深く、名人のみが到達しうる聖域であってとても筆者の立ち入る筋のものではないということか、と思ったりするのである。
と書いてあります。なるほど。
篠田次郎先生によると、明治時代の酒のレッテルに「謹製」内容の言葉として「吟醸」使われたといいます。
大正6年、広島の酒史を書いた桐原花村著『天下の芳醇』の中に「上酒吟醸の秘訣は…」とあり、「吟味して醸す」といった言葉のようです。

(写真は福井県・加藤吉平商店より 昭和初期の蔵人の前掛けに「吟醸」と書いてある 詳細は下記に)
全国清酒品評会が明治40年より2年に一度、開催されるようになりました。当時、品評会入選の優良酒は「醇良酒」といっていたようで、業界雑誌「日本醸造協会誌」上んでの「吟醸」については、大正12年、江田鎌次郎先生の品評会出品酒を評した論説「吟醸に対する希望」の中で出てくるが、品評会では「香気芳列、旨味タップリ、且つハネのある濃醇酒を選ぶべし」とし、いらずらに米を高度に精米し、低温発酵の吟醸を行い、アルコール分が低い、エキス分の多い口当たりのよい酒を造ろうとしているが、これは推賞できないと論じており、「吟醸酒」との表現は使っていません。ただ、現実にはこういう飲みやすい型の酒が次第に迎えられるようになっていくのであります。(つづく)
追伸:さて、江田鎌次郎先生と真っ向から美酒論を展開する鹿又先生が「吟醸と経済」(昭和2年)の論文の中で、吟醸酒についての定義を定めるという話は、次回に…江田VS鹿又論争は戦前の日本酒史のひのき舞台ですね。
余談だが・・・(長文です)
写真の説明:
写真:「昭和天皇の御大典の儀の地方選酒になり、加藤吉平商店の蔵の前で、当時の蔵役との記念写真。」。この写真が何を物語っているか、たいへんに興味深いことがある。この写真は昭和初期のこと。この前掛けに「吟醸」という文字がある。日本で初めて吟醸という言葉が登場した時の写真である(と思う)。
現在では誰もが吟醸酒という言葉に馴染みがあるが、高度に精米して醸した日本酒=吟醸酒が誕生したのがこの時代である。それまで、お米を磨く手段としては水車精米か、人力による足踏み精米であった。
水車精米にしろ、足踏み精米にしろ精米歩合90%程度しか磨くことができなかった。現在の基準では精米歩合60%以下が吟醸酒で、50%以下が大吟醸酒であるが、この精米が可能にしたのが、広島の佐竹利市氏が発明した「佐竹式竪型精米機」の誕生だ。動力に電気を使い、現在の精米機の原点といえる機械を完成させた。高度精白した原料米で低温でじっくりと醗酵させるとこの世のものとは思えぬ芳しい香気が漂う美酒が生まれた。これを吟醸酒と評したのである。その当時吟醸酒を加藤吉平商店は発売していたことを物語っている。
残念なことに、高度に精米する吟醸酒は、暗い時代を迎えてしまう。米が国の統制下におかれ、贅沢に米を使う吟醸酒は醸造が認められなくなった。
もともと吟醸酒は明治40年から隔年に開催された全国新酒品評会の出品酒として各地の銘醸蔵が腕を競うため醸した。昭和13年を最後に戦後まで開催が中止された。
戦後、日本酒を醸造することはできるようになったが、吟醸酒の復活はそれよりもっともっと後のことになる。昭和44年に「梵」(加藤吉平商店)で戦後初の吟醸酒発売になるが、みんなが吟醸酒を認知するのは昭和50年代、60年代。ようやく吟醸酒の戦後がやってきたのだ。吟醸酒にとっては長い長い戦争だったように思う。
Posted by たわらや at
12:00
│Comments(0)
2011年02月22日
仰清正公 №12 安土城焼け落ちる
-仰清正公- №12 安土城焼け落ちる
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第12話「安土城焼け落ちる」
明智光秀は、安土城に入ったが、ここから落ちる前に城に火を放った。信長が贅を凝らして立てた安土の城は炎上してしまえば無残な残骸である。
その安土へ織田信勝の軍が入った。信勝は秀吉より先に安土に入りたかった。秀吉はするがままにさせた。
秀吉は信勝と信孝の陣屋を離れたところに設けさせ、加藤虎之助に長浜行きを命じた。秀吉の中国遠征中、居城の長浜には帰っていない。その長浜も明智勢に抑えられたという。しかし偲びの者の報告では羽柴一族や家来の家族は無事だという。虎之助は、武者三十騎と足軽七十人を率いて長浜に向かった。
一時長浜を押さえた京極勢はすでにこの地から離れている。
本能寺の変を聞いた長浜城の留守居役岩佐甚助は、篭城はせずに、秀吉や家臣の家族を白から逃がした。その後へ京極勢がはいったが、光秀の山崎の敗戦を聞いて、場内を荒らし、これも城を去っていた。見方も敵もいない長浜の城は、灯さえなかった。虎之助は、城の狭間から遠くの村にも見えるように火を点じた。長浜城が健在であることを領民に示すための知恵でした。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第12話「安土城焼け落ちる」
明智光秀は、安土城に入ったが、ここから落ちる前に城に火を放った。信長が贅を凝らして立てた安土の城は炎上してしまえば無残な残骸である。
その安土へ織田信勝の軍が入った。信勝は秀吉より先に安土に入りたかった。秀吉はするがままにさせた。
秀吉は信勝と信孝の陣屋を離れたところに設けさせ、加藤虎之助に長浜行きを命じた。秀吉の中国遠征中、居城の長浜には帰っていない。その長浜も明智勢に抑えられたという。しかし偲びの者の報告では羽柴一族や家来の家族は無事だという。虎之助は、武者三十騎と足軽七十人を率いて長浜に向かった。
一時長浜を押さえた京極勢はすでにこの地から離れている。
本能寺の変を聞いた長浜城の留守居役岩佐甚助は、篭城はせずに、秀吉や家臣の家族を白から逃がした。その後へ京極勢がはいったが、光秀の山崎の敗戦を聞いて、場内を荒らし、これも城を去っていた。見方も敵もいない長浜の城は、灯さえなかった。虎之助は、城の狭間から遠くの村にも見えるように火を点じた。長浜城が健在であることを領民に示すための知恵でした。(JS)
Posted by たわらや at
12:00
│Comments(0)
2011年02月22日
分かりやすい清酒醸造学 №13 酒母の主流派 速醸酒母
-分かりやすい清酒醸造学-№13
酒母の主流派 速醸酒母について考察する
◆ 酒母の主流派・速醸酒母
現在に醸される日本酒の大半が、速醸酒母で醸されています。この酒母で仕込んだ酒は、ラベルに「速醸仕込み」とか標記することはありません。逆に「山廃仕込み」と標記してあれば「山廃酒母」であるし、「生酛仕込み」と標記してあれば「生酛酒母」です。
速醸酒母は比較的室温に近い温度で仕込みます。標準的には20℃前後です。この温度は、日本酒の本仕込みが10℃~14℃の品温で発酵させることと比較すれば、ずいぶん高い温度と言えます。
20℃前後で仕込むため、蒸米の溶解糖化が早くなります。温度が高いと、麹菌が作り出す糖化酵素(アミラーゼ)が活発に働きます。温度が低い時より、温度が高い方が活発に働きます。そうすると、米のデンプン質がどんどん糖分に変わり、米粒がどんどん溶けていきます。
杜氏に言わせれば「速醸酒母は早湧きしない」といいます。早湧きとは、米の溶解糖化によって内容成分が充分に整わないうちに発酵が始まることをいいます。このような状態になると、酵母が充分に増殖する前に、アルコール分をどんどん生産してくれる状況です。アルコール分が多くなると、酵母の増殖が抑制されます。そうすれば、単位容積の中に
必要とする酵母がない状態となります。このような酒母を造って、次の本仕込みに使うと、十分な酵母が無いために、アルコール発酵が進まず、最悪の場合、腐造につながる事態になります。ですので、酒母を造る時に杜氏は、早湧きしないように努めているのです。
◆ なぜ速醸が主流なのか
山廃仕込みや生酛仕込みについては、後日詳細に述べることにします。
なぜ、速醸が主流になったかというと、「簡便」に健全な酒母ができあがるからです。
比較すると
1)酒母ができあがるまでの日数が短い
2)作業が簡便であり、使用する道具が少なく、経験をあまり必要としない
3)労力も燃料も少なくて済む
が列挙できます。ですので主流になりました。
このような時代であるから、逆に山廃仕込みや生酛仕込みをして、独自の香味を追求して、特徴にある酒を世に出すという蔵もあります。
酒母の主流派 速醸酒母について考察する
◆ 酒母の主流派・速醸酒母
現在に醸される日本酒の大半が、速醸酒母で醸されています。この酒母で仕込んだ酒は、ラベルに「速醸仕込み」とか標記することはありません。逆に「山廃仕込み」と標記してあれば「山廃酒母」であるし、「生酛仕込み」と標記してあれば「生酛酒母」です。
速醸酒母は比較的室温に近い温度で仕込みます。標準的には20℃前後です。この温度は、日本酒の本仕込みが10℃~14℃の品温で発酵させることと比較すれば、ずいぶん高い温度と言えます。
20℃前後で仕込むため、蒸米の溶解糖化が早くなります。温度が高いと、麹菌が作り出す糖化酵素(アミラーゼ)が活発に働きます。温度が低い時より、温度が高い方が活発に働きます。そうすると、米のデンプン質がどんどん糖分に変わり、米粒がどんどん溶けていきます。
杜氏に言わせれば「速醸酒母は早湧きしない」といいます。早湧きとは、米の溶解糖化によって内容成分が充分に整わないうちに発酵が始まることをいいます。このような状態になると、酵母が充分に増殖する前に、アルコール分をどんどん生産してくれる状況です。アルコール分が多くなると、酵母の増殖が抑制されます。そうすれば、単位容積の中に
必要とする酵母がない状態となります。このような酒母を造って、次の本仕込みに使うと、十分な酵母が無いために、アルコール発酵が進まず、最悪の場合、腐造につながる事態になります。ですので、酒母を造る時に杜氏は、早湧きしないように努めているのです。
◆ なぜ速醸が主流なのか
山廃仕込みや生酛仕込みについては、後日詳細に述べることにします。
なぜ、速醸が主流になったかというと、「簡便」に健全な酒母ができあがるからです。
比較すると
1)酒母ができあがるまでの日数が短い
2)作業が簡便であり、使用する道具が少なく、経験をあまり必要としない
3)労力も燃料も少なくて済む
が列挙できます。ですので主流になりました。
このような時代であるから、逆に山廃仕込みや生酛仕込みをして、独自の香味を追求して、特徴にある酒を世に出すという蔵もあります。
タグ :分かりやすい清酒醸造学速醸酒母
Posted by たわらや at
07:00
│Comments(0)
2011年02月22日
2月22日 おはようございます。
平成23年02月22日(火)
旧暦:1月20日
たわらや酒店 日刊かわらばん アップします。
おはようございます。
今日の熊本(菊陽町)の天気は晴。
最低気温3℃。
日中は14℃まで上がる予報が出ています。

お散歩の時に水仙が咲いていました。
庭の持ち主から数輪頂きました。
保育園に持って行きました。
(2月21日 朝 写真は次男と水仙)
本日のかわら版をアップします。
午前07時00分:分かりやすい清酒醸造学№13 酒母の主流は速醸酒母
正午:仰清正公 №12 安土城焼け落ちる

木蓮の蕾も膨らみはじめました
旧暦:1月20日
たわらや酒店 日刊かわらばん アップします。
おはようございます。
今日の熊本(菊陽町)の天気は晴。
最低気温3℃。
日中は14℃まで上がる予報が出ています。

お散歩の時に水仙が咲いていました。
庭の持ち主から数輪頂きました。
保育園に持って行きました。
(2月21日 朝 写真は次男と水仙)
本日のかわら版をアップします。
午前07時00分:分かりやすい清酒醸造学№13 酒母の主流は速醸酒母
正午:仰清正公 №12 安土城焼け落ちる

木蓮の蕾も膨らみはじめました
Posted by たわらや at
06:32
│Comments(0)
2011年02月21日
栄光冨士で神力を仕込む №4
栄光冨士で神力を仕込む №4
-加藤清正公生誕450年 没後400年 九州新幹線全線開業 記念企画-
■ 栄光冨士・神力の酒母づくり
2月3日から神力の酒母づくりがスタートしました。日刊たわらやかわら版でも、酒母について、詳しく述べていますので、詳細は割愛をいたします。

(↑栄光冨士 神力 酒母の表面の様子)

■ 栄光冨士・神力の麹米づくり
酒母づくりと並行して、2月7日より、本仕込み用の麹米づくりがスタートしました。
初添え用麹米30㎏は、2月8日に蒸されました。
蒸した麹米は、35℃付近まで、冷ましてやり、麹室に入れます。そし麹菌をかけます。それから48時間、麹室の中で、米粒の麹菌を繁殖させて麹米をつくります。

2月10日に麹室から出され、2月11日の本仕込み・初添え用の麹米として使われるのです。
同じようなスケジュールで、仲添え用麹米40㎏は2月10日に蒸し、留添え用麹米50㎏は2月11日に蒸され、それぞれ、48時間かけて麹米が造られました。(つづく)
写真提供:冨士酒造㈱ より
写真撮影は女性蔵人・池田美和氏
-加藤清正公生誕450年 没後400年 九州新幹線全線開業 記念企画-
■ 栄光冨士・神力の酒母づくり
2月3日から神力の酒母づくりがスタートしました。日刊たわらやかわら版でも、酒母について、詳しく述べていますので、詳細は割愛をいたします。

(↑栄光冨士 神力 酒母の表面の様子)

■ 栄光冨士・神力の麹米づくり
酒母づくりと並行して、2月7日より、本仕込み用の麹米づくりがスタートしました。
初添え用麹米30㎏は、2月8日に蒸されました。
蒸した麹米は、35℃付近まで、冷ましてやり、麹室に入れます。そし麹菌をかけます。それから48時間、麹室の中で、米粒の麹菌を繁殖させて麹米をつくります。

2月10日に麹室から出され、2月11日の本仕込み・初添え用の麹米として使われるのです。
同じようなスケジュールで、仲添え用麹米40㎏は2月10日に蒸し、留添え用麹米50㎏は2月11日に蒸され、それぞれ、48時間かけて麹米が造られました。(つづく)
写真提供:冨士酒造㈱ より
写真撮影は女性蔵人・池田美和氏
Posted by たわらや at
15:00
│Comments(0)
2011年02月21日
仰清正公 №11 本能寺の変
-仰清正公- №11 本能寺の変
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第11話「本能寺の変」
水に漬かった高松城、城主・清水宗治の切腹した前日の天正11(1582)年6月3日、日本史最大ともいえるクーデター、本能寺の変が起きた。織田信長が中国遠征をはかり、その先兵たるべき明智光秀が警戒を解いて京都の本能寺に宿泊した信長を奇襲したのである。
羽柴秀吉は早飛脚の報でそれを知ったが顔色にも表さず、宗治の切腹を見届け、かつ毛利勢と和議を固めた。加藤虎之助は武将たちの末席からそれを見ていた。
秀吉は姫路の陣を発って東へ向かう。全軍を五部にわけ、それぞれが緊密に連絡を取る。大阪に向かい、そこで信長の遺子、三七郎信孝(さんしちろうのぶたか)を立て、光秀と決戦するつもりだ。これで大義名分は立つ。だが戦場がどこになるか、秀吉も光秀すらもわからない。
このとき光秀は55歳、秀吉は47歳であった。
虎之助は秀吉から直接命を受け、淀川沿いの山崎の地を望める天王山に足軽三十人を率いて備えた。
家来利吉と才八に馬一等。総員33名で最前線に臨むのである。
そして山崎の里で光秀軍の物見と遭遇し、相手の将の首をはねた。夜が明けると、秀吉軍が山崎に入ってきた。
6月13日、虎之助は早朝の物見の合戦で足軽二人を失い四人を負傷させているのでおおきい働きは期待できない。動きは昼過ぎてからであった。秀吉軍は天王山の山頂から山崎の里を抑えていて有利である。午後四時ごろ総攻撃となる。遊軍となっていた虎之助に秀吉からエンメイジへの攻撃を命じられる。白兵戦も羽柴軍に有利であった。大勝利である。
信長の子、信孝・のぶたか・と信勝・のぶかつ・は仲が悪い。武将では柴田勝家がいる。
光秀は長岡京市・勝龍寺城城に篭ったが、一夜ももつまい。そこを出て、安土や長浜にもどり再興を図るか。翌朝秀吉は淀の宿を出て近江の二井寺に陣を構えた。
長岡京市・勝龍寺城は翌朝落ちたが光秀はいなかった。そして二井寺の秀吉の陣に光秀が土民に竹やりで突かれ命を落としたとの知らせが入った。(JS)
↓京都の本能寺

☆明智光秀の娘・たまは、熊本初代藩主・細川忠興の妻でした。たまは数奇な運命です。キリシタンとなりガラシャとなります。
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第11話「本能寺の変」
水に漬かった高松城、城主・清水宗治の切腹した前日の天正11(1582)年6月3日、日本史最大ともいえるクーデター、本能寺の変が起きた。織田信長が中国遠征をはかり、その先兵たるべき明智光秀が警戒を解いて京都の本能寺に宿泊した信長を奇襲したのである。
羽柴秀吉は早飛脚の報でそれを知ったが顔色にも表さず、宗治の切腹を見届け、かつ毛利勢と和議を固めた。加藤虎之助は武将たちの末席からそれを見ていた。
秀吉は姫路の陣を発って東へ向かう。全軍を五部にわけ、それぞれが緊密に連絡を取る。大阪に向かい、そこで信長の遺子、三七郎信孝(さんしちろうのぶたか)を立て、光秀と決戦するつもりだ。これで大義名分は立つ。だが戦場がどこになるか、秀吉も光秀すらもわからない。
このとき光秀は55歳、秀吉は47歳であった。
虎之助は秀吉から直接命を受け、淀川沿いの山崎の地を望める天王山に足軽三十人を率いて備えた。
家来利吉と才八に馬一等。総員33名で最前線に臨むのである。
そして山崎の里で光秀軍の物見と遭遇し、相手の将の首をはねた。夜が明けると、秀吉軍が山崎に入ってきた。
6月13日、虎之助は早朝の物見の合戦で足軽二人を失い四人を負傷させているのでおおきい働きは期待できない。動きは昼過ぎてからであった。秀吉軍は天王山の山頂から山崎の里を抑えていて有利である。午後四時ごろ総攻撃となる。遊軍となっていた虎之助に秀吉からエンメイジへの攻撃を命じられる。白兵戦も羽柴軍に有利であった。大勝利である。
信長の子、信孝・のぶたか・と信勝・のぶかつ・は仲が悪い。武将では柴田勝家がいる。
光秀は長岡京市・勝龍寺城城に篭ったが、一夜ももつまい。そこを出て、安土や長浜にもどり再興を図るか。翌朝秀吉は淀の宿を出て近江の二井寺に陣を構えた。
長岡京市・勝龍寺城は翌朝落ちたが光秀はいなかった。そして二井寺の秀吉の陣に光秀が土民に竹やりで突かれ命を落としたとの知らせが入った。(JS)
↓京都の本能寺

☆明智光秀の娘・たまは、熊本初代藩主・細川忠興の妻でした。たまは数奇な運命です。キリシタンとなりガラシャとなります。
Posted by たわらや at
12:00
│Comments(0)
2011年02月21日
天狗舞 五凛 石川門 純米生酒 22BY
-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№222
天狗舞 『五凛』 石川門 純米生酒
1800ml:2415円(税込)
0720ml:1207円(税込)

製造元:車多酒造㈱ 石川県白山市坊丸60番地1
◆ 車多酒造「天狗舞」の酒蔵
創業文政六年(1823年)。初代蔵元 車多太右衛門が諸国行脚の折に口にした各地の酒の旨さが忘れられず、自らの居するこの地に酒蔵を構え、旨い酒をとの一心で酒造りをはじめたという。あの時、蔵はうっそうたる森に囲まれており、木々の葉のすれあう音がまるで天狗の舞う音に聞こえたそうです。その謂れから、《天狗舞》の酒銘は生まれたそうです。米の旨みを十二分に引き出す酒づくりの技法の一つである「山廃仕込み」を連綿と受継ぎ、「旨味」豊か、味わい深い酒を造っています。
◆ 新酒米ブランド・~石川門~
良質の酒を造るために開発された米が「酒米石川門」。酒米石川門は、「石川独自の米で、石川でしか造れない酒を造る」という長年の夢を現実のものにしました。十数年の歳月をかけた品種改良や試験栽培の結果、酒米の命ともいうべき心白が極めて大きい、吟醸酒づくりに適した、高品質の酒造好適米ができました。
平成20年、酒米石川門は酒づくりに理解のある4軒の酒米農家で栽培され、収穫された米は6軒の酒造会社で米の味がしっかり伝わる純米酒や純米吟醸酒などになりました。酒米生産者と酒造会社が連携した新しい石川の酒づくりが始まっています。
この度、この酒米を使って、車多酒造で仕込んだものがこの酒です。
酒米石川門の特徴は…
1.石川県での栽培に適している
2.早生品種/短棹で倒伏しにくい
3.吟醸酒向きの品質を有している
4.粒が大きい(五百万石よりも大粒)/心白が大きく、心白発現率が高い
酒米石川門の譜系図…

◆ 春先の限定酒。五凛 「石川門」純米生酒
2月12日 五凛「石川門」純米生酒が入荷しました。早速、この夜に試飲しました。
香りは控えめ。生酒ですのでフレッシュ。天狗舞の特徴である「旨み」を表現しながらも、すっきりしたさわやかな香りがあり、味わいもキレのある爽やかな味わいが広がります。完全に食中に向く食中酒です。
原料米: 石川県産 石川門
精米歩合:麹米60%
掛米60%
日本酒度: +3.0
酸 度: 1.4
アミノ酸度: 1.5
アルコール度数: 16.5%
酵 母: 金沢酵母
天狗舞 『五凛』 石川門 純米生酒
1800ml:2415円(税込)
0720ml:1207円(税込)

製造元:車多酒造㈱ 石川県白山市坊丸60番地1
◆ 車多酒造「天狗舞」の酒蔵
創業文政六年(1823年)。初代蔵元 車多太右衛門が諸国行脚の折に口にした各地の酒の旨さが忘れられず、自らの居するこの地に酒蔵を構え、旨い酒をとの一心で酒造りをはじめたという。あの時、蔵はうっそうたる森に囲まれており、木々の葉のすれあう音がまるで天狗の舞う音に聞こえたそうです。その謂れから、《天狗舞》の酒銘は生まれたそうです。米の旨みを十二分に引き出す酒づくりの技法の一つである「山廃仕込み」を連綿と受継ぎ、「旨味」豊か、味わい深い酒を造っています。
◆ 新酒米ブランド・~石川門~
良質の酒を造るために開発された米が「酒米石川門」。酒米石川門は、「石川独自の米で、石川でしか造れない酒を造る」という長年の夢を現実のものにしました。十数年の歳月をかけた品種改良や試験栽培の結果、酒米の命ともいうべき心白が極めて大きい、吟醸酒づくりに適した、高品質の酒造好適米ができました。
平成20年、酒米石川門は酒づくりに理解のある4軒の酒米農家で栽培され、収穫された米は6軒の酒造会社で米の味がしっかり伝わる純米酒や純米吟醸酒などになりました。酒米生産者と酒造会社が連携した新しい石川の酒づくりが始まっています。
この度、この酒米を使って、車多酒造で仕込んだものがこの酒です。
酒米石川門の特徴は…
1.石川県での栽培に適している
2.早生品種/短棹で倒伏しにくい
3.吟醸酒向きの品質を有している
4.粒が大きい(五百万石よりも大粒)/心白が大きく、心白発現率が高い
酒米石川門の譜系図…

◆ 春先の限定酒。五凛 「石川門」純米生酒
2月12日 五凛「石川門」純米生酒が入荷しました。早速、この夜に試飲しました。
香りは控えめ。生酒ですのでフレッシュ。天狗舞の特徴である「旨み」を表現しながらも、すっきりしたさわやかな香りがあり、味わいもキレのある爽やかな味わいが広がります。完全に食中に向く食中酒です。
原料米: 石川県産 石川門
精米歩合:麹米60%
掛米60%
日本酒度: +3.0
酸 度: 1.4
アミノ酸度: 1.5
アルコール度数: 16.5%
酵 母: 金沢酵母
Posted by たわらや at
07:00
│Comments(1)
2011年02月21日
2月21日 おはようございます。
平成23年02月21日(月)
旧暦:1月19日
たわらや酒店 日刊かわらばん アップします。
【亀の尾いよいよ発売】
昨日・2月20日、上槽(しぼり)がはじまりました。
発売日:03月12日(土)・九州新幹線全線開業の日に発売
1800ml換算で(限定)約550本発売予定。
予定価格は:1800ml/2625円(税込)・720ml/1313円(税込)
亀の尾ができるまでの様子を3月9日(水)夕方・熊本県民テレビ(KKT)のニュース番組で
放映予定です。乞うご期待!!
★予約承ります。予約多数の場合は、抽選といたします。
おはようございます。
今日は月曜日、一週間の始まりは何となく憂鬱です。
いつものように3時50分に起床しましたが、何となく眠いです。
今日の熊本(菊陽町)の天気は晴れ。
最低気温6℃。
日中は14℃まで上がる予報が出ています。
亀の尾の反響が凄いです。
日本酒に触れる切っ掛けの一つになったらいいですよね。
各地で、各酒蔵で、各酒屋でこんな運動が起こったら、
日本酒消費も向上すると思います。きっと・・・。
本日のかわら版をアップします。
午前07時00分:天狗舞『五凛』(ごりん) 石川門・純米生酒 只今入荷中!!
正午:仰清正公 №11 本能寺の変
旧暦:1月19日
たわらや酒店 日刊かわらばん アップします。
【亀の尾いよいよ発売】
昨日・2月20日、上槽(しぼり)がはじまりました。
発売日:03月12日(土)・九州新幹線全線開業の日に発売
1800ml換算で(限定)約550本発売予定。
予定価格は:1800ml/2625円(税込)・720ml/1313円(税込)
亀の尾ができるまでの様子を3月9日(水)夕方・熊本県民テレビ(KKT)のニュース番組で
放映予定です。乞うご期待!!
★予約承ります。予約多数の場合は、抽選といたします。
おはようございます。
今日は月曜日、一週間の始まりは何となく憂鬱です。
いつものように3時50分に起床しましたが、何となく眠いです。
今日の熊本(菊陽町)の天気は晴れ。
最低気温6℃。
日中は14℃まで上がる予報が出ています。
亀の尾の反響が凄いです。
日本酒に触れる切っ掛けの一つになったらいいですよね。
各地で、各酒蔵で、各酒屋でこんな運動が起こったら、
日本酒消費も向上すると思います。きっと・・・。
本日のかわら版をアップします。
午前07時00分:天狗舞『五凛』(ごりん) 石川門・純米生酒 只今入荷中!!
正午:仰清正公 №11 本能寺の変
Posted by たわらや at
06:48
│Comments(0)
2011年02月20日
九州初 酒米『亀の尾』で泰斗を造ろう №6 上槽
九州初 酒米「亀の尾」で泰斗を造ろう
シリーズ6:2月20日 上槽(搾る)
◆ 酒米『亀の尾』純米酒 しぼる
本日(2011年02月20日)午前11時より、熊本県山鹿市・千代の園酒造㈱にて、上槽(お酒を搾る)作業が行われました。上槽とは、モロミの液体部分(清酒)と固形部分(酒粕)に分離するという作業です。
亀の尾は、昨年11月に千代の園酒造へ持ち込まれました。収穫した米の量は860㎏。これを65%まで精米しまし、総米560㎏の仕込みで純米酒を造りました。通常の日本酒の仕込みが総米1500㎏、大吟醸小仕込みでも750㎏ですから、この『亀の尾』の仕込みが如何に小さいかが分かると思います。
1月16日(日)に酒母麹米の浸漬が始まりました。その後、酒母づくりが行われ、1月26日・本仕込み・初添え、1月28日・中添え、1月29日・留添えが行われました。
『亀の尾』のお米の特徴を、千代の園・製造部・金重真一氏(41)にたずねたところ、「お米が硬い。吸水を慎重に行う。そうしないと、麹米が上手くゆかず、お米が溶けなくなる。初めての種類の米なので、慎重に仕込む」とのことでした。
それから、23日。仕込み日数23日目の今日、上槽の時期を迎えました。昨日のモロミの状態は、日本酒度±0、アルコール度数17.4%、酸度2.35、アミノ酸度1.5だったそうです。


午前11時、仕込みタンクのノミが切られました。下の置いてある半切りのタライに、真っ白なモロミが迸ります。この日、集った方は、熊本酒文化の会「泰斗」販売の酒屋、たちばな酒店(熊本市)さん、緒方酒店(大津町)さん、宮本酒店(水俣市)さん、渡辺酒店(菊池市)さん、野田酒店(山鹿市)さん、酒の蔵元(長洲町)さん、そして私の7店。テレビ取材として熊本県民テレビ3名、醸界タイムス・上籠支局長が見守る中、約1時間の上槽が行われました。

◆『亀の尾』純米酒はべっぴんさん
昨日のデーターからすると、本日の酒は、想像ですが、
日本酒度+1~+2
アルコール度数18°弱
酸度2.4
アミノ酸度1.5
でしょう。
迸る亀の尾のモロミの香りは、涼しげな、高いところで香る吟醸香がありました。酵母は熊本KA-1号酵母。熊本では定番中の定番の酵母。私もこの酵母で仕込んだ、千代の園の酒をたくさんきき酒しましたが、香りの表現が明らかに違っています。精米歩合65%と、はっきり言ってあまり磨いていない米にして、モロミが大吟醸の高精白米のように真っ白。これには驚きました。


モロミをテフロンの酒袋に入れて、氷枕を縦に並べる容量で、槽の器の内側に並べていきます。テフロンの布の隙間から、自然に亀の尾の酒が迸ります。徐々に酒袋を上に積み上げていくために、下部は圧力がかかり、さらに酒が迸るのです。
ここで、出てきた酒は『あらばしり』といいます。
自然に迸らなくなると、槽の上から圧力をかけて酒を搾るのです。「あらばしり」から「中汲み」、そして「セメ」と呼ばれます。香味もそれぞれに違っていきます。
これから、2日間をかけて、亀の尾の酒を搾ります。
さて、一番みなさんが知りたい部分を書きます。
酒はどんな感じかということですが。香りは、青リンゴ、若草、ミントを思わせる香りです。熊本酵母らしい熟れたバナナの香りが全く感じられません。香りからこれまでの熊本の酒にない香りの酒でした。
続いて味わい。すっきりした爽やかな味わい。きれいな旋律の酒質。フランスアルザスの白ワインのように、すっきりした辛口の酒質です。お世辞にも芳醇ではなく、スレンダーな酒質。酸度2.35という高い酸度とは思えない酒質です。産まれたばかりの酒は、炭酸ガスが絡んで飲みにくいのですが、この酒はすでに飲みごろ。アルコール度数を15.5%に和水すると、きっと水っぽくなる気がしました。無濾過原酒の状態で、十分にバランスが取れて美味しいお酒です。
◆発売は?。(あくまで予定)
発売本数は、総米560㎏で、垂れ歩合300ℓ/1tで計算すると、無濾過生原酒で980ℓの酒ができることになります。一升瓶で550本程度。20店の販売店で販売すると、約30本程度の少ない量です。
発売は3月12日(土)・九州新幹線開業の日の予定です。泰斗の販売店で発売します。
亀の尾を田植えから発売までを、3月9日(水)夕方の熊本県民テレビ(KKT)のニュースで放映されます。ご覧ください。
価格は、未定ですが、1800ml・2625円、720ml・1313円かなぁ~。
【責任問合先】
㈲たわらや酒店 宇野 功一
096-232-3138 メール:info@tawaraya-sake.co.jp


シリーズ6:2月20日 上槽(搾る)
◆ 酒米『亀の尾』純米酒 しぼる
本日(2011年02月20日)午前11時より、熊本県山鹿市・千代の園酒造㈱にて、上槽(お酒を搾る)作業が行われました。上槽とは、モロミの液体部分(清酒)と固形部分(酒粕)に分離するという作業です。
亀の尾は、昨年11月に千代の園酒造へ持ち込まれました。収穫した米の量は860㎏。これを65%まで精米しまし、総米560㎏の仕込みで純米酒を造りました。通常の日本酒の仕込みが総米1500㎏、大吟醸小仕込みでも750㎏ですから、この『亀の尾』の仕込みが如何に小さいかが分かると思います。
1月16日(日)に酒母麹米の浸漬が始まりました。その後、酒母づくりが行われ、1月26日・本仕込み・初添え、1月28日・中添え、1月29日・留添えが行われました。
『亀の尾』のお米の特徴を、千代の園・製造部・金重真一氏(41)にたずねたところ、「お米が硬い。吸水を慎重に行う。そうしないと、麹米が上手くゆかず、お米が溶けなくなる。初めての種類の米なので、慎重に仕込む」とのことでした。
それから、23日。仕込み日数23日目の今日、上槽の時期を迎えました。昨日のモロミの状態は、日本酒度±0、アルコール度数17.4%、酸度2.35、アミノ酸度1.5だったそうです。


午前11時、仕込みタンクのノミが切られました。下の置いてある半切りのタライに、真っ白なモロミが迸ります。この日、集った方は、熊本酒文化の会「泰斗」販売の酒屋、たちばな酒店(熊本市)さん、緒方酒店(大津町)さん、宮本酒店(水俣市)さん、渡辺酒店(菊池市)さん、野田酒店(山鹿市)さん、酒の蔵元(長洲町)さん、そして私の7店。テレビ取材として熊本県民テレビ3名、醸界タイムス・上籠支局長が見守る中、約1時間の上槽が行われました。

◆『亀の尾』純米酒はべっぴんさん
昨日のデーターからすると、本日の酒は、想像ですが、
日本酒度+1~+2
アルコール度数18°弱
酸度2.4
アミノ酸度1.5
でしょう。
迸る亀の尾のモロミの香りは、涼しげな、高いところで香る吟醸香がありました。酵母は熊本KA-1号酵母。熊本では定番中の定番の酵母。私もこの酵母で仕込んだ、千代の園の酒をたくさんきき酒しましたが、香りの表現が明らかに違っています。精米歩合65%と、はっきり言ってあまり磨いていない米にして、モロミが大吟醸の高精白米のように真っ白。これには驚きました。


モロミをテフロンの酒袋に入れて、氷枕を縦に並べる容量で、槽の器の内側に並べていきます。テフロンの布の隙間から、自然に亀の尾の酒が迸ります。徐々に酒袋を上に積み上げていくために、下部は圧力がかかり、さらに酒が迸るのです。
ここで、出てきた酒は『あらばしり』といいます。
自然に迸らなくなると、槽の上から圧力をかけて酒を搾るのです。「あらばしり」から「中汲み」、そして「セメ」と呼ばれます。香味もそれぞれに違っていきます。
これから、2日間をかけて、亀の尾の酒を搾ります。
さて、一番みなさんが知りたい部分を書きます。
酒はどんな感じかということですが。香りは、青リンゴ、若草、ミントを思わせる香りです。熊本酵母らしい熟れたバナナの香りが全く感じられません。香りからこれまでの熊本の酒にない香りの酒でした。
続いて味わい。すっきりした爽やかな味わい。きれいな旋律の酒質。フランスアルザスの白ワインのように、すっきりした辛口の酒質です。お世辞にも芳醇ではなく、スレンダーな酒質。酸度2.35という高い酸度とは思えない酒質です。産まれたばかりの酒は、炭酸ガスが絡んで飲みにくいのですが、この酒はすでに飲みごろ。アルコール度数を15.5%に和水すると、きっと水っぽくなる気がしました。無濾過原酒の状態で、十分にバランスが取れて美味しいお酒です。
◆発売は?。(あくまで予定)
発売本数は、総米560㎏で、垂れ歩合300ℓ/1tで計算すると、無濾過生原酒で980ℓの酒ができることになります。一升瓶で550本程度。20店の販売店で販売すると、約30本程度の少ない量です。
発売は3月12日(土)・九州新幹線開業の日の予定です。泰斗の販売店で発売します。
亀の尾を田植えから発売までを、3月9日(水)夕方の熊本県民テレビ(KKT)のニュースで放映されます。ご覧ください。
価格は、未定ですが、1800ml・2625円、720ml・1313円かなぁ~。
【責任問合先】
㈲たわらや酒店 宇野 功一
096-232-3138 メール:info@tawaraya-sake.co.jp


Posted by たわらや at
22:13
│Comments(0)



