2011年02月26日
コラム・呑んどっと №20 寿司の古今を考える
-コラム・呑んどっと-№20
寿司の古今を考える
■ 富山駅 駅弁 『特選ますのすし』

(㈱源 1700円)
最近は百貨店の催事で、全国有名駅弁大会がよく行われています。全国各地の旧国鉄を完乗を8年かがりで行った私にとって、とくに印象に残る駅弁が富山駅の『ますのすし』です。駅弁大会でも高い人気の駅弁当です。今年も、私の地元の百貨店で駅弁当大会がありました。もちろん『ますのすし』を買い、お燗酒を飲みながら、ますのすしを食べました。旨かったです。
富山駅『ますのすし』の歴史はたいへんに古い。1912年(明治45年)に発売が開始されています。富山駅の開業は1899年(明治32年)。北陸本線は字のごとく、近畿地方から北陸を結ぶ大動脈。物資輸送もさることながら、駅弁が発売されるようになったのは旅客輸送が増えたからでしょう。
丸い輪っぱに、富山県産のコシヒカリを酢飯にして、朱鷺色の鱒を敷き詰め、笹でくるんだ押し寿司が『ますのすし』です。笹の葉の緑と鱒の朱鷺色が色鮮やかで、まさに駅弁のの芸術品と言っていいような駅弁です。
北陸本線を走る特急の車内テーブルにちょうど載せれる程の大きなになっています。『ますのすし』の箱の中に付属のプラステック製のナイフがついています。それを使って、8等分に割って食べます。押し寿司なので、おなかいっぱいになります。
私も北陸本線を旅する時には、必ず、この『ますのすし』を2つ購入します。1つは、すぐに車内で食べます。もう1つは、お土産にします。賞味期限が切れるのですが、『ますのすし』も押し寿司でありますので、少し時間を経過して美味しくなります。お酢と鱒とシャリが馴染むのでしょうか。どのくらい熟成させるかというと約1~2日。車内で食べるできたての『ますのすし』よりも格段に旨くなります。熟成させたものを売っていればいいのですが、製造する駅弁の会社としては、賞味期限がくれば、販売することはできないため、この熟成『ますのすし』づくりは、購入した人の楽しみな作業になります。
この『ますのすし』は、江戸時代に八代将軍・徳川吉宗が、富山藩主より献上され、たいへん気に入ったということです。きっとその時に吉宗が食した『ますのすし』も熟成した『ますのすし』であったと思います。ちなみに笹の葉は殺菌作用もあるということでくるんであるようです。先人達の美意識と知恵に感服します。
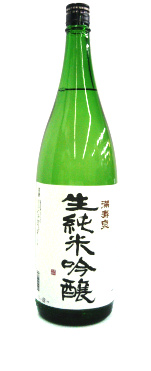
富山のますのすし には 富山の銘酒「満寿泉」がぴったり。
原料米 兵庫産
麹米:山田錦
掛米:山田錦
精米歩合:麹米50%
:掛米40%
日本酒度:非公開
酸 度:非公開
アミノ酸度:非公開
アルコール度数:16~17%
酵 母:
価 格:1800ml 3150円(税込)
■ 寿司の古今を考える
『ますのすし』を食べながら、子どもからこんな質問がきた。
「生の魚を切り身にしてシャリに載せたものが寿司だが、『ますのすし』や『松前寿司』はシャリを押しつぶした押寿司。具を散らしたチラシ寿司など寿司といいながらいろいろあるけど、どう違うのか?」
というものであった。なるほど、寿司(鮨)という名称は同じでも、少しづつ製法の違いを指摘したものであろう。
私なりに調べてみました。
■ 寿司の起源は馴れ寿司
馴れ寿司をご存知でしょうか?。有名なのは、琵琶湖(滋賀県)周辺で食べらている鮒の馴れ寿司が有名です。
太古の昔、冷蔵庫が無かった時代、川や湖・海で獲れた魚を長期保存するために生まれた保存食が馴れ寿司です。魚の持つ、有用な動物性たんぱく質を長期保存する知恵は、我々祖先が編み出した食文化の歴史そのものです。
獲れた魚に塩と飯を混ぜ合わせ、樽などのような容器に入れます。丈上部に蓋をして、蓋の上に重石を置いて圧力をかけます。この状態で、短くて数カ月、もしくは何年もの間この状態を保ちます。
炊いた米が時間と伴に乳酸発酵をし始めます。飯から乳酸が生まれます。乳酸発酵がどんどん進み、その結果、飯状の粒粒は原型をとどめない形になりますが、樽の中は乳酸によりPHが低下します。つまり酸性状態となり、雑菌の繁殖が抑制されるか死滅されます。
これによって、長期保存が可能となるということになります。また、魚のタンパク質は、アミノ酸に分解されます。アミノ酸は旨味の成分ですので、馴れる程に旨味を増すということになります。
臭いは、ちょうど、八丈島などで造られるクサヤの干物に似ています。一種独特の臭いがありますので好き嫌いがはっきり分かれます。
一般的にタンパク質分解酵素を含んだ微生物にはこの系統の臭いがあります。腐敗しているか、発酵しているか、紙一重のような微妙は臭いです。
寒冷な地方では、蒸した飯に加えて、麹米を用いる馴れ寿司もあります。麹の持つ糖化酵素に作用により、発酵を促し、甘みを増す保存食を作り出します。石川県のカブラ寿司、秋田県のハタハタ寿司が麹米を入れた馴れ寿司です。
■ 押し寿司から江戸前へ
馴れ寿司が出来上がるまで、何カ月、何年という時間がかかります。米酢が作られるようになった室町時代後期に、蒸飯に酢を混ぜ、箱に入れてネタを上に置き、重石を置いて食べる押し寿司ができました。
私たちが一般的に想像する寿司は江戸前。シャリの上に新鮮な肴が乗ったものが登場するのは今から200年前の江戸・両国。諸説あるが、文化12(1829)年には文献に登場しています。長期保存食から、気の短い江戸っ子が育んだ直ぐに食べられる寿司まで、時代とともに変化しています。いずれの寿司も晴れの日のご馳走であったことは変わりがないようです。
さて、21世紀は回転寿司からどんな寿司が産まれるのでしょうか?。食の進化を見るもの楽しみの一つです。
寿司の古今を考える
■ 富山駅 駅弁 『特選ますのすし』

(㈱源 1700円)
最近は百貨店の催事で、全国有名駅弁大会がよく行われています。全国各地の旧国鉄を完乗を8年かがりで行った私にとって、とくに印象に残る駅弁が富山駅の『ますのすし』です。駅弁大会でも高い人気の駅弁当です。今年も、私の地元の百貨店で駅弁当大会がありました。もちろん『ますのすし』を買い、お燗酒を飲みながら、ますのすしを食べました。旨かったです。
富山駅『ますのすし』の歴史はたいへんに古い。1912年(明治45年)に発売が開始されています。富山駅の開業は1899年(明治32年)。北陸本線は字のごとく、近畿地方から北陸を結ぶ大動脈。物資輸送もさることながら、駅弁が発売されるようになったのは旅客輸送が増えたからでしょう。
丸い輪っぱに、富山県産のコシヒカリを酢飯にして、朱鷺色の鱒を敷き詰め、笹でくるんだ押し寿司が『ますのすし』です。笹の葉の緑と鱒の朱鷺色が色鮮やかで、まさに駅弁のの芸術品と言っていいような駅弁です。
北陸本線を走る特急の車内テーブルにちょうど載せれる程の大きなになっています。『ますのすし』の箱の中に付属のプラステック製のナイフがついています。それを使って、8等分に割って食べます。押し寿司なので、おなかいっぱいになります。
私も北陸本線を旅する時には、必ず、この『ますのすし』を2つ購入します。1つは、すぐに車内で食べます。もう1つは、お土産にします。賞味期限が切れるのですが、『ますのすし』も押し寿司でありますので、少し時間を経過して美味しくなります。お酢と鱒とシャリが馴染むのでしょうか。どのくらい熟成させるかというと約1~2日。車内で食べるできたての『ますのすし』よりも格段に旨くなります。熟成させたものを売っていればいいのですが、製造する駅弁の会社としては、賞味期限がくれば、販売することはできないため、この熟成『ますのすし』づくりは、購入した人の楽しみな作業になります。
この『ますのすし』は、江戸時代に八代将軍・徳川吉宗が、富山藩主より献上され、たいへん気に入ったということです。きっとその時に吉宗が食した『ますのすし』も熟成した『ますのすし』であったと思います。ちなみに笹の葉は殺菌作用もあるということでくるんであるようです。先人達の美意識と知恵に感服します。
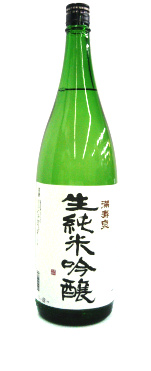
富山のますのすし には 富山の銘酒「満寿泉」がぴったり。
原料米 兵庫産
麹米:山田錦
掛米:山田錦
精米歩合:麹米50%
:掛米40%
日本酒度:非公開
酸 度:非公開
アミノ酸度:非公開
アルコール度数:16~17%
酵 母:
価 格:1800ml 3150円(税込)
■ 寿司の古今を考える
『ますのすし』を食べながら、子どもからこんな質問がきた。
「生の魚を切り身にしてシャリに載せたものが寿司だが、『ますのすし』や『松前寿司』はシャリを押しつぶした押寿司。具を散らしたチラシ寿司など寿司といいながらいろいろあるけど、どう違うのか?」
というものであった。なるほど、寿司(鮨)という名称は同じでも、少しづつ製法の違いを指摘したものであろう。
私なりに調べてみました。
■ 寿司の起源は馴れ寿司
馴れ寿司をご存知でしょうか?。有名なのは、琵琶湖(滋賀県)周辺で食べらている鮒の馴れ寿司が有名です。
太古の昔、冷蔵庫が無かった時代、川や湖・海で獲れた魚を長期保存するために生まれた保存食が馴れ寿司です。魚の持つ、有用な動物性たんぱく質を長期保存する知恵は、我々祖先が編み出した食文化の歴史そのものです。
獲れた魚に塩と飯を混ぜ合わせ、樽などのような容器に入れます。丈上部に蓋をして、蓋の上に重石を置いて圧力をかけます。この状態で、短くて数カ月、もしくは何年もの間この状態を保ちます。
炊いた米が時間と伴に乳酸発酵をし始めます。飯から乳酸が生まれます。乳酸発酵がどんどん進み、その結果、飯状の粒粒は原型をとどめない形になりますが、樽の中は乳酸によりPHが低下します。つまり酸性状態となり、雑菌の繁殖が抑制されるか死滅されます。
これによって、長期保存が可能となるということになります。また、魚のタンパク質は、アミノ酸に分解されます。アミノ酸は旨味の成分ですので、馴れる程に旨味を増すということになります。
臭いは、ちょうど、八丈島などで造られるクサヤの干物に似ています。一種独特の臭いがありますので好き嫌いがはっきり分かれます。
一般的にタンパク質分解酵素を含んだ微生物にはこの系統の臭いがあります。腐敗しているか、発酵しているか、紙一重のような微妙は臭いです。
寒冷な地方では、蒸した飯に加えて、麹米を用いる馴れ寿司もあります。麹の持つ糖化酵素に作用により、発酵を促し、甘みを増す保存食を作り出します。石川県のカブラ寿司、秋田県のハタハタ寿司が麹米を入れた馴れ寿司です。
■ 押し寿司から江戸前へ
馴れ寿司が出来上がるまで、何カ月、何年という時間がかかります。米酢が作られるようになった室町時代後期に、蒸飯に酢を混ぜ、箱に入れてネタを上に置き、重石を置いて食べる押し寿司ができました。
私たちが一般的に想像する寿司は江戸前。シャリの上に新鮮な肴が乗ったものが登場するのは今から200年前の江戸・両国。諸説あるが、文化12(1829)年には文献に登場しています。長期保存食から、気の短い江戸っ子が育んだ直ぐに食べられる寿司まで、時代とともに変化しています。いずれの寿司も晴れの日のご馳走であったことは変わりがないようです。
さて、21世紀は回転寿司からどんな寿司が産まれるのでしょうか?。食の進化を見るもの楽しみの一つです。
Posted by たわらや at 20:25│Comments(0)


