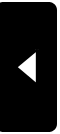2011年02月12日
仰清正公 №3 蛇の目
-仰清正公- №3 蛇の目
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第3話「蛇の目」
「蛇の目」といったら何を思いますか?。この文章をお読みになっている方々は、日本酒ファンですから、きっと「きき猪口(ちょこ)を思い出すでしょうね。
一世代前の人なら「蛇の目傘」を思い浮かべるでしょう。和傘の一種で、華奢(きゃしゃ)に細身に作られていました。傘を開くと、傘紙の真ん中寄りに二重の蛇の目が白抜きされていました。女性用といえましょう。
二世代前の人なら、家紋、紋所と答えるでしょうね。戦国武将の加藤清正の家紋は蛇の目です。その末裔たる富士酒造の蔵元加藤家の家紋も、当然蛇の目です。
さて、今回は「きき猪口」の蛇の目の話をしましょう。
日本酒ファンの皆さんは、日本酒のきき酒はきき猪口でやることをご存知ですが、あれがファンの間に周知されたのは三十年前ぐらいからなんです。それ以前も酒蔵の中ではきき猪口が使われていましたが、ファンはそのことを知りませんでした。当時は酒を飲むときはほとんど燗酒でしたから、徳利と小さい杯を使っていました。
吟醸酒が熱心なファンたちの手で発見発掘されて、吟醸酒は冷で飲むので、グラスまたは大振りなきき猪口がファンたちの前に登場したのです。
きき猪口は、酒の品質を見るのによくできた酒器なのです。酒の品質を見るときは、味と香りが中心なのですが、識別力の高い視力でも判別できるのです。識別の酒の数が多くなると、味覚や臭覚は数重なると麻痺してきますが視覚はそういうことがありません。そこで数多いきき酒のときほどきき猪口が重宝されたのでした。
酒は視覚にどう映るのでしょうか。まず色を見るために地は白色でなければなりません。次に透明度を見るために、くっきり見えるものが欲しいですね。それが濃い藍色(ほとんど黒色)の蛇の目なのです。
それだけでは十分ではありません。たくさん並べてきき酒する、その数だけのきき猪口が、同一白色同一濃い藍色をしていなければならないのです。ですから、酒蔵にあるものや研究機関にあるきき猪口の外側面に、それぞれの字体で1から50の番号や銘柄名が焼き付けてありました。つまり50個が1セットなのです。
今は、釉薬と焼成技術が向上しましたから、通し番号つきのものは見かけなくなりましたね。
形状は、直径が8センチ、高さが7センチです。縁の上端は外に向かって傾斜しています。香りをかぐとき、鼻がすっぽり覆われる口径と、酒が口内に幅広く流れ込むようになっているのです。
ちなみに、お醤油のためのきき猪口もあります。これは、底がとても浅くなっています。醤油の場合、数ミリしか注ぎません。
どうもきき猪口は、本草(漢方薬)の煎じ薬の鑑定から酒の法へ移ってきたらしいのですが、その歴史は調査中です。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第3話「蛇の目」
「蛇の目」といったら何を思いますか?。この文章をお読みになっている方々は、日本酒ファンですから、きっと「きき猪口(ちょこ)を思い出すでしょうね。
一世代前の人なら「蛇の目傘」を思い浮かべるでしょう。和傘の一種で、華奢(きゃしゃ)に細身に作られていました。傘を開くと、傘紙の真ん中寄りに二重の蛇の目が白抜きされていました。女性用といえましょう。
二世代前の人なら、家紋、紋所と答えるでしょうね。戦国武将の加藤清正の家紋は蛇の目です。その末裔たる富士酒造の蔵元加藤家の家紋も、当然蛇の目です。
さて、今回は「きき猪口」の蛇の目の話をしましょう。
日本酒ファンの皆さんは、日本酒のきき酒はきき猪口でやることをご存知ですが、あれがファンの間に周知されたのは三十年前ぐらいからなんです。それ以前も酒蔵の中ではきき猪口が使われていましたが、ファンはそのことを知りませんでした。当時は酒を飲むときはほとんど燗酒でしたから、徳利と小さい杯を使っていました。
吟醸酒が熱心なファンたちの手で発見発掘されて、吟醸酒は冷で飲むので、グラスまたは大振りなきき猪口がファンたちの前に登場したのです。
きき猪口は、酒の品質を見るのによくできた酒器なのです。酒の品質を見るときは、味と香りが中心なのですが、識別力の高い視力でも判別できるのです。識別の酒の数が多くなると、味覚や臭覚は数重なると麻痺してきますが視覚はそういうことがありません。そこで数多いきき酒のときほどきき猪口が重宝されたのでした。
酒は視覚にどう映るのでしょうか。まず色を見るために地は白色でなければなりません。次に透明度を見るために、くっきり見えるものが欲しいですね。それが濃い藍色(ほとんど黒色)の蛇の目なのです。
それだけでは十分ではありません。たくさん並べてきき酒する、その数だけのきき猪口が、同一白色同一濃い藍色をしていなければならないのです。ですから、酒蔵にあるものや研究機関にあるきき猪口の外側面に、それぞれの字体で1から50の番号や銘柄名が焼き付けてありました。つまり50個が1セットなのです。
今は、釉薬と焼成技術が向上しましたから、通し番号つきのものは見かけなくなりましたね。
形状は、直径が8センチ、高さが7センチです。縁の上端は外に向かって傾斜しています。香りをかぐとき、鼻がすっぽり覆われる口径と、酒が口内に幅広く流れ込むようになっているのです。
ちなみに、お醤油のためのきき猪口もあります。これは、底がとても浅くなっています。醤油の場合、数ミリしか注ぎません。
どうもきき猪口は、本草(漢方薬)の煎じ薬の鑑定から酒の法へ移ってきたらしいのですが、その歴史は調査中です。(JS)
Posted by たわらや at
07:04
│Comments(0)
2011年02月11日
仰清正公 №2 落語に出てくる清正公
-仰清正公- №2 落語に出てくる清正公
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第2話「落語に出てくる清正公」
戦国時代の武将と落語と、縁がなさそうなのですが、「清正公酒屋」と、ちゃんと名前まで入っている落語があります。
この場合、清正公は、「せいしょうこう」と呼びます。落語という話芸ができたのは江戸時代で、加藤清正は江戸っ子に人気があり、「せいしょうこう」と呼ばれていたようです。
アラスジ--
江戸のある町、二軒のお店が向かい合ってありました。
一方は菓子屋で屋号は虎屋、木彫りの虎を屋根に載せ、それが看板になっている。 一方は酒屋で、加藤清正の木像を店に飾っているので清正公酒屋と呼ばれている。甘党と辛党、扱うものお客の筋もちがう。清正と虎、両家が仲がいいはずはない。
その上、虎屋はお念仏(南無阿弥陀仏の宗旨)、酒屋はお題目(南無妙法蓮華経の宗旨)である。
酒屋の息子、清七は、町内一の好男子、つまりイケメンで、虎屋の娘おなかは小町といわれる美貌。これが相思相愛の仲になってしまった。ともに一人息子と一人娘、これまでのいきさつもあり、結ばれる縁ではない。本人たちも親にせがんだ。
虎屋は娘を遠いところの親類に預けたが、恋の炎は燃え盛るのみ。
清七は、おなかから来た手紙に誘われてたずね、連れ出す。が、添いとげることはできないと、あの世で結ばれようと情死することを決め大川に身を投げることになる。
一歩先におなかが飛び込んだ。清七も続いて飛び込もうとすると、「待て清七、はやまるな」と腕を捕まれる。
振り向くとそこにいるのは蛇の目紋をつけた烏帽子に鎧兜、手に片鎌の槍を持つ清正公ではないか。
清七は「アァ、ありがとうぞんじます。どうせお助けくださるなら、女のほうも願います」
「いやいや、おなかの方は助けることはできん」
「そりゃまた、なぜでございます」
--あとはこの落語のオチになります。このオチを明かさないのが落語の話をするときの掟です。どうぞ寄席で聞いてください。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第2話「落語に出てくる清正公」
戦国時代の武将と落語と、縁がなさそうなのですが、「清正公酒屋」と、ちゃんと名前まで入っている落語があります。
この場合、清正公は、「せいしょうこう」と呼びます。落語という話芸ができたのは江戸時代で、加藤清正は江戸っ子に人気があり、「せいしょうこう」と呼ばれていたようです。
アラスジ--
江戸のある町、二軒のお店が向かい合ってありました。
一方は菓子屋で屋号は虎屋、木彫りの虎を屋根に載せ、それが看板になっている。 一方は酒屋で、加藤清正の木像を店に飾っているので清正公酒屋と呼ばれている。甘党と辛党、扱うものお客の筋もちがう。清正と虎、両家が仲がいいはずはない。
その上、虎屋はお念仏(南無阿弥陀仏の宗旨)、酒屋はお題目(南無妙法蓮華経の宗旨)である。
酒屋の息子、清七は、町内一の好男子、つまりイケメンで、虎屋の娘おなかは小町といわれる美貌。これが相思相愛の仲になってしまった。ともに一人息子と一人娘、これまでのいきさつもあり、結ばれる縁ではない。本人たちも親にせがんだ。
虎屋は娘を遠いところの親類に預けたが、恋の炎は燃え盛るのみ。
清七は、おなかから来た手紙に誘われてたずね、連れ出す。が、添いとげることはできないと、あの世で結ばれようと情死することを決め大川に身を投げることになる。
一歩先におなかが飛び込んだ。清七も続いて飛び込もうとすると、「待て清七、はやまるな」と腕を捕まれる。
振り向くとそこにいるのは蛇の目紋をつけた烏帽子に鎧兜、手に片鎌の槍を持つ清正公ではないか。
清七は「アァ、ありがとうぞんじます。どうせお助けくださるなら、女のほうも願います」
「いやいや、おなかの方は助けることはできん」
「そりゃまた、なぜでございます」
--あとはこの落語のオチになります。このオチを明かさないのが落語の話をするときの掟です。どうぞ寄席で聞いてください。(JS)
Posted by たわらや at
11:51
│Comments(0)
2011年02月11日
分かりやすい清酒醸造学 №8仮面ライダーみたいな清酒酵母たち
-分かりやすい醸造学- №8
仮面ライダーみたいな優良清酒酵母たち
◆ 優良清酒酵母
酒づくりに関与する酵母は、優良清酒酵母と野生酵母(家付酵母を含)に分けられます。
優良清酒酵母は、目標とする酒づくり、例えば、目標のアルコール度数、目標の日本酒度や酸度やアミノ酸度、整った香味にピッタリとあった、醸造経過をコントロールできる酵母を指します。一般に低温でよく発酵を致します。
◆ 仮面ライダーみたいな日本酒の酵母
日本酒のラベルの裏側を見た時に、使用酵母の欄があります。その欄の中に「7号酵母」やら「9号酵母」などと記載されています。弊店にご来店なさったお客様からこんな質問が来ました。
「使用酵母の7号やら9号って何ですか?」
「酵母が換えれば、酒の味は違うのですか?」
答えは、7号やら9号というのは、酵母に付けられた名前のことです。日本醸造協会では、全国から優秀な日本酒や焼酎を醸しだす酵母を集めて、培養して、全国の日本酒や焼酎蔵に販売しているのです。発見した順番で1号から番号がついています。
昭和50年ごろから、吟醸酒がブームになるとともに吟醸酵母が注目を集めてきました。もともと酒蔵にはその蔵に住み着く「蔵付酵母」がいて、優秀な酵母は「日本醸造協会」に登録され全国の蔵元に配布されているのです。これは、健全に優れた日本酒を全国的に釀造できることは、特に戦前は国を富ますため重要な政策だったようです。酒税で日本は富国強兵を進めてゆきました。
最近では、県単位に独自酵母の開発が進み、静岡酵母、秋田酵母、アルプス酵母(長野)など有名な酵母が排出され、そのいくつかは日本醸造協会に登録され、全国に協会酵母として配布されています。
◆ 同じ酵母を使っても同じ原料を使っても、同じ香味にならないのは何故?
日本酒の大半が協会9号や10号酵母で造られています。原料米も精白歩合も同じ、酵母も同じなのに、香味が大きく違う日本酒があります。どうしてですか?という質問が来ます。
同じ酵母を使っても、蔵の中には蔵付酵母という蔵ごとに異なる自然酵母が存在します。蔵内の空気中を浮遊して、仕込中にタンクに入り醗酵に関与します。もちろん、蔵人の流儀の違いもありますが、酵母の見えない力が関わっているのは事実なのです。
【協会酵母一覧】
協会酵母×市販年×分離蔵元
1号(灘)×明治39×桜正宗
2号(京都)×明治?×月桂冠
3号(広島)×大正3×酔心
4号(広島)×大正13×不明
5号(広島)×大正14×賀茂鶴
6号(秋田)×昭和10×新政
7号(長野)×昭和21×真澄
8号 ×昭和37×試験所
9号(熊本)×昭和43×香露
10号(東北)×昭和52× 明利
11号 ×昭和50×試験所
12号(宮城)×昭和41×浦霞
13号 ×昭和56×9号と10号の交配
14号(金沢)×平成7×金沢
15号(秋田)×平成8×秋田
この他にも、県レベルで沢山の優秀な酵母が分離開発され、日本酒の香味のバリエーションを生み出しています。
仮面ライダーみたいな優良清酒酵母たち
◆ 優良清酒酵母
酒づくりに関与する酵母は、優良清酒酵母と野生酵母(家付酵母を含)に分けられます。
優良清酒酵母は、目標とする酒づくり、例えば、目標のアルコール度数、目標の日本酒度や酸度やアミノ酸度、整った香味にピッタリとあった、醸造経過をコントロールできる酵母を指します。一般に低温でよく発酵を致します。
◆ 仮面ライダーみたいな日本酒の酵母
日本酒のラベルの裏側を見た時に、使用酵母の欄があります。その欄の中に「7号酵母」やら「9号酵母」などと記載されています。弊店にご来店なさったお客様からこんな質問が来ました。
「使用酵母の7号やら9号って何ですか?」
「酵母が換えれば、酒の味は違うのですか?」
答えは、7号やら9号というのは、酵母に付けられた名前のことです。日本醸造協会では、全国から優秀な日本酒や焼酎を醸しだす酵母を集めて、培養して、全国の日本酒や焼酎蔵に販売しているのです。発見した順番で1号から番号がついています。
昭和50年ごろから、吟醸酒がブームになるとともに吟醸酵母が注目を集めてきました。もともと酒蔵にはその蔵に住み着く「蔵付酵母」がいて、優秀な酵母は「日本醸造協会」に登録され全国の蔵元に配布されているのです。これは、健全に優れた日本酒を全国的に釀造できることは、特に戦前は国を富ますため重要な政策だったようです。酒税で日本は富国強兵を進めてゆきました。
最近では、県単位に独自酵母の開発が進み、静岡酵母、秋田酵母、アルプス酵母(長野)など有名な酵母が排出され、そのいくつかは日本醸造協会に登録され、全国に協会酵母として配布されています。
◆ 同じ酵母を使っても同じ原料を使っても、同じ香味にならないのは何故?
日本酒の大半が協会9号や10号酵母で造られています。原料米も精白歩合も同じ、酵母も同じなのに、香味が大きく違う日本酒があります。どうしてですか?という質問が来ます。
同じ酵母を使っても、蔵の中には蔵付酵母という蔵ごとに異なる自然酵母が存在します。蔵内の空気中を浮遊して、仕込中にタンクに入り醗酵に関与します。もちろん、蔵人の流儀の違いもありますが、酵母の見えない力が関わっているのは事実なのです。
【協会酵母一覧】
協会酵母×市販年×分離蔵元
1号(灘)×明治39×桜正宗
2号(京都)×明治?×月桂冠
3号(広島)×大正3×酔心
4号(広島)×大正13×不明
5号(広島)×大正14×賀茂鶴
6号(秋田)×昭和10×新政
7号(長野)×昭和21×真澄
8号 ×昭和37×試験所
9号(熊本)×昭和43×香露
10号(東北)×昭和52× 明利
11号 ×昭和50×試験所
12号(宮城)×昭和41×浦霞
13号 ×昭和56×9号と10号の交配
14号(金沢)×平成7×金沢
15号(秋田)×平成8×秋田
この他にも、県レベルで沢山の優秀な酵母が分離開発され、日本酒の香味のバリエーションを生み出しています。
Posted by たわらや at
11:47
│Comments(0)
2011年02月10日
仰清正公 №1 家紋
-仰清正公 -№1 家紋
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第一話「家紋」
古いお家には、それぞれの家紋があります。紋所と呼ばれることもあります。いまはほとんど使われなくなりましたが、和服の正装である紋付羽織は、襟と袖に紋所が入ったものです。
江戸時代には、この紋服だけでなく、家具、調度類、武器、建物、提灯などにも紋所を記して、人目でどの家かわかるようにしていました。
有名なのは徳川家の三つ葉葵()みつばあおいです。水戸光圀の諸国漫遊で、イザというところで「これが見えぬか」と示すのは、印籠にある三つ葉葵ですよね。
それにおとらず有名なのが加藤清正の「蛇の目」の紋所です。蛇の目というのは、二重の幅広の同心円をいいます。二重丸を幅広く描いたのが蛇の目です。
加藤家では、「蛇の目」と「桔梗」の両方の紋を持っていました。もう一つ、硯の紋もあるそうです。

(↑蛇の目の紋)

(↑桔梗の紋)
加藤清正の虎退治の絵は、江戸時代の清正人気の象徴といえる図柄です。清正は、槍の使い手で、烏帽子(えぼし・縦長の被り物)兜にくっきりと蛇の目紋が描かれ、片鎌の槍を構えて、咆哮する虎と対峙する構図は、勇ましいものでした。
富士酒造の加藤家の家紋も「蛇の目」です。古い日本家屋や蔵のあちこちに、蛇の目紋が描かれています。拝見はしていませんが、羽織にも蛇の目が染め抜かれているのでしょう。そのほか、先祖から伝わっている調度類にも蛇の目が印されているのでしょうね。(JS)
清正公生誕450年没後400年・九州新幹線全線開業記念企画
■第一話「家紋」
古いお家には、それぞれの家紋があります。紋所と呼ばれることもあります。いまはほとんど使われなくなりましたが、和服の正装である紋付羽織は、襟と袖に紋所が入ったものです。
江戸時代には、この紋服だけでなく、家具、調度類、武器、建物、提灯などにも紋所を記して、人目でどの家かわかるようにしていました。
有名なのは徳川家の三つ葉葵()みつばあおいです。水戸光圀の諸国漫遊で、イザというところで「これが見えぬか」と示すのは、印籠にある三つ葉葵ですよね。
それにおとらず有名なのが加藤清正の「蛇の目」の紋所です。蛇の目というのは、二重の幅広の同心円をいいます。二重丸を幅広く描いたのが蛇の目です。
加藤家では、「蛇の目」と「桔梗」の両方の紋を持っていました。もう一つ、硯の紋もあるそうです。

(↑蛇の目の紋)

(↑桔梗の紋)
加藤清正の虎退治の絵は、江戸時代の清正人気の象徴といえる図柄です。清正は、槍の使い手で、烏帽子(えぼし・縦長の被り物)兜にくっきりと蛇の目紋が描かれ、片鎌の槍を構えて、咆哮する虎と対峙する構図は、勇ましいものでした。
富士酒造の加藤家の家紋も「蛇の目」です。古い日本家屋や蔵のあちこちに、蛇の目紋が描かれています。拝見はしていませんが、羽織にも蛇の目が染め抜かれているのでしょう。そのほか、先祖から伝わっている調度類にも蛇の目が印されているのでしょうね。(JS)
Posted by たわらや at
07:06
│Comments(0)
2011年02月09日
鍋島 特別純米 無濾過生原酒
-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№215
鍋島 純米 無濾過生原酒
1800ml:2940円(税込)
◆ 鍋島を醸す富久千代酒造について
江戸時代から続く風情ある街並みを残す、肥前浜宿(ひぜんはましゅく)。浜川沿いには、白壁土蔵造りの酒蔵が立ち並び、地元の人たちはこの通を「酒蔵通り」と呼んでいます。長崎街道多良往還(多良海道)の宿場町としてにぎわい、江戸時代に荷物の輸送拠点だった継場(つぎば)も修復され、新たな観光スポットとして人気です。継場は現在の郵便局といったところでしょうか。継場の前には馬の縄を縛っておく楔があり、当時の賑わいを垣間見ることができます。
その酒蔵通りは、「鍋島」を醸す富久千代酒造だけでなく「金波」「王将」「呉竹」「乾杯」「君恩」「万寿亀」などなど通りにはたくさんの造り酒屋があります。
そんな酒蔵通りの中で、美酒を醸すのは「鍋島」酒蔵当主でもあり、自らが酒を仕込むという・飯盛直喜さんです。
生産規模は500石といいますから、(1升瓶で年間5万本の生産量)、とっても小さな酒蔵です。
◆ 立春をつげる新酒!!
鍋島 純米 無濾過生原酒
鍋島の定番酒といえば「特別純米鍋島」です。そのお酒を、搾ったばかりの状態で直瓶詰めした酒が『純米 無濾過生原酒』です。
味わいは…
飲んだ瞬間「これは旨い」と思わせる美酒
わずかにジュワジュワ、チリチリと微発泡しており、口に含んだ瞬間、
グレープフルーツを彷彿させる爽やかな酸味を帯びた香味を感じる。
鍋島・純米らしく、繊細ながら、コシがしっかりしており、熟成させた時にはよりダイナミックになるような片鱗を感じるフレッシュな新酒です。
すっぴん酒が無濾過生原酒
通常の日本酒は、搾った後、炭素濾過します。濾過することにより酒質は安定しますし、長期保存に向くことになりますが、出来たての「香り」「味わい」「色」が損なわれてしまいます。
このお酒は無濾過で、しかも生の状態で、割り水することなく、搾ったばかりの状態の酒ですので、酒蔵で味わうあの味わいが楽しめます。すっぴんの酒です。
【鍋島 純米無濾過生酒】
春めいてくると飲みたくなる美酒。

原料米: 全量佐賀県産米
精米歩合: 55%
日本酒度:+7.0
酸 度: 1.7
アミノ酸度:?
度数: 17~18%
酵 母:?
鍋島 純米 無濾過生原酒
1800ml:2940円(税込)
◆ 鍋島を醸す富久千代酒造について
江戸時代から続く風情ある街並みを残す、肥前浜宿(ひぜんはましゅく)。浜川沿いには、白壁土蔵造りの酒蔵が立ち並び、地元の人たちはこの通を「酒蔵通り」と呼んでいます。長崎街道多良往還(多良海道)の宿場町としてにぎわい、江戸時代に荷物の輸送拠点だった継場(つぎば)も修復され、新たな観光スポットとして人気です。継場は現在の郵便局といったところでしょうか。継場の前には馬の縄を縛っておく楔があり、当時の賑わいを垣間見ることができます。
その酒蔵通りは、「鍋島」を醸す富久千代酒造だけでなく「金波」「王将」「呉竹」「乾杯」「君恩」「万寿亀」などなど通りにはたくさんの造り酒屋があります。
そんな酒蔵通りの中で、美酒を醸すのは「鍋島」酒蔵当主でもあり、自らが酒を仕込むという・飯盛直喜さんです。
生産規模は500石といいますから、(1升瓶で年間5万本の生産量)、とっても小さな酒蔵です。
◆ 立春をつげる新酒!!
鍋島 純米 無濾過生原酒
鍋島の定番酒といえば「特別純米鍋島」です。そのお酒を、搾ったばかりの状態で直瓶詰めした酒が『純米 無濾過生原酒』です。
味わいは…
飲んだ瞬間「これは旨い」と思わせる美酒
わずかにジュワジュワ、チリチリと微発泡しており、口に含んだ瞬間、
グレープフルーツを彷彿させる爽やかな酸味を帯びた香味を感じる。
鍋島・純米らしく、繊細ながら、コシがしっかりしており、熟成させた時にはよりダイナミックになるような片鱗を感じるフレッシュな新酒です。
すっぴん酒が無濾過生原酒
通常の日本酒は、搾った後、炭素濾過します。濾過することにより酒質は安定しますし、長期保存に向くことになりますが、出来たての「香り」「味わい」「色」が損なわれてしまいます。
このお酒は無濾過で、しかも生の状態で、割り水することなく、搾ったばかりの状態の酒ですので、酒蔵で味わうあの味わいが楽しめます。すっぴんの酒です。
【鍋島 純米無濾過生酒】
春めいてくると飲みたくなる美酒。

原料米: 全量佐賀県産米
精米歩合: 55%
日本酒度:+7.0
酸 度: 1.7
アミノ酸度:?
度数: 17~18%
酵 母:?
Posted by たわらや at
06:14
│Comments(0)
2011年02月08日
鍋島 特別純米 活性にごり生酒
-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№214
鍋島 特別純米 活性にごり生酒
1800ml:2760円(税込)
■ 鍋島の代表銘柄・特別純米酒について語る。
白ワインを注ぐゴブレットに鍋島特別純米が注ぐ。みずみずしいメロンの香りを秘めた酒はとても輝いていました。
鍋島・特別純米酒を「カプっ」と口に放り込みました。芳香というか、酒の放つ香りと同じメロンを彷彿させる含み香りが口いっぱいに広がります。とても余韻が楽しくキレがいい酒です。
もう一つの特徴は、たいへんみずみずしい酒質です。私もたくさんのお酒を利き酒してきましたが、こんなみずみずしく、のびのびとした酒質、飲んでいてホッとするようなオアシスのような酒は初めて出会いました。
思わず、「これ日本酒?」と疑うような酒なんです。そして、価格が非常にリズナブル。この日本酒が嫌いな人はいないのではないかなぁ~、と思いました。酒通の方には強いて勧めませんが、これからお酒を嗜む方やワインが好きな方、肩肘を張らずに気楽に楽しむ酒として、お奨めの一本です。
もう一つ、このお酒が好きになった理由は、酒質も価格もさることながら、地元の酒米、西海134号や佐賀の華を原料米として仕込んでいることです。地米をこのように清楚に表現している酒と出会って嬉しかったです。正直に言って。佐賀の酒のイメージ、日本酒のイメージにまた新しいページが生まれました。
■ジャパニーズ・シャンパーン・鍋島「活性にごり酒」
定番・特別純米酒を厳冬の時期に仕込んでいます。このお酒は、お酒を搾る時、モロミをあらごしした状態で、直接瓶詰めした酒です。予め予約をした限定本数に限り、このような形で瓶詰めをします。
■特徴は瓶内発酵・瓶内熟成
モロミを直接瓶詰めしているため、もちろん、無濾過生原酒。液体の中には、酵母も酵素も生きています。温度を常温に戻すと、活発に発酵が始まります。
日々、酵母と酵素の働きで、アルコール発酵が進んでいます。ですから、日々、味が変化している生きている酒なのです。生産された二酸化炭素は、瓶内から外に出ることができず、酒の中に溶け込みます。
瓶を開けた時に、シュワシュワとした清涼感あふれるのは、瓶内発酵・瓶内熟成の所以です。まさに、ジャパニーズ・シャンパーンです。
切れのよい酒質です。甘みも少なく、上品な酒質。食前酒としてお薦め。春のほろ苦い山菜(たらの芽、蕗のとう)の天麩羅にこの酒はぴったりです。
【鍋島 特別純米酒 活性にごり生酒】

原料米:佐賀県産
山田錦
佐賀の華(等)
精米歩合: 55%
日本酒度: +5.0
酸 度: 1.6ml
アミノ酸度:?
度数:
酵 母: ?
鍋島 特別純米 活性にごり生酒
1800ml:2760円(税込)
■ 鍋島の代表銘柄・特別純米酒について語る。
白ワインを注ぐゴブレットに鍋島特別純米が注ぐ。みずみずしいメロンの香りを秘めた酒はとても輝いていました。
鍋島・特別純米酒を「カプっ」と口に放り込みました。芳香というか、酒の放つ香りと同じメロンを彷彿させる含み香りが口いっぱいに広がります。とても余韻が楽しくキレがいい酒です。
もう一つの特徴は、たいへんみずみずしい酒質です。私もたくさんのお酒を利き酒してきましたが、こんなみずみずしく、のびのびとした酒質、飲んでいてホッとするようなオアシスのような酒は初めて出会いました。
思わず、「これ日本酒?」と疑うような酒なんです。そして、価格が非常にリズナブル。この日本酒が嫌いな人はいないのではないかなぁ~、と思いました。酒通の方には強いて勧めませんが、これからお酒を嗜む方やワインが好きな方、肩肘を張らずに気楽に楽しむ酒として、お奨めの一本です。
もう一つ、このお酒が好きになった理由は、酒質も価格もさることながら、地元の酒米、西海134号や佐賀の華を原料米として仕込んでいることです。地米をこのように清楚に表現している酒と出会って嬉しかったです。正直に言って。佐賀の酒のイメージ、日本酒のイメージにまた新しいページが生まれました。
■ジャパニーズ・シャンパーン・鍋島「活性にごり酒」
定番・特別純米酒を厳冬の時期に仕込んでいます。このお酒は、お酒を搾る時、モロミをあらごしした状態で、直接瓶詰めした酒です。予め予約をした限定本数に限り、このような形で瓶詰めをします。
■特徴は瓶内発酵・瓶内熟成
モロミを直接瓶詰めしているため、もちろん、無濾過生原酒。液体の中には、酵母も酵素も生きています。温度を常温に戻すと、活発に発酵が始まります。
日々、酵母と酵素の働きで、アルコール発酵が進んでいます。ですから、日々、味が変化している生きている酒なのです。生産された二酸化炭素は、瓶内から外に出ることができず、酒の中に溶け込みます。
瓶を開けた時に、シュワシュワとした清涼感あふれるのは、瓶内発酵・瓶内熟成の所以です。まさに、ジャパニーズ・シャンパーンです。
切れのよい酒質です。甘みも少なく、上品な酒質。食前酒としてお薦め。春のほろ苦い山菜(たらの芽、蕗のとう)の天麩羅にこの酒はぴったりです。
【鍋島 特別純米酒 活性にごり生酒】

原料米:佐賀県産
山田錦
佐賀の華(等)
精米歩合: 55%
日本酒度: +5.0
酸 度: 1.6ml
アミノ酸度:?
度数:
酵 母: ?
Posted by たわらや at
06:25
│Comments(0)
2011年02月07日
鍋島 雄町 純米吟醸生酒
-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№213
鍋島 雄町 純米吟醸生酒
1800ml:3360円(税込)
◆鍋島を醸す富久千代酒造について
江戸時代から続く風情ある街並みを残す、肥前浜宿(ひぜんはましゅく)。浜川沿いには、白壁土蔵造りの酒蔵が立ち並び、地元の人たちはこの通を「酒蔵通り」と呼んでいます。長崎街道多良往還(多良海道)の宿場町としてにぎわい、江戸時代に荷物の輸送拠点だった継場(つぎば)も修復され、新たな観光スポットとして人気です。継場は現在の郵便局といったところでしょうか。継場の前には馬の縄を縛っておく楔があり、当時の賑わいを垣間見ることができます。
その酒蔵通りは、「鍋島」を醸す富久千代酒造だけでなく「金波」「王将」「呉竹」「乾杯」「君恩」「万寿亀」などなど通りにはたくさんの造り酒屋があります。
そんな酒蔵通りの中で、美酒を醸すのは「鍋島」酒蔵当主でもあり、自らが酒を仕込むという・飯盛直喜さんです。
生産規模は300石といいますから、(1升瓶で年間3万本の生産量)、とっても小さな酒蔵です。
◆フルボディーのニューフェイス
岡山県赤磐産の『雄町』は、兵庫県吉川産『山田錦』とともに、最良の酒米として有名です。1俵当たりの価格ももちろん日本一高価です。
全国の銘醸蔵で、赤磐産雄町で酒を仕込んでいますが、口の中に入れた時の香味は、山田錦が平面的な味わいが広がるとすれば、雄町は立体的な味わいが広がる。そんな感じがします。山田錦よりもコクと旨味をより強く感じます。
■芳醇&フレッシュ
鍋島 赤磐産雄町 純米吟醸もフルボディーの新しい味わいです。
まさに芳醇&フレッシュという表現がぴったりな酒です。
香りは、マスカットグレープ、ライチ、ラフランス系の芳しい香りが広がります。
味わいは、鍋島らしくみずみずしい味わいに、雄町の迫力のあるコクと旨味が広がります。
酒に力強さを感じます。脂分の多い肉料理にも十分に対応できるフルボディーの酒です。
【鍋島 赤磐産雄町 純米吟醸生酒】

原料米: 岡山県赤磐産雄町
麹米:雄町
掛米:雄町
精米歩合: 50%
日本酒度: +0.0
酸 度: 1.6
アミノ酸度:?
度数: 16.5%
酵 母:?
鍋島 雄町 純米吟醸生酒
1800ml:3360円(税込)
◆鍋島を醸す富久千代酒造について
江戸時代から続く風情ある街並みを残す、肥前浜宿(ひぜんはましゅく)。浜川沿いには、白壁土蔵造りの酒蔵が立ち並び、地元の人たちはこの通を「酒蔵通り」と呼んでいます。長崎街道多良往還(多良海道)の宿場町としてにぎわい、江戸時代に荷物の輸送拠点だった継場(つぎば)も修復され、新たな観光スポットとして人気です。継場は現在の郵便局といったところでしょうか。継場の前には馬の縄を縛っておく楔があり、当時の賑わいを垣間見ることができます。
その酒蔵通りは、「鍋島」を醸す富久千代酒造だけでなく「金波」「王将」「呉竹」「乾杯」「君恩」「万寿亀」などなど通りにはたくさんの造り酒屋があります。
そんな酒蔵通りの中で、美酒を醸すのは「鍋島」酒蔵当主でもあり、自らが酒を仕込むという・飯盛直喜さんです。
生産規模は300石といいますから、(1升瓶で年間3万本の生産量)、とっても小さな酒蔵です。
◆フルボディーのニューフェイス
岡山県赤磐産の『雄町』は、兵庫県吉川産『山田錦』とともに、最良の酒米として有名です。1俵当たりの価格ももちろん日本一高価です。
全国の銘醸蔵で、赤磐産雄町で酒を仕込んでいますが、口の中に入れた時の香味は、山田錦が平面的な味わいが広がるとすれば、雄町は立体的な味わいが広がる。そんな感じがします。山田錦よりもコクと旨味をより強く感じます。
■芳醇&フレッシュ
鍋島 赤磐産雄町 純米吟醸もフルボディーの新しい味わいです。
まさに芳醇&フレッシュという表現がぴったりな酒です。
香りは、マスカットグレープ、ライチ、ラフランス系の芳しい香りが広がります。
味わいは、鍋島らしくみずみずしい味わいに、雄町の迫力のあるコクと旨味が広がります。
酒に力強さを感じます。脂分の多い肉料理にも十分に対応できるフルボディーの酒です。
【鍋島 赤磐産雄町 純米吟醸生酒】

原料米: 岡山県赤磐産雄町
麹米:雄町
掛米:雄町
精米歩合: 50%
日本酒度: +0.0
酸 度: 1.6
アミノ酸度:?
度数: 16.5%
酵 母:?
Posted by たわらや at
08:12
│Comments(0)
2011年02月06日
分かりやすい清酒醸造学 №7 酒母=酛(もと)について
分かりやすい醸造学-7‐酒母=酛(もと)について
◆ 酒の母
酒の母と書いて酒母(しゅぼ)と読みます。または、昔は酛(もと)と言っていました。酒母からお酒が生まれます。
酛という字からも意味が読み取れます。「酉」と「元」で出来ています。「酉」は「さけのとりべん」で、酒を表します。「元」は「みなもと」を意味します。酒の素という意味です。
お酒のいう液体の特徴を一言でいうと『アルコール(エチル)が入っていること』ですね。では、アルコールはどのようにできるかというと、糖分を酵母が食べます。酵母は取り込んだ糖分でエネルギーを得ます。体内で消化して行き、アルコールを排泄するのです。よって、酵母によって糖分がアルコールに変えられているのです。
◆ 酵母はどこにいるのか?
酵母はどこにいるか?ということになります。酵母は微生物です。自然界の空気中を漂っています。目には見えませんが、顕微鏡を使うとはっきり観察することができます。
その酵母にはいろんな種類があります。ワインしたら美味しいワインを造るワイン酵母。焼酎を造る時に使う焼酎酵母。パンの種を造る時に用いるパン酵母。清酒や吟醸酒を造るための清酒酵母、吟醸酒酵母。
中には、アルコール発酵が下手でアルコールを全く造らないダメ酵母もありますし、アルコールの他に人間の人体を害する毒性の物質を造り出す酵母もいます。
現在は、いろんな酵母を培地培養することによって、さまざまな物質を作り出して、さまざまな製品の原料、薬の原料として利用しています。この技術が広い意味で「バイオテクノロジー」といいます。
日本は、資源が乏しい国だけに、酵母や微生物を巧みに使うことによってバイオテクノロジーの先進地でもあります。私たちの現在の生活の中で、この技術無くしては出来上がらないといっても過言ではありません。
ここにおいては、清酒酵母を話題にしたいと思います。
◆ 家付き酵母
「家付き酵母」という言葉を聞いたことがありますか?。
今も、昔も酒造蔵の天井や壁、蔵内の空気中に住みついているいる酵母が『家付き酵母』です。昔は、それぞれの酒蔵の家付き酵母が、自然に桶の中の醪(もろみ)に落下して、酒が仕込まれました。このような家付き酵母は一種の野生酵母であります。安全に安定して醸造することに向いていない傾向にあります。(続)

※写真:千代の園酒造㈱にて 純米吟醸50%精白の酒母(酒母完成) 2003年01月15日
◆ 酒の母
酒の母と書いて酒母(しゅぼ)と読みます。または、昔は酛(もと)と言っていました。酒母からお酒が生まれます。
酛という字からも意味が読み取れます。「酉」と「元」で出来ています。「酉」は「さけのとりべん」で、酒を表します。「元」は「みなもと」を意味します。酒の素という意味です。
お酒のいう液体の特徴を一言でいうと『アルコール(エチル)が入っていること』ですね。では、アルコールはどのようにできるかというと、糖分を酵母が食べます。酵母は取り込んだ糖分でエネルギーを得ます。体内で消化して行き、アルコールを排泄するのです。よって、酵母によって糖分がアルコールに変えられているのです。
◆ 酵母はどこにいるのか?
酵母はどこにいるか?ということになります。酵母は微生物です。自然界の空気中を漂っています。目には見えませんが、顕微鏡を使うとはっきり観察することができます。
その酵母にはいろんな種類があります。ワインしたら美味しいワインを造るワイン酵母。焼酎を造る時に使う焼酎酵母。パンの種を造る時に用いるパン酵母。清酒や吟醸酒を造るための清酒酵母、吟醸酒酵母。
中には、アルコール発酵が下手でアルコールを全く造らないダメ酵母もありますし、アルコールの他に人間の人体を害する毒性の物質を造り出す酵母もいます。
現在は、いろんな酵母を培地培養することによって、さまざまな物質を作り出して、さまざまな製品の原料、薬の原料として利用しています。この技術が広い意味で「バイオテクノロジー」といいます。
日本は、資源が乏しい国だけに、酵母や微生物を巧みに使うことによってバイオテクノロジーの先進地でもあります。私たちの現在の生活の中で、この技術無くしては出来上がらないといっても過言ではありません。
ここにおいては、清酒酵母を話題にしたいと思います。
◆ 家付き酵母
「家付き酵母」という言葉を聞いたことがありますか?。
今も、昔も酒造蔵の天井や壁、蔵内の空気中に住みついているいる酵母が『家付き酵母』です。昔は、それぞれの酒蔵の家付き酵母が、自然に桶の中の醪(もろみ)に落下して、酒が仕込まれました。このような家付き酵母は一種の野生酵母であります。安全に安定して醸造することに向いていない傾向にあります。(続)

※写真:千代の園酒造㈱にて 純米吟醸50%精白の酒母(酒母完成) 2003年01月15日
Posted by たわらや at
17:18
│Comments(0)
2011年02月06日
冨士酒造で神力を仕込3加藤清正公生誕450年没後400年記念
冨士酒造で神力を仕込む №3
-加藤清正公生誕450年 没後400年 九州新幹線全線開業記念企画-
(前回の続き)
■ 栄光冨士・神力の洗米ついて
いよいよ神力の酒づくりがスタートしました。
私たちが食しているご飯用のお米は、精米歩合でいうと97~92%です。しかし、酒を仕込むお米は、高精白しています。栄光冨士「神力」純米吟醸を仕込む場合では、精米歩合50%です。
当然、精米歩合が小さければ、小さいほど、割れやすくなります。しかも、酒米は、米の中心部に「心白」があります。この部分は、特に柔らかい部分です。ですから、日本酒を仕込む場合の洗米作業は、丁寧に、細心の注意を払って、大事に、大事に原料米を洗っていきます。
この時、蔵人は、原料米がどれだけ水を吸収するかを測ります。水に浸す前の白米の重量を測り、洗米後の白米の重量を再び測ります。その差は、白米が吸収した水分ということになります。
冨士酒造では、写真のように最新鋭の洗米用の機械を使っています。水流をおこし、米が割れないように丁寧に洗米する機械です。そして、洗米後の重量を計測してくれるという優れ物です。
写真は洗米した神力が笊に降ろしているところです。真っ白な神力が出されています。
神力の特徴として、お米が硬い傾向にあります。冨士酒造では、神力に吸水することにたいへん気を使ったということでした。
余談ですが、明治時代以後、優れた品種を掛け合わせて品種改良が進みます。神力×亀の尾と交配させて産まれた品種が「五百萬石」「美山錦」「たかね錦」です。現在でもこれらの品種は銘醸地の代表的な酒米として活躍しています。五百萬石も米が硬いと言われますが、この特性は神力譲りの特性なのかもしれません。


※写真提供:冨士酒造より
(つづく)
-加藤清正公生誕450年 没後400年 九州新幹線全線開業記念企画-
(前回の続き)
■ 栄光冨士・神力の洗米ついて
いよいよ神力の酒づくりがスタートしました。
私たちが食しているご飯用のお米は、精米歩合でいうと97~92%です。しかし、酒を仕込むお米は、高精白しています。栄光冨士「神力」純米吟醸を仕込む場合では、精米歩合50%です。
当然、精米歩合が小さければ、小さいほど、割れやすくなります。しかも、酒米は、米の中心部に「心白」があります。この部分は、特に柔らかい部分です。ですから、日本酒を仕込む場合の洗米作業は、丁寧に、細心の注意を払って、大事に、大事に原料米を洗っていきます。
この時、蔵人は、原料米がどれだけ水を吸収するかを測ります。水に浸す前の白米の重量を測り、洗米後の白米の重量を再び測ります。その差は、白米が吸収した水分ということになります。
冨士酒造では、写真のように最新鋭の洗米用の機械を使っています。水流をおこし、米が割れないように丁寧に洗米する機械です。そして、洗米後の重量を計測してくれるという優れ物です。
写真は洗米した神力が笊に降ろしているところです。真っ白な神力が出されています。
神力の特徴として、お米が硬い傾向にあります。冨士酒造では、神力に吸水することにたいへん気を使ったということでした。
余談ですが、明治時代以後、優れた品種を掛け合わせて品種改良が進みます。神力×亀の尾と交配させて産まれた品種が「五百萬石」「美山錦」「たかね錦」です。現在でもこれらの品種は銘醸地の代表的な酒米として活躍しています。五百萬石も米が硬いと言われますが、この特性は神力譲りの特性なのかもしれません。


※写真提供:冨士酒造より
(つづく)
Posted by たわらや at
16:53
│Comments(0)
2011年02月05日
出羽桜 雄町 純米吟醸しぼりたて生酒
-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№212
出羽桜 雄町 純米吟醸 しぼりたて生原酒
500ml:1365円(税込)
※2月5日までにお申し込みをください。2月23日発売ですので、2月下旬ごろ入荷予定です。
◆ 出羽桜「雄町」を醸す出羽桜酒造㈱について
出羽桜酒造は、1980年(昭和55年)に『桜花吟醸』を市販化した。鑑評会用として仕込まれる大吟醸には、お米から醸し出された酒とは思えないほど、リンゴやバナナなど果物を思わせる香気を放つ。しかし、大吟醸はたいへん高価な値段になる。これを市販化するために試行錯誤して造られた酒が『桜花吟醸』だ。酒徒をおっと言わせた。初めて口にした人は、「これが日本酒ならば、今まで飲んでいた日本酒はいったい何ぞや…」。吟醸酒という業界の言葉が、広く日本人に知れ渡ったのは、このお酒が一翼を担ったことは、間違いはない。
吟醸という「道」が日本酒の世界には存在すると私は思う。その道は、日本人の生真面目で、職人気質が造りだした「美」の世界かもしれない。
話が飛躍するが、吟醸づくりも、宇宙開発も、似ている点がある。宇宙へロケットを飛ばして研究するにはそれなりの研究費用がかかる。決して安くはない。宇宙とは人が住めない環境であるが故に、それなりの装備が必要となる。宇宙開発で培った技術が、我々の日常生活で使う道具にフィードバックされて、豊かなでより快適な生活を送ることができているのだ。例えば、テフロン加工のフライパン。昔はよく焦げた。
戦前の品評会、そして、現在も続く新酒鑑評会。大きな蔵も、小さな蔵も、蔵のもてる技術で、小仕込みで酒を醸す。一見、無駄とも思えるのだが、技術を研鑽し、技術を若手に伝授する場になる。
◆ 出羽桜「雄町」純米吟醸しぼりたて生原酒
2009年11月東京で、第1回純米酒大賞制定委員会主催の「純米酒大賞2009」が開催されました。全国84蔵から5部門合わせて137点のエントリーがあり、その中で「出羽桜 純米吟醸 雄町」が見事大賞に輝きました!
2008年の、「純米大吟醸 一路」IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)チャンピオン・サケ受賞に続き、出羽桜の純米造りが高く評価されました。
そして、昨年2010年11月、第2回純米酒大賞制定委員会主催の「純米酒大賞2010」に「愛山」が大賞を受賞。昨年に続き出羽桜が連続受賞しました。
それを記念して、500mlに壜詰めしたしぼりたて生原酒を予約分に限り発売することになりました。
今回初の発売ですので、香味のコメントはできませんが、「雄町」の持つ芳醇にしてキレ良い味。しぼりたてのフレッシュな味わい。きっとご満足いただける酒であると思います。たいへん楽しみな酒が発売されます。
2月5日までにお申し込みをください。2月23日発売ですので、2月下旬ごろ入荷予定です。

<写真は720mlの写真・イメージとして…>
原料米: 岡山県赤磐産 雄町
精米歩合: 50%
日本酒度: +5.0
酸 度: 1.6ml
アミノ酸度:
度数: 17.5%
酵 母: 山形KA酵母
出羽桜 雄町 純米吟醸 しぼりたて生原酒
500ml:1365円(税込)
※2月5日までにお申し込みをください。2月23日発売ですので、2月下旬ごろ入荷予定です。
◆ 出羽桜「雄町」を醸す出羽桜酒造㈱について
出羽桜酒造は、1980年(昭和55年)に『桜花吟醸』を市販化した。鑑評会用として仕込まれる大吟醸には、お米から醸し出された酒とは思えないほど、リンゴやバナナなど果物を思わせる香気を放つ。しかし、大吟醸はたいへん高価な値段になる。これを市販化するために試行錯誤して造られた酒が『桜花吟醸』だ。酒徒をおっと言わせた。初めて口にした人は、「これが日本酒ならば、今まで飲んでいた日本酒はいったい何ぞや…」。吟醸酒という業界の言葉が、広く日本人に知れ渡ったのは、このお酒が一翼を担ったことは、間違いはない。
吟醸という「道」が日本酒の世界には存在すると私は思う。その道は、日本人の生真面目で、職人気質が造りだした「美」の世界かもしれない。
話が飛躍するが、吟醸づくりも、宇宙開発も、似ている点がある。宇宙へロケットを飛ばして研究するにはそれなりの研究費用がかかる。決して安くはない。宇宙とは人が住めない環境であるが故に、それなりの装備が必要となる。宇宙開発で培った技術が、我々の日常生活で使う道具にフィードバックされて、豊かなでより快適な生活を送ることができているのだ。例えば、テフロン加工のフライパン。昔はよく焦げた。
戦前の品評会、そして、現在も続く新酒鑑評会。大きな蔵も、小さな蔵も、蔵のもてる技術で、小仕込みで酒を醸す。一見、無駄とも思えるのだが、技術を研鑽し、技術を若手に伝授する場になる。
◆ 出羽桜「雄町」純米吟醸しぼりたて生原酒
2009年11月東京で、第1回純米酒大賞制定委員会主催の「純米酒大賞2009」が開催されました。全国84蔵から5部門合わせて137点のエントリーがあり、その中で「出羽桜 純米吟醸 雄町」が見事大賞に輝きました!
2008年の、「純米大吟醸 一路」IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)チャンピオン・サケ受賞に続き、出羽桜の純米造りが高く評価されました。
そして、昨年2010年11月、第2回純米酒大賞制定委員会主催の「純米酒大賞2010」に「愛山」が大賞を受賞。昨年に続き出羽桜が連続受賞しました。
それを記念して、500mlに壜詰めしたしぼりたて生原酒を予約分に限り発売することになりました。
今回初の発売ですので、香味のコメントはできませんが、「雄町」の持つ芳醇にしてキレ良い味。しぼりたてのフレッシュな味わい。きっとご満足いただける酒であると思います。たいへん楽しみな酒が発売されます。
2月5日までにお申し込みをください。2月23日発売ですので、2月下旬ごろ入荷予定です。

<写真は720mlの写真・イメージとして…>
原料米: 岡山県赤磐産 雄町
精米歩合: 50%
日本酒度: +5.0
酸 度: 1.6ml
アミノ酸度:
度数: 17.5%
酵 母: 山形KA酵母
Posted by たわらや at
13:00
│Comments(0)
2011年02月05日
冨士酒造で神力を仕込2加藤清正公生誕450年没後400年記念
冨士酒造で神力を仕込む №2 -加藤清正公生誕450年 没後400年 九州新幹線全線開業記念企画-
(前回の続き)
■ 山形酵母について
日本酒は米と米麹、そして日本酒酵母の発酵によって造られます。ひと昔前までは、日本酒の大半が、熊本酵母(協会9号酵母)で仕込まれていました。
酒の特徴は、原料米の選定、酵母の選定で決まります。全国の酒蔵が、こぞって、「山田錦」を使用して、精米歩合35%まで磨き、熊本酵母(協会9号)で仕込む。発酵の経過を、熊本県酒造研究所(香露醸造元)・萱島昭二先生が編み出したB曲線(注)に従ってモロミを管理すると美酒が出来上がります。これは全国新酒鑑評会で金賞を受賞するための方程式とも言われました。YK35(Y=山田錦、K=熊本酵母、35=35%精白)という言葉が生まれました。
そんな時代の中、山形は独自性を打ち出すために、山形県が中心となって、山形に適した酒米の開発、その酒米に適した麹菌の開発、そして適した酵母の開発を進めてきました。現在でこそ、地産地消が声高に言われていますが、そのパイオニアとなったのが、山形酵母であったと記憶します。
山形酵母が生まれたのは昭和61(1986)年。山形のとある酒蔵の蔵付酵母から分離した吟醸用酵母Y-1(YAMAGATA-1)株。その後、ソフト化清酒酵母としてYK-0107株とYK-2911株の2種類を加えて、合計3種類が平成3(1990)年より山形県内の酒蔵に頒布されました。
当時の特徴として、エステル生成量(香りが高い)高く、酸味がやや多めとなる傾向にあります。初めて飲んだ時の感想として「これって、白ワイン?」というような新鮮な印象は忘れられません。
余談だが、この翌年の平成4(1991)年に長野県から長野アルプス酵母が登場し、その後、秋田県から秋田花酵母が登場。全国各地で、それぞれの地産酵母がぞくぞく登場するようになりました。
B曲線(注)…BMD曲線ともいう。これについては、日刊たわらやかわら版2010年08月30日号・知っているようで知らない酒の話№97を参照ください。
■ 熊本神力と山形酵母のコラボ
これまで熊本県山鹿市・千代の園酒造㈱で、平成7年BYより神力を仕込んで参りました。しっかりした味わい、芳醇な旨味を持ちながらキレのよい男酒といったところでしょうか。
山形県の栄光冨士の酒質は、繊細にしてきめ細やかなです。栄光冨士流の神力はきっとお姫様のような柔らかなふんわりした酒質になるのでは~と産まれる前から想像というか希望を持っています。(笑)(つづく)
【目でみる栄光富士流神力の仕込み】


(写真の提供:冨士酒造㈱)
綺麗な麹米です。麹菌の菌糸が米全体にまんべんなく行き届いています。いい麹米ができているようです。
酒造りは、一麹、二酛、三造りと申します。麹づくりが酒づくりの要になります。
きっといい酒ができると思います。楽しみです。
(前回の続き)
■ 山形酵母について
日本酒は米と米麹、そして日本酒酵母の発酵によって造られます。ひと昔前までは、日本酒の大半が、熊本酵母(協会9号酵母)で仕込まれていました。
酒の特徴は、原料米の選定、酵母の選定で決まります。全国の酒蔵が、こぞって、「山田錦」を使用して、精米歩合35%まで磨き、熊本酵母(協会9号)で仕込む。発酵の経過を、熊本県酒造研究所(香露醸造元)・萱島昭二先生が編み出したB曲線(注)に従ってモロミを管理すると美酒が出来上がります。これは全国新酒鑑評会で金賞を受賞するための方程式とも言われました。YK35(Y=山田錦、K=熊本酵母、35=35%精白)という言葉が生まれました。
そんな時代の中、山形は独自性を打ち出すために、山形県が中心となって、山形に適した酒米の開発、その酒米に適した麹菌の開発、そして適した酵母の開発を進めてきました。現在でこそ、地産地消が声高に言われていますが、そのパイオニアとなったのが、山形酵母であったと記憶します。
山形酵母が生まれたのは昭和61(1986)年。山形のとある酒蔵の蔵付酵母から分離した吟醸用酵母Y-1(YAMAGATA-1)株。その後、ソフト化清酒酵母としてYK-0107株とYK-2911株の2種類を加えて、合計3種類が平成3(1990)年より山形県内の酒蔵に頒布されました。
当時の特徴として、エステル生成量(香りが高い)高く、酸味がやや多めとなる傾向にあります。初めて飲んだ時の感想として「これって、白ワイン?」というような新鮮な印象は忘れられません。
余談だが、この翌年の平成4(1991)年に長野県から長野アルプス酵母が登場し、その後、秋田県から秋田花酵母が登場。全国各地で、それぞれの地産酵母がぞくぞく登場するようになりました。
B曲線(注)…BMD曲線ともいう。これについては、日刊たわらやかわら版2010年08月30日号・知っているようで知らない酒の話№97を参照ください。
■ 熊本神力と山形酵母のコラボ
これまで熊本県山鹿市・千代の園酒造㈱で、平成7年BYより神力を仕込んで参りました。しっかりした味わい、芳醇な旨味を持ちながらキレのよい男酒といったところでしょうか。
山形県の栄光冨士の酒質は、繊細にしてきめ細やかなです。栄光冨士流の神力はきっとお姫様のような柔らかなふんわりした酒質になるのでは~と産まれる前から想像というか希望を持っています。(笑)(つづく)
【目でみる栄光富士流神力の仕込み】


(写真の提供:冨士酒造㈱)
綺麗な麹米です。麹菌の菌糸が米全体にまんべんなく行き届いています。いい麹米ができているようです。
酒造りは、一麹、二酛、三造りと申します。麹づくりが酒づくりの要になります。
きっといい酒ができると思います。楽しみです。
Posted by たわらや at
09:15
│Comments(0)
2011年02月04日
出羽桜 愛山 純米大吟醸しぼりたて生酒
-日本酒を楽しもう 先ずは一献-№211
出羽桜 愛山 純米大吟醸 しぼりたて生酒
500ml:1785円(税込)
※2月5日までにお申し込みをください。2月23日発売ですので、2月下旬ごろ入荷予定です。
◆ 出羽桜「愛山」を醸す出羽桜酒造㈱について
出羽桜酒造は、1980年(昭和55年)に『桜花吟醸』を市販化した。鑑評会用として仕込まれる大吟醸には、お米から醸し出された酒とは思えないほど、リンゴやバナナなど果物を思わせる香気を放つ。しかし、大吟醸はたいへん高価な値段になる。これを市販化するために試行錯誤して造られた酒が『桜花吟醸』だ。酒徒をおっと言わせた。初めて口にした人は、「これが日本酒ならば、今まで飲んでいた日本酒はいったい何ぞや…」。吟醸酒という業界の言葉が、広く日本人に知れ渡ったのは、このお酒が一翼を担ったことは、間違いはない。
吟醸という「道」が日本酒の世界には存在すると私は思う。その道は、日本人の生真面目で、職人気質が造りだした「美」の世界かもしれない。
話が飛躍するが、吟醸づくりも、宇宙開発も、似ている点がある。宇宙へロケットを飛ばして研究するにはそれなりの研究費用がかかる。決して安くはない。宇宙とは人が住めない環境であるが故に、それなりの装備が必要となる。宇宙開発で培った技術が、我々の日常生活で使う道具にフィードバックされて、豊かなでより快適な生活を送ることができているのだ。例えば、テフロン加工のフライパン。昔はよく焦げた。
戦前の品評会、そして、現在も続く新酒鑑評会。大きな蔵も、小さな蔵も、蔵のもてる技術で、小仕込みで酒を醸す。一見、無駄とも思えるのだが、技術を研鑽し、技術を若手に伝授する場になる。
◆ 幻の酒米「愛山」について
酒米・愛山(あいやま)は1949年(昭和24年)に兵庫県立農業試験場で開発された酒米です。母系に「愛船117」、父系に「山雄67」を交配させて誕生した酒米。真珠のように大粒で、芯白がとても大きく、最高の酒米として近年・若手醸造家たちが研究し始めている注目の酒米だ。
米の品種ができるまでには、最低でも10年はかかる。昭和24年に誕生ということは、戦中、戦前に、美酒を求めて、先人達が研究を積み重ねた結果である。米を造る技術者の魂、酒を造る蔵人の魂、その思いが一つの「酒」(出羽桜「愛山」純米大吟醸)になりました。
◆ 出羽桜「愛山」純米大吟醸しぼりたて生原酒
2010年11月に開催された純米酒大賞制定委員会(フルネット)主催・市販純米酒の品評会において、最高賞「純米酒大賞」を受賞。
今回、上槽したばかりのしぼりたて原酒を、予約分に限って500mlに壜詰めして発売します。
五味が絶妙に調和した味わいが特徴の「愛山」新酒をどうぞ。
○ 出羽桜「愛山」 純米大吟醸しぼりたて生原酒

※写真は大古酒。イメージ写真です。
原料米: 兵庫県播州産・愛山
精米歩合: 45%
日本酒度: +3.0
酸 度: 1.5ml
アミノ酸度:?
アルコール度数: 17.5%
酵 母: 山形KA酵母
出羽桜 愛山 純米大吟醸 しぼりたて生酒
500ml:1785円(税込)
※2月5日までにお申し込みをください。2月23日発売ですので、2月下旬ごろ入荷予定です。
◆ 出羽桜「愛山」を醸す出羽桜酒造㈱について
出羽桜酒造は、1980年(昭和55年)に『桜花吟醸』を市販化した。鑑評会用として仕込まれる大吟醸には、お米から醸し出された酒とは思えないほど、リンゴやバナナなど果物を思わせる香気を放つ。しかし、大吟醸はたいへん高価な値段になる。これを市販化するために試行錯誤して造られた酒が『桜花吟醸』だ。酒徒をおっと言わせた。初めて口にした人は、「これが日本酒ならば、今まで飲んでいた日本酒はいったい何ぞや…」。吟醸酒という業界の言葉が、広く日本人に知れ渡ったのは、このお酒が一翼を担ったことは、間違いはない。
吟醸という「道」が日本酒の世界には存在すると私は思う。その道は、日本人の生真面目で、職人気質が造りだした「美」の世界かもしれない。
話が飛躍するが、吟醸づくりも、宇宙開発も、似ている点がある。宇宙へロケットを飛ばして研究するにはそれなりの研究費用がかかる。決して安くはない。宇宙とは人が住めない環境であるが故に、それなりの装備が必要となる。宇宙開発で培った技術が、我々の日常生活で使う道具にフィードバックされて、豊かなでより快適な生活を送ることができているのだ。例えば、テフロン加工のフライパン。昔はよく焦げた。
戦前の品評会、そして、現在も続く新酒鑑評会。大きな蔵も、小さな蔵も、蔵のもてる技術で、小仕込みで酒を醸す。一見、無駄とも思えるのだが、技術を研鑽し、技術を若手に伝授する場になる。
◆ 幻の酒米「愛山」について
酒米・愛山(あいやま)は1949年(昭和24年)に兵庫県立農業試験場で開発された酒米です。母系に「愛船117」、父系に「山雄67」を交配させて誕生した酒米。真珠のように大粒で、芯白がとても大きく、最高の酒米として近年・若手醸造家たちが研究し始めている注目の酒米だ。
米の品種ができるまでには、最低でも10年はかかる。昭和24年に誕生ということは、戦中、戦前に、美酒を求めて、先人達が研究を積み重ねた結果である。米を造る技術者の魂、酒を造る蔵人の魂、その思いが一つの「酒」(出羽桜「愛山」純米大吟醸)になりました。
◆ 出羽桜「愛山」純米大吟醸しぼりたて生原酒
2010年11月に開催された純米酒大賞制定委員会(フルネット)主催・市販純米酒の品評会において、最高賞「純米酒大賞」を受賞。
今回、上槽したばかりのしぼりたて原酒を、予約分に限って500mlに壜詰めして発売します。
五味が絶妙に調和した味わいが特徴の「愛山」新酒をどうぞ。
○ 出羽桜「愛山」 純米大吟醸しぼりたて生原酒

※写真は大古酒。イメージ写真です。
原料米: 兵庫県播州産・愛山
精米歩合: 45%
日本酒度: +3.0
酸 度: 1.5ml
アミノ酸度:?
アルコール度数: 17.5%
酵 母: 山形KA酵母
Posted by たわらや at
07:03
│Comments(0)
2011年02月04日
冨士酒造で神力を仕込1加藤清正公生誕450年没後400年記念
冨士酒造で神力を仕込む №1 -加藤清正公生誕450年 没後400年 九州新幹線全線開業記念企画-
■序文
平成23(2011)年は、現在の熊本の礎を築いた加藤清正公生誕450年、没後400年です。併せまして、3月には九州新幹線が全線開業をして、熊本が大きく変わる記念すべき年です。
このことを記念して、山形県鶴岡市の冨士酒造㈱・加藤有慶様に相談して、熊本で私たちが栽培した酒米『神力』で吟醸酒を仕込んでいただけないか依頼していました。快諾を頂きまして、1月17日より、酒づくりが始まりました。このコラムでは、冨士酒造㈱で、神力を仕込む様子をお伝えします。
■ 清正公末裔の造り酒屋
清正公は、今から400年前の1611年3月28日に、二条城で豊臣秀頼と徳川家康の対面の時に、秀頼公のお供として同伴。その後、熊本への帰路、病に伏されて6月24日に他界しました。
家督を継いだ加藤忠広公の時代、1633年に加藤家改易となります。山形県鶴岡藩の徳川家臣・酒井家に1万石で預かりの身となります。加藤家再興することはかなわず、忠廣公は他界しました。
江戸時代中期の安永7年(1778年)、加藤家の末裔とされる加茂屋專之助が酒銘を「冨士」と定め酒造業を始めます。酒名に「冨士」をつける所以は分かりませんが、「冨士」の文字は左右対称をなし、裏表のない酒造りに対する姿勢を貫く意が含まれるといいます。まさに清正公気質がうかがえます。
■ 三つのカン
熊本で栽培した酒米『神力』を、鶴岡の冨士酒造で仕込んでもらいます。
この企画が目指すことは、
①感謝:仰清正公…清正公の遺徳を偲ぶ
②還流(交流):ふれあい…熊本と鶴岡の交流の懸け橋づくり。
③感動:旨い~…新しい吟醸酒の香味創造。
の3つの「感」(カン)です。
■ 山形酵母で仕込む
1月上旬、神力栽培農家・原誠一さんが収穫後冷温庫で保存したいた酒米「神力」を山形県鶴岡市の冨士酒造へ輸送。神力は、鶴岡で50%まで精米されました。
平成7年より、千代の園酒造で仕込んできた神力は、熊本酵母でした。冨士酒造㈱では、神力を山形酵母で仕込むということでした。酵母が変われば、香味の表現も違ってきます。どのような香味になるか、たいへん楽しみです。
そして、1月17日より栄光富士流神力の酒づくりがはじまりました。

これが山形酵母のアンプルです。
この綿栓の瓶に詰められているものが「山形酵母」です。山形酵母だけが純粋培養された液体です。これだけみるとたいへんグロイのですが、酒母(酛)にこの液体を入れて、山形酵母をさらに増殖させて、本仕込みを迎える準備をいたします。
(写真の提供:冨士酒造㈱より)
(続く)
■序文
平成23(2011)年は、現在の熊本の礎を築いた加藤清正公生誕450年、没後400年です。併せまして、3月には九州新幹線が全線開業をして、熊本が大きく変わる記念すべき年です。
このことを記念して、山形県鶴岡市の冨士酒造㈱・加藤有慶様に相談して、熊本で私たちが栽培した酒米『神力』で吟醸酒を仕込んでいただけないか依頼していました。快諾を頂きまして、1月17日より、酒づくりが始まりました。このコラムでは、冨士酒造㈱で、神力を仕込む様子をお伝えします。
■ 清正公末裔の造り酒屋
清正公は、今から400年前の1611年3月28日に、二条城で豊臣秀頼と徳川家康の対面の時に、秀頼公のお供として同伴。その後、熊本への帰路、病に伏されて6月24日に他界しました。
家督を継いだ加藤忠広公の時代、1633年に加藤家改易となります。山形県鶴岡藩の徳川家臣・酒井家に1万石で預かりの身となります。加藤家再興することはかなわず、忠廣公は他界しました。
江戸時代中期の安永7年(1778年)、加藤家の末裔とされる加茂屋專之助が酒銘を「冨士」と定め酒造業を始めます。酒名に「冨士」をつける所以は分かりませんが、「冨士」の文字は左右対称をなし、裏表のない酒造りに対する姿勢を貫く意が含まれるといいます。まさに清正公気質がうかがえます。
■ 三つのカン
熊本で栽培した酒米『神力』を、鶴岡の冨士酒造で仕込んでもらいます。
この企画が目指すことは、
①感謝:仰清正公…清正公の遺徳を偲ぶ
②還流(交流):ふれあい…熊本と鶴岡の交流の懸け橋づくり。
③感動:旨い~…新しい吟醸酒の香味創造。
の3つの「感」(カン)です。
■ 山形酵母で仕込む
1月上旬、神力栽培農家・原誠一さんが収穫後冷温庫で保存したいた酒米「神力」を山形県鶴岡市の冨士酒造へ輸送。神力は、鶴岡で50%まで精米されました。
平成7年より、千代の園酒造で仕込んできた神力は、熊本酵母でした。冨士酒造㈱では、神力を山形酵母で仕込むということでした。酵母が変われば、香味の表現も違ってきます。どのような香味になるか、たいへん楽しみです。
そして、1月17日より栄光富士流神力の酒づくりがはじまりました。

これが山形酵母のアンプルです。
この綿栓の瓶に詰められているものが「山形酵母」です。山形酵母だけが純粋培養された液体です。これだけみるとたいへんグロイのですが、酒母(酛)にこの液体を入れて、山形酵母をさらに増殖させて、本仕込みを迎える準備をいたします。
(写真の提供:冨士酒造㈱より)
(続く)
Posted by たわらや at
06:58
│Comments(0)
2011年02月03日
知っているようで知らない酒の話№129酒蔵の労務管理(後編
知っているようで知らない酒の話 №129 江戸時代の酒蔵の労務管理「後編」
■ 碓屋の職制
米を精米する作業を担当する職人です。お米の外側には、日本酒を仕込んだ時に雑味となる成分が多く含まれています。日本人は経験的にそのことを知っていました。そこで米を搗いて精米するのです。
碓頭(うすがしら)…現在では精米杜氏といいます。精米の部署の責任者です。
桝取(ますとり)…計量する係
米踏(こめふみ)…実際に足踏み精米によって精米する人。
精米の部署でも、上人(じょうびと)・中人(ちゅうびと)・下人(したびと)、飯焚き(ままたき)
がいました。
碓屋は米を精白する米糠で髪の毛から体じゅう真っ白になります。そこで、白子とか白鼠(しろねずみ)とか言われたそうです。
元禄時代、諸白700石(126kl)醸造するために、酒米1000石(150t)を必要としました。
例えば、毎日、毎日、酒米10石ずつ仕込むならば、100日を要します。このことについては、前述いたしました。10石日仕舞蔵での稼働人数は、杜氏、頭、麹師、酛廻りの他に約15名を必要としていたようです。全体で約20名となります。
これに精米を担当する碓屋が20~25名を必要としました。
よって、10石日仕舞蔵では、
製造部署20名+精米部署20~25名、合計40名~45名の職人がいました。
■ 蔵は女人禁制
いつの時代に始まったか分かりませんが、昔は酒造りの蔵の中は女人禁制でした。
厳冬の100日間、若い男衆が大勢いる酒蔵の中に、女性が入ると、集中力が衰えるからだ、とか、酒造りが上々にできるように、酒造りで事故がないように祈願している酒の神様が女性の神様であり、蔵内に女性が入ると嫉妬してしまうからだ、とか諸説あります。
いずれにしても、よい酒を集中して仕込むための戒めを律したことのようです。
■今では
今の酒づくりで、千石蔵でこのような職人はいません。精米は電気によりローラーを回転させ、自動で精米する精米機が取りつけてありますので、ほとんど碓屋はいなくなりました。
酒づくりの部署でも、省力化の機械の導入で蔵人が少なくなっています。
■ 碓屋の職制
米を精米する作業を担当する職人です。お米の外側には、日本酒を仕込んだ時に雑味となる成分が多く含まれています。日本人は経験的にそのことを知っていました。そこで米を搗いて精米するのです。
碓頭(うすがしら)…現在では精米杜氏といいます。精米の部署の責任者です。
桝取(ますとり)…計量する係
米踏(こめふみ)…実際に足踏み精米によって精米する人。
精米の部署でも、上人(じょうびと)・中人(ちゅうびと)・下人(したびと)、飯焚き(ままたき)
がいました。
碓屋は米を精白する米糠で髪の毛から体じゅう真っ白になります。そこで、白子とか白鼠(しろねずみ)とか言われたそうです。
元禄時代、諸白700石(126kl)醸造するために、酒米1000石(150t)を必要としました。
例えば、毎日、毎日、酒米10石ずつ仕込むならば、100日を要します。このことについては、前述いたしました。10石日仕舞蔵での稼働人数は、杜氏、頭、麹師、酛廻りの他に約15名を必要としていたようです。全体で約20名となります。
これに精米を担当する碓屋が20~25名を必要としました。
よって、10石日仕舞蔵では、
製造部署20名+精米部署20~25名、合計40名~45名の職人がいました。
■ 蔵は女人禁制
いつの時代に始まったか分かりませんが、昔は酒造りの蔵の中は女人禁制でした。
厳冬の100日間、若い男衆が大勢いる酒蔵の中に、女性が入ると、集中力が衰えるからだ、とか、酒造りが上々にできるように、酒造りで事故がないように祈願している酒の神様が女性の神様であり、蔵内に女性が入ると嫉妬してしまうからだ、とか諸説あります。
いずれにしても、よい酒を集中して仕込むための戒めを律したことのようです。
■今では
今の酒づくりで、千石蔵でこのような職人はいません。精米は電気によりローラーを回転させ、自動で精米する精米機が取りつけてありますので、ほとんど碓屋はいなくなりました。
酒づくりの部署でも、省力化の機械の導入で蔵人が少なくなっています。
Posted by たわらや at
06:21
│Comments(0)
2011年02月02日
知っているようで知らない酒の話№128酒蔵の労務管理(前編
知っているようで知らない酒の話 №128 江戸時代の酒蔵の労務管理「前編」
■ 千石蔵(江戸時代)の労務管理
労務管理というと、1930年代、アメリカの自動車産業で実践されて世界中にひろまったようでありますが、日本において、17世紀後期にはすでに千石蔵で実践されていたことには驚きます。
造り酒屋における季節労働者の職制が固定化したのは17世紀後期のことであります。江戸への下り酒のため生産規模が拡大し、酒造マニュファクチャー形態が整います。千石蔵で実際的に酒づくりに携わるのは
「蔵人」と「米搗き・碓屋」でした。
「蔵人」とは、千石蔵で直接諸白による酒づくりに従事する職人です。
「米搗き(こめつき)・碓屋(うすや)」は、米を搗く、精米する職人です。
■ 上方の蔵人の職制について
千石蔵が合理的だったのは、この職能により職制を定めて、職人の役割を分掌させていたことでしょう。この辺りをみても、日本人、先人たちの知恵に脱帽します。欧米での労務管理が起こるおよそ300年前にそのような理論が体系化され、当り前に実践されていたのです。
杜氏…オヤジ、親方と言われた。酒蔵の主人から酒蔵における技術や労務の一切を委嘱されて酒造りを行う最高責任者。
頭(かしら)…世話やき、脇、世話役と呼ばれていました。杜氏の補佐役で、蔵人を直接指導し、日常の実務作業を管理しました。杜氏が理事長ならば、頭は専務理事でしょう。
麹師(こうじし)…衛門、大師、代司、麹屋などと呼ばれていました。麹造りの主任です。酒づくりにおいて、一麹、二酛、三造りと言われるように、よい麹を造るか否かで決まります。
酛廻り(もとまわり)…酛屋と言われていました。麹の次に大切なのはいい酛(酒母)を造ることです。酛の管理を行う職人です。
道具廻し…酒づくりに必要な道具類の整備と管理をする人。
釜屋…酒米を蒸すための作業一切を仕切る職人。
上人(じょうびと)・中人(ちゅうびと)・下人(したびと)…頭の指導で、蔵内の雑務に服する職人。経験と技術を持つものが上人。その次が中人。飯焚きから上がって酒づくりに始めて関わる初心者が下人。
飯焚き(ままたき)…蔵人の食事と風呂の係。たいてい、新参のルーキーがこれに当たる。人の世話ができなければ、酒づくりはできない、とある杜氏は言っていました。酒づくりで大切な「察する」ということを学ぶ第一歩の役でした。
(明日は米を搗く職人について書きます)
■ 千石蔵(江戸時代)の労務管理
労務管理というと、1930年代、アメリカの自動車産業で実践されて世界中にひろまったようでありますが、日本において、17世紀後期にはすでに千石蔵で実践されていたことには驚きます。
造り酒屋における季節労働者の職制が固定化したのは17世紀後期のことであります。江戸への下り酒のため生産規模が拡大し、酒造マニュファクチャー形態が整います。千石蔵で実際的に酒づくりに携わるのは
「蔵人」と「米搗き・碓屋」でした。
「蔵人」とは、千石蔵で直接諸白による酒づくりに従事する職人です。
「米搗き(こめつき)・碓屋(うすや)」は、米を搗く、精米する職人です。
■ 上方の蔵人の職制について
千石蔵が合理的だったのは、この職能により職制を定めて、職人の役割を分掌させていたことでしょう。この辺りをみても、日本人、先人たちの知恵に脱帽します。欧米での労務管理が起こるおよそ300年前にそのような理論が体系化され、当り前に実践されていたのです。
杜氏…オヤジ、親方と言われた。酒蔵の主人から酒蔵における技術や労務の一切を委嘱されて酒造りを行う最高責任者。
頭(かしら)…世話やき、脇、世話役と呼ばれていました。杜氏の補佐役で、蔵人を直接指導し、日常の実務作業を管理しました。杜氏が理事長ならば、頭は専務理事でしょう。
麹師(こうじし)…衛門、大師、代司、麹屋などと呼ばれていました。麹造りの主任です。酒づくりにおいて、一麹、二酛、三造りと言われるように、よい麹を造るか否かで決まります。
酛廻り(もとまわり)…酛屋と言われていました。麹の次に大切なのはいい酛(酒母)を造ることです。酛の管理を行う職人です。
道具廻し…酒づくりに必要な道具類の整備と管理をする人。
釜屋…酒米を蒸すための作業一切を仕切る職人。
上人(じょうびと)・中人(ちゅうびと)・下人(したびと)…頭の指導で、蔵内の雑務に服する職人。経験と技術を持つものが上人。その次が中人。飯焚きから上がって酒づくりに始めて関わる初心者が下人。
飯焚き(ままたき)…蔵人の食事と風呂の係。たいてい、新参のルーキーがこれに当たる。人の世話ができなければ、酒づくりはできない、とある杜氏は言っていました。酒づくりで大切な「察する」ということを学ぶ第一歩の役でした。
(明日は米を搗く職人について書きます)
Posted by たわらや at
06:16
│Comments(0)
2011年02月01日
呑んどっと №16 -晴れの酒 卦の酒-
呑んどっと №16 日本酒拡大の次の一手 -晴れの酒 卦の酒-
徐文
11月5日に日刊たわらやかわら版で「絶滅危惧酒」について書きました。元日本吟醸酒協会の会長をなさった篠田次郎先生より、日本酒の消費拡大の次の一手というべきヒントを記したメールが来ました。
消費者の方は、興味があればお読みください。酒造りに携わる方は、是非ご一読をお願いします。
(メールの原文を載せます)
幻の日本酒を飲む会ニュース
平成22年 12月号 Vol.216
「日本酒消費形態の不思議」
(1) 若者からのメール
熊本の弟子、たわらや酒店、宇野功一君からのメール文
◆ 絶滅危惧酒
今年は国連が定める国際生物多様性年です。先日、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が、名古屋で開催されたことは、皆様もニュース等でご存知と思います。世界には多くの絶滅危惧に瀕した動植物が存在します。人類が生態系を壊した反動で、多くの生物が危機に瀕しているというものです。
絶滅とは申しませんが、危機的な存在なのが日本酒です。
私も今年の秋にいろんなところで日本酒の会を企画しています。どの会も人数が集まり、大盛況なのです。が、実際のところ、消費を下支えするような動きになっていません。日本酒と焼酎を同時に出す酒の会では、日本酒のブースにお客様が群がり、日本酒から売り切れになってしまいます。日本酒は特別な酒になってしまっているのです。
日本人は日本酒が嫌いになっている訳ではないようです。普段は焼酎を口にする人でも、日本酒の会(イベント)の時は、日本酒を飲んでくれます。普段の晩酌は焼酎、普段居酒屋で飲む酒も焼酎、イベントの時は日本酒という消費行動なのです。
--以上は宇野君の文章そのままである。宇野君(彼は東京農工大出身だから、酒の世界では先生と呼ばれることもあるが、このニュースでは'君'で呼ばせてもらう)は、酒販店の息子として育ち、東京農工大に進み、そこで吟醸酒に出会った。
これを学びたくて、人を頼り頼り、私の許にやってきて、留年して同大を出た。
焼酎の主産地にありながら、日本酒に深い愛情を持っているのは文章からわかるだろう。--同君のメールは「たわらや瓦版11月5日付」から
12月01日号「日刊たわらやかわら版」にて、篠田次郎先生が述べる日本酒消費拡大のカギについて、項目をおって書いた内容を掲載しています。その続きを考察します。
■「晴れの日の酒、卦(け)の日の酒」
「晴れの日と卦の日」について説明しなければならないでしょう。これは六曜制(大安・仏滅・友引・赤口・先勝・先負の六曜)や民間信仰の陰陽と違って、何かの法則にしたがってやってくるとかではありません。それぞれの人が、その環境で、「晴れの日」だったり「卦(け)の日」だったり。
晴れの日とは、その人にとって「おめでたい」とか「運がいい」とか「ついている」とか。事前に決めてもいいのです。この晴れの日には、いいことがあるとして、それに対応する行動をするのです。
卦の日は、晴れの日以外のすべての日をいいます。いわば普段の日というところでしょうか。
この区別は世間の約束事ではなく、個人個人のものなのです。私にもこのような晴れと卦があるようで、なにかよいことがあるとか、よさそうとか、よくなればいいと思う、そんな日は晴れです。ですから、毎日がお祭りということになりましょうか。
それを意識しない日、別に卦の日とはいいませんが、普段の日として迎え、送ります。
(2)
昨年12月号の主題、「日本酒消費形態の不思議」は、熊本の酒販店、たわらや宇野功一君が彼のメルマガ「たわらや瓦版・11月5日号」で提示した問題です。彼は焼酎の本場で、彼が開く、または参加する日本酒きき酒会や飲む会、パーティーはどれも参加者が多く盛大だといっています。日本酒と焼酎が並ぶものは、日本酒が先に費消されてしまうそうです。
それなのに、その人気の日本酒が実需につながらないといっているのです。なぜか?
宇野君のその疑問に、彼に吟醸酒を教えた私(篠田次郎)として何らかの回答をしなければならないと思って、「日本酒消費形態の不思議」を書いたのでした。明確な答えは出ませんでした。私にも答えが見つからなかったのです。
それで、吟醸酒が世間にデビューする飲酒形態として、比べ飲みという形があり、これの波及能力が小さいこと。そもそも日本酒は、かつて三増醸酒というかなり怪しげな製法を認められ、その方法で作られた酒が、今日でも相当量出ていること。だから、マスコミが、比べ飲みして楽しい吟醸酒 を取り上げないこと。もっと大きくいうと、日本酒業界は、比べ飲みされると困るという体質であること。などを私の解答にした。
極論すれば、日本酒を助ける可能性のある吟醸酒品質を、日本酒業界がアピールしていないところが根本原因だとしたのである。
私は宇野君に、
「たぶんあなたが私の事務所にいたとき検討したと思いますが、飲ませるビジネスと売るビジネス、その間をまたいだ楽しい情報発信が、新市場を形成していくと。」
これを答えとしました。それが12月号ニュースだったのです。
(3)
盛岡で熱心な吟醸酒ファンのSさんと再会し、夜遅くから翌朝まで語りました。
その話題の一つに、「日本酒消費形態の不思議」をあげました。Sさんはしばらく考えてから、「晴れの日の酒、卦の日の酒」を言い出したのです。
いうまでもなく、心が弾む日は吟醸酒を飲もうと思う。そして、きき酒会や日本酒パーティーに出る日は晴れの日と思うのだというのです。
その他の日は卦の日で、焼酎を飲むのだと。
Sさんのこの説に対しては、反論はできませんでした。「なるほど」と納得してしまったのです。まぁ、懸案の課題がこのSさんの説で全部解けるわけではありませんが、考え方は否定できません。
私の飲酒経歴にも「晴れの日卦の日の酒」というのがありましたね。酒とは、飲むだけの関係だった学生時代は、晴れの日の酒は日本酒(二日酔い覚悟で)、ビール(女性のサービスが受けられる店、値段が高かった)でした。その他、つまり卦の日はブドー割焼酎でした。それさえも、小さい財布を搾り出してでした。
酒に関係ない社会人時代は、ビール、日本酒、ブドー割り焼酎、密造どぶろくでした。このどぶろくは、高度成長時代に入り、身の回りから消えていきます。
酒に関係ある社会人時代になり、ビール、日本酒、合成酒、焼酎の順になります。他の人たちは、ビール、ハイボール、このハイボールのウイスキーが特・一級ものと二級もの(トリスクラス)に別れ、日本酒と焼酎が消えていく。
昭和50年に吟醸酒が商品として芽生え、昭和60年から平成時代にかけて、吟醸酒の比べ飲みパーティーが少しずつ開かれていくのに合わせて、吟醸酒はステータスとなる。
吟醸酒を作り続けた、あるいはすばらしい吟醸品質を世に出した蔵の吟醸銘柄が「晴れの日の酒」に位置づけられる。この流れには説得されます。吟醸銘柄の蔵も、吟醸をつくりながら売れていない蔵も納得せざるを得ないでしょう。悦に入っている蔵もあります。
(4)
晴れの日に吟醸酒を飲む。飲まれる吟醸酒蔵は「よござんした」ですね。
ほかの日は焼酎(これも高低ありますが)、安価日本酒となりましょうか。
ところが吟醸酒を知った人は、安価日本酒には行かないのです。
この構造だと「飲まれていない、売れていない吟醸銘柄」は割り込む隙間がありません。この部分の蔵元は、吟醸をつくっても売れず、廉価商品では量産蔵、宣伝できる蔵にかなわない。つまり立ち行かないということになりますね。
酒類消費の構造が見えてきました。その結果、立ち行かない業者があることがわかりました。世に酒造組合中央会という全国規模の団体があるそうですが、中央会さん、どうしてくれます。「そりゃ、個々の業者の努力不足だ」とおっしゃるのですか。では「どういう努力をしたらいいのですか? 道は示されているのでしょうか?」
こういうことに答えられない機構は「あってもなくてもいい」のです。「あってもなくてもいい」ものは、ないほうがいいんですね。
(5)
では、晴れの日に飲まれる吟醸酒蔵は安泰なのでしょうか。立ち行かない蔵、何の示唆も受けられない蔵から見れば安泰といえますが、家の外には七人の敵がいるんですよ。
晴れの日の酒の間の競争。
多くの飲酒者の晴れと卦の日の酒を考えてみましょう。
*醸造酒グループ
a/a) ハレ:吟醸酒(銘柄品または専門家の推薦するもの。ケ:焼酎・廉価日本酒。)
a/b) ハレ:銘柄ワイン。ケ:廉価ワイン
a/c)ハレ:ビール。ケ:ビール系飲料。このグループは、ハレ:プレミアムビ
ール。ケ:スタンダードビール。というのもあるでしょう。でも概して、プレミアムの人、スタンダードの人、ビール風の人とハレもケもなく分かれているでしょう。
*蒸留酒グループ
d/d) ハレ:ブランド焼酎。ケ:安価な焼酎。
d/e) ハレ:ブランドウイスキー。ケ:安価ウイスキー。このグループは、ブランドものだけを飲んでいるでしょう。
*f)こだわらずに酒を飲むグループ。
酒類消費者の行動は、上記6つに分類されていると思います。
飲酒消費者は、酒になじんでいくとき、ぼんやりと入っていくのでしょう。つまり'f'状態だと思います。その後、宣伝の影響、世間の評判、先輩のアドバイス、自分の好みなどによって、'a/aからc/eへと深入りするものと思います。この深さも、人によってまちまちで、いろいろのをやったり、移転したり、深くなじんだりとなりましょう。
(6)
こうして酒類消費者のビヘーバー・行動を分析すると、日本酒は吸引力で弱いと感じるのは筆者だけでしょう。
まず消費者が酒類と初対面のとき、日本酒を選ぶ確立は「限りなく低い」ですね。
この文章の読者(日本酒ファンか関係者だと思いますが)は、日本酒関連業界の人か、消費者の場合は、たぶんいい日本酒の魅力を知る先輩に教わったのだと思います。日本酒は、このスタート時点ですでに不利です。
さらに、「おいしくない日本酒」に出会った人が、「おいしい日本酒」に移る可能性は、「a/bからd/eに移る確立より低いですね。
とすると、日本酒業界は、入り口でダメ、せっかくシンパになっても、他酒類に流れる可能性大では、将来は真っ暗というわけです。
徐文
11月5日に日刊たわらやかわら版で「絶滅危惧酒」について書きました。元日本吟醸酒協会の会長をなさった篠田次郎先生より、日本酒の消費拡大の次の一手というべきヒントを記したメールが来ました。
消費者の方は、興味があればお読みください。酒造りに携わる方は、是非ご一読をお願いします。
(メールの原文を載せます)
幻の日本酒を飲む会ニュース
平成22年 12月号 Vol.216
「日本酒消費形態の不思議」
(1) 若者からのメール
熊本の弟子、たわらや酒店、宇野功一君からのメール文
◆ 絶滅危惧酒
今年は国連が定める国際生物多様性年です。先日、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が、名古屋で開催されたことは、皆様もニュース等でご存知と思います。世界には多くの絶滅危惧に瀕した動植物が存在します。人類が生態系を壊した反動で、多くの生物が危機に瀕しているというものです。
絶滅とは申しませんが、危機的な存在なのが日本酒です。
私も今年の秋にいろんなところで日本酒の会を企画しています。どの会も人数が集まり、大盛況なのです。が、実際のところ、消費を下支えするような動きになっていません。日本酒と焼酎を同時に出す酒の会では、日本酒のブースにお客様が群がり、日本酒から売り切れになってしまいます。日本酒は特別な酒になってしまっているのです。
日本人は日本酒が嫌いになっている訳ではないようです。普段は焼酎を口にする人でも、日本酒の会(イベント)の時は、日本酒を飲んでくれます。普段の晩酌は焼酎、普段居酒屋で飲む酒も焼酎、イベントの時は日本酒という消費行動なのです。
--以上は宇野君の文章そのままである。宇野君(彼は東京農工大出身だから、酒の世界では先生と呼ばれることもあるが、このニュースでは'君'で呼ばせてもらう)は、酒販店の息子として育ち、東京農工大に進み、そこで吟醸酒に出会った。
これを学びたくて、人を頼り頼り、私の許にやってきて、留年して同大を出た。
焼酎の主産地にありながら、日本酒に深い愛情を持っているのは文章からわかるだろう。--同君のメールは「たわらや瓦版11月5日付」から
12月01日号「日刊たわらやかわら版」にて、篠田次郎先生が述べる日本酒消費拡大のカギについて、項目をおって書いた内容を掲載しています。その続きを考察します。
■「晴れの日の酒、卦(け)の日の酒」
「晴れの日と卦の日」について説明しなければならないでしょう。これは六曜制(大安・仏滅・友引・赤口・先勝・先負の六曜)や民間信仰の陰陽と違って、何かの法則にしたがってやってくるとかではありません。それぞれの人が、その環境で、「晴れの日」だったり「卦(け)の日」だったり。
晴れの日とは、その人にとって「おめでたい」とか「運がいい」とか「ついている」とか。事前に決めてもいいのです。この晴れの日には、いいことがあるとして、それに対応する行動をするのです。
卦の日は、晴れの日以外のすべての日をいいます。いわば普段の日というところでしょうか。
この区別は世間の約束事ではなく、個人個人のものなのです。私にもこのような晴れと卦があるようで、なにかよいことがあるとか、よさそうとか、よくなればいいと思う、そんな日は晴れです。ですから、毎日がお祭りということになりましょうか。
それを意識しない日、別に卦の日とはいいませんが、普段の日として迎え、送ります。
(2)
昨年12月号の主題、「日本酒消費形態の不思議」は、熊本の酒販店、たわらや宇野功一君が彼のメルマガ「たわらや瓦版・11月5日号」で提示した問題です。彼は焼酎の本場で、彼が開く、または参加する日本酒きき酒会や飲む会、パーティーはどれも参加者が多く盛大だといっています。日本酒と焼酎が並ぶものは、日本酒が先に費消されてしまうそうです。
それなのに、その人気の日本酒が実需につながらないといっているのです。なぜか?
宇野君のその疑問に、彼に吟醸酒を教えた私(篠田次郎)として何らかの回答をしなければならないと思って、「日本酒消費形態の不思議」を書いたのでした。明確な答えは出ませんでした。私にも答えが見つからなかったのです。
それで、吟醸酒が世間にデビューする飲酒形態として、比べ飲みという形があり、これの波及能力が小さいこと。そもそも日本酒は、かつて三増醸酒というかなり怪しげな製法を認められ、その方法で作られた酒が、今日でも相当量出ていること。だから、マスコミが、比べ飲みして楽しい吟醸酒 を取り上げないこと。もっと大きくいうと、日本酒業界は、比べ飲みされると困るという体質であること。などを私の解答にした。
極論すれば、日本酒を助ける可能性のある吟醸酒品質を、日本酒業界がアピールしていないところが根本原因だとしたのである。
私は宇野君に、
「たぶんあなたが私の事務所にいたとき検討したと思いますが、飲ませるビジネスと売るビジネス、その間をまたいだ楽しい情報発信が、新市場を形成していくと。」
これを答えとしました。それが12月号ニュースだったのです。
(3)
盛岡で熱心な吟醸酒ファンのSさんと再会し、夜遅くから翌朝まで語りました。
その話題の一つに、「日本酒消費形態の不思議」をあげました。Sさんはしばらく考えてから、「晴れの日の酒、卦の日の酒」を言い出したのです。
いうまでもなく、心が弾む日は吟醸酒を飲もうと思う。そして、きき酒会や日本酒パーティーに出る日は晴れの日と思うのだというのです。
その他の日は卦の日で、焼酎を飲むのだと。
Sさんのこの説に対しては、反論はできませんでした。「なるほど」と納得してしまったのです。まぁ、懸案の課題がこのSさんの説で全部解けるわけではありませんが、考え方は否定できません。
私の飲酒経歴にも「晴れの日卦の日の酒」というのがありましたね。酒とは、飲むだけの関係だった学生時代は、晴れの日の酒は日本酒(二日酔い覚悟で)、ビール(女性のサービスが受けられる店、値段が高かった)でした。その他、つまり卦の日はブドー割焼酎でした。それさえも、小さい財布を搾り出してでした。
酒に関係ない社会人時代は、ビール、日本酒、ブドー割り焼酎、密造どぶろくでした。このどぶろくは、高度成長時代に入り、身の回りから消えていきます。
酒に関係ある社会人時代になり、ビール、日本酒、合成酒、焼酎の順になります。他の人たちは、ビール、ハイボール、このハイボールのウイスキーが特・一級ものと二級もの(トリスクラス)に別れ、日本酒と焼酎が消えていく。
昭和50年に吟醸酒が商品として芽生え、昭和60年から平成時代にかけて、吟醸酒の比べ飲みパーティーが少しずつ開かれていくのに合わせて、吟醸酒はステータスとなる。
吟醸酒を作り続けた、あるいはすばらしい吟醸品質を世に出した蔵の吟醸銘柄が「晴れの日の酒」に位置づけられる。この流れには説得されます。吟醸銘柄の蔵も、吟醸をつくりながら売れていない蔵も納得せざるを得ないでしょう。悦に入っている蔵もあります。
(4)
晴れの日に吟醸酒を飲む。飲まれる吟醸酒蔵は「よござんした」ですね。
ほかの日は焼酎(これも高低ありますが)、安価日本酒となりましょうか。
ところが吟醸酒を知った人は、安価日本酒には行かないのです。
この構造だと「飲まれていない、売れていない吟醸銘柄」は割り込む隙間がありません。この部分の蔵元は、吟醸をつくっても売れず、廉価商品では量産蔵、宣伝できる蔵にかなわない。つまり立ち行かないということになりますね。
酒類消費の構造が見えてきました。その結果、立ち行かない業者があることがわかりました。世に酒造組合中央会という全国規模の団体があるそうですが、中央会さん、どうしてくれます。「そりゃ、個々の業者の努力不足だ」とおっしゃるのですか。では「どういう努力をしたらいいのですか? 道は示されているのでしょうか?」
こういうことに答えられない機構は「あってもなくてもいい」のです。「あってもなくてもいい」ものは、ないほうがいいんですね。
(5)
では、晴れの日に飲まれる吟醸酒蔵は安泰なのでしょうか。立ち行かない蔵、何の示唆も受けられない蔵から見れば安泰といえますが、家の外には七人の敵がいるんですよ。
晴れの日の酒の間の競争。
多くの飲酒者の晴れと卦の日の酒を考えてみましょう。
*醸造酒グループ
a/a) ハレ:吟醸酒(銘柄品または専門家の推薦するもの。ケ:焼酎・廉価日本酒。)
a/b) ハレ:銘柄ワイン。ケ:廉価ワイン
a/c)ハレ:ビール。ケ:ビール系飲料。このグループは、ハレ:プレミアムビ
ール。ケ:スタンダードビール。というのもあるでしょう。でも概して、プレミアムの人、スタンダードの人、ビール風の人とハレもケもなく分かれているでしょう。
*蒸留酒グループ
d/d) ハレ:ブランド焼酎。ケ:安価な焼酎。
d/e) ハレ:ブランドウイスキー。ケ:安価ウイスキー。このグループは、ブランドものだけを飲んでいるでしょう。
*f)こだわらずに酒を飲むグループ。
酒類消費者の行動は、上記6つに分類されていると思います。
飲酒消費者は、酒になじんでいくとき、ぼんやりと入っていくのでしょう。つまり'f'状態だと思います。その後、宣伝の影響、世間の評判、先輩のアドバイス、自分の好みなどによって、'a/aからc/eへと深入りするものと思います。この深さも、人によってまちまちで、いろいろのをやったり、移転したり、深くなじんだりとなりましょう。
(6)
こうして酒類消費者のビヘーバー・行動を分析すると、日本酒は吸引力で弱いと感じるのは筆者だけでしょう。
まず消費者が酒類と初対面のとき、日本酒を選ぶ確立は「限りなく低い」ですね。
この文章の読者(日本酒ファンか関係者だと思いますが)は、日本酒関連業界の人か、消費者の場合は、たぶんいい日本酒の魅力を知る先輩に教わったのだと思います。日本酒は、このスタート時点ですでに不利です。
さらに、「おいしくない日本酒」に出会った人が、「おいしい日本酒」に移る可能性は、「a/bからd/eに移る確立より低いですね。
とすると、日本酒業界は、入り口でダメ、せっかくシンパになっても、他酒類に流れる可能性大では、将来は真っ暗というわけです。
Posted by たわらや at
06:48
│Comments(0)